
美術品や骨董品等の相続税評価方法と税務上の重要ポイント
骨董品等の相続税評価は「鑑定人しだい」で何十倍も異なることもありえます。そんな骨董品等の相続税評価方法や物納、寄付を利用した相続税対策などについて解説しています。
骨董品等の相続税評価は「鑑定人しだい」で何十倍も異なることもありえます。そんな骨董品等の相続税評価方法や物納、寄付を利用した相続税対策などについて解説しています。
美術品や工芸品、書画骨董品等の相続税評価方法は
等を参酌して評価します。
ただし、購入時に数十万円程度のものであれば、電化製品や家具と同じように家財として申告できます。

売買実例価額とは、同じようなものが売りにだされている金額で、精通者意見価格とは専門家(鑑定人)が査定した金額のことです。
また、美術年鑑も参考になります。
美術年鑑には保存状態が完壁とした場合の、デパートや画廊が顧客に売却する際の参考価格が記載されています。
ただし、美術年鑑は購入価額が載っているのであり、価値(財産評価額)が載っているわけではありません。
美術年鑑に載っているような美術品・骨童品の場合には、専門家による鑑定で評価しましょう。
また、相当高額になりそうな美術品や骨童品などの場合にも、専門家(鑑定人)に査定してもらいましょう。
鑑定人に資格はありません。
なので、鑑定人にしだいで評価額が「何十倍にも異なってくる」ことがあります。
また、逆に「美術年鑑の記載価格」と「鑑定人による鑑定価格」が大きく異なることも珍しくありません。
あくまでも美術年鑑に載っている価額は購入価額であり、価値(財産評価額)が載っているわけではないからです。
鑑定の結果、美術年鑑の金額の数十分の一にまで下がることもあり得ます。
なので、鑑定人へ査定をお願いする時には「実績があり信頼できる鑑定人」にお願いしましょう。

ただ、鑑定費用は相続税の計算上控除できません。
評価額よりも費用の方が高くついた。
こんなことが起きないように注意しましょう。
価値の高い骨董品等を相続しても、相続税の納税資金に困っている。
そのような場合、骨董品等の物納で相続税を納税したいという方もおられます。
物納制度とは、納税期限までに現金での納税が厳しい場合に、現金の代わりに物で支払うという制度です。
詳しくは相続税の物納制度の利用は簡単ではない!その仕組みや手続方法に記載していますが、物納には物納が出来る順番というものがあります。
骨董品等の物納は順位が低く、現実的ではありません。
なので納税に困っている場合には、骨董品等を「売却した代金で相続税を払う」のが現実的です。

ただ、【特定登録美術品に該当する】ものであれば、順位に関係なく物納をすることが出来ます。
特定登録美術品とは、美術品の美術館における公開の促進に関する法律第2条第3号に規定する登録美術品で、相続開始の時において既に登録を受けているものをいいます。
被相続人(故人)の美術品や工芸品、書画骨董品等を相続してもうれしくない。
そういう方もいらっしゃると思います。
もしも、骨董品等をいらないという場合には、価値の高い美術品等については、国や地方公共団体等の運営する美術館等に寄付をするという方法もあります。
寄付として受け入れてもらえれば、その美術品や骨董品に対する相続税は発生しません。
なので、受け入れてもらえれば、寄付は相続税対策になります。
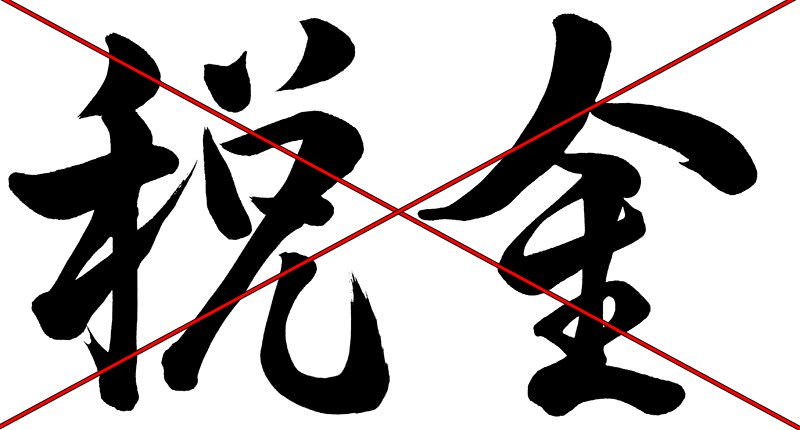
また、相続税対策として寄付が有効という面もありますが、いらないと思っている方が持ち続けるよりも、必要とし大切に保管してくれる美術館等に寄付されるほうが、被相続人も喜ぶ可能性が高いとも思われます。
もしも、相続税の納税に困った場合には、売却して相続税を捻出することも大切ですが、「寄付をして相続税そのものを減らす」という相続税対策も検討してみる価値はあります。
売却して相続税を捻出する場合には、専門家や専門事業者に相談しましょう。
通常、骨董品等を売却するといっても、買い手を探すのは大変です。
専門家であれば買い手を探すことはもちろん、オークションに持ち込み売却することも可能になるかもしれません。

美術品や骨董品等の相続税評価方法について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
美術品、骨とう品の評価は、売買実例価額や精通者意見価格を参考にして評価することとなります。
ただし、購入時に数十万程度のものであれば、電化製品や家具と同様に家財として申告が可能です。
ここで売買実例価額とは、その美術品や骨とう品の類似品が売り出されている場合の、その売り出されている金額を指します。
また、精通者意見価格とは専門家が査定した金額をいいます。
売買実例価額は金額自体が把握しづらいこと、そして精通者意見価格は鑑定人によって、金額が変わるということが大きな問題となってまいります。
ですので、できれば信頼のできる鑑定人に評価してもらうことをおすすめ致します。
ここで鑑定費用は相続税の計算上控除ができませんので、鑑定費用がものすごく高い場合はご注意下さい。
また美術品・骨とう品について、相続しても相続税の支払が大変だと思われる方やそもそも、そういったものにご興味がないという方でしたら、国や地方公共団体が運営する美術館などに寄付をするという方法もございます。
寄附をした場合には相続税はかかりません。
あるいは売却をして現金に換えるという方法もございます。
どちらがよいかはケースバイケースですので、何かお困りな事がございましたならば税理士法人・都心綜合会計事務所までご連絡下さい。