
家族信託は相続対策の最前線
今後の相続対策の最前線として、認知症対策が見過ごせない状況です。そして認知症対策には、家族信託が有効な方法です。家族信託は今後の相続税対策、及び財産管理の主流になる可能性があります。それは家族信託を利用すれば【相続に関するマイルール】の作成が可能だからです。
今後の相続対策の最前線として、認知症対策が見過ごせない状況です。そして認知症対策には、家族信託が有効な方法です。家族信託は今後の相続税対策、及び財産管理の主流になる可能性があります。それは家族信託を利用すれば【相続に関するマイルール】の作成が可能だからです。
相続税対策として
など、様々な書籍やメディアなどで目に触れた方も多数いらっしゃると思います。
どの相続税対策が一番有効か?
それは置かれた環境や財産状況により、一概に○○が最も有効な相続税対策です、とは言えません。
ただ、今後の相続税対策の最前線は「認知症対策が中心となってくる可能性」があります。
なぜ認知症対策が相続税対策の最前線になるのかというと、認知症になると有効な相続税対策ができなくなるからです。
被相続人が認知症になると、自身の財産処分や生前贈与ができません。
最前線の節税方法や相続税対策というのは、税制改正などもあり時代とともに変わっていきます。
そして認知症になると、この最前線の節税方法や相続税対策ができなくなります。
また、相続税対策以外にも様々な問題が発生します。(詳しくは認知症だと法律行為ができず【財産の管理や処分】ができないに記載しています。)
しかし、認知症対策と言っても誰がなるのかは分かりません。
そこで今、家族信託というものが注目されています。
家族信託を利用すれば、被相続人が認知症になったとしても、有効な相続税対策などが打て、また家族が被相続人の財産を管理・処分することができるからです。

ただし、認知症になってからでは、家族信託を利用することはできません。
被相続人が認知症になる前に始める必要があります。
団塊の世代が75歳を迎える2025年には、高齢者の5人に1人が認知症患者になると言われています。
その数なんと700万人。
日本中で認知症患者を見る日が、すぐ近くまで来ているのかもしれません。

そして認知症になると、生前贈与ができなくなるのはもちろん、財産が凍結されます。
こうなってくると有効な相続税対策は?などと言ってられない状況になります。
認知症になった場合には「成年後見人制度を利用する」しか手はなくなります。
しかしながら、この制度は「認知症の方の財産を守る」という意味合いの強い制度です。
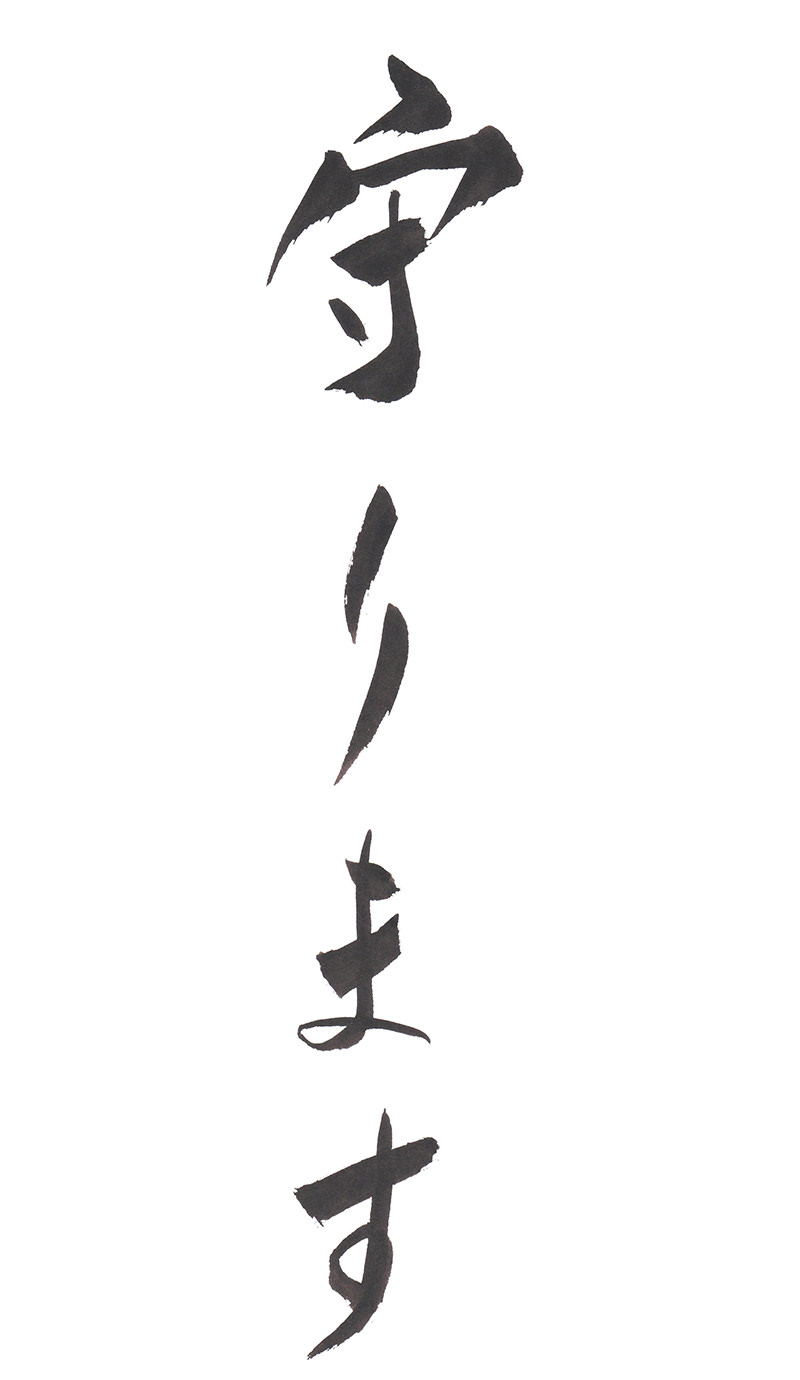
したがって、財産を処分したり贈与したりする行為は「認知症の方の財産を減らす行為」として様々な制約を受けます。
それがいかに有効な相続税対策であったとしても、この制度のもとで実行することは難しくなります。
さらに成年後見制度では、その活動内容を家庭裁判所に報告しなければなりません。
これに対して「家族信託は個人同士の契約」です。

内容は家庭の事情に合わせて、柔軟に決めることができます。
5人に1人が認知症になると言われている時代。
認知症になる前に家族信託の検討を始めましょう。
家族信託は本人(被相続人)の意向に従い、財産の管理処分を家族に任せることができます。
ここでは簡単にご紹介しますと、以下のようなことが可能です。
家族信託の場合、成年後見人制度では到底できなかった財産の活用ができます。
例えば、認知症の親に代わって不動産を売却することも、売却して新しい建物を建てることなども可能です。
また、預金の解約なども可能です。
さらに遺言でも不可能な「次の次の世代まで」相続を指定することができます。
どういうことかと言いますと、遺言では子供(A)に○○を相続させる、という指定はできます。
ただし、Aに○○を相続させた後に、次は○○をAの子供のBに相続させる、というような指定はできません。
これが家族信託の場合はできるのです。
次の次の承継先まで指定できるのです。
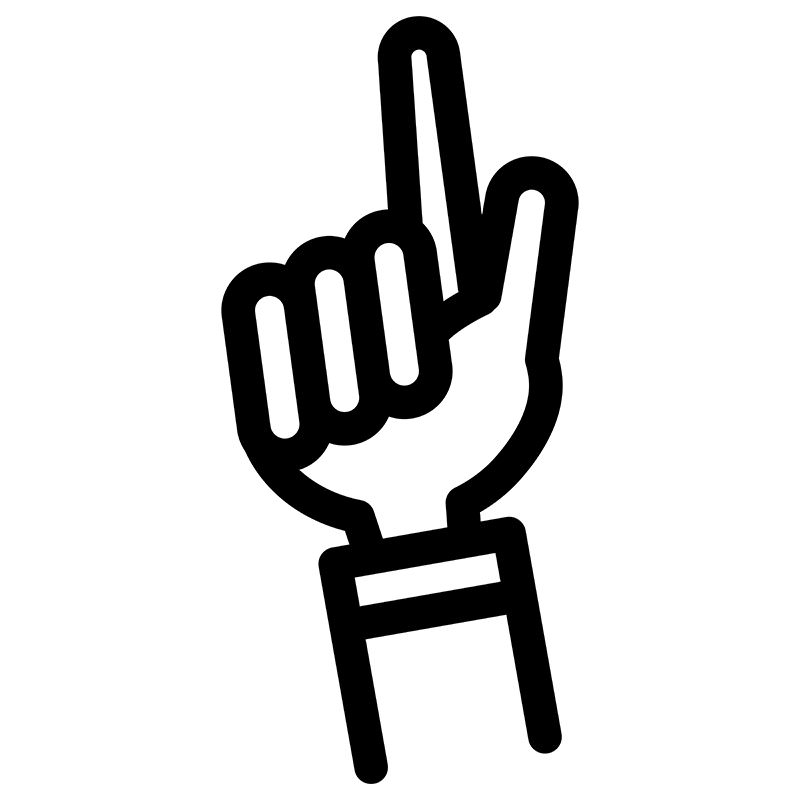
例えば、子供がいない長男にいったん○○を相続させたとします。
本来であれば、この長男が亡くなった場合、その長男の配偶者である妻が相続人となり○○を相続する権利を得ます。
ただし、もしも長男の妻に○○を相続させたくなかったら・・。
このような場合に家族信託を使えば、長男が○○を相続したら次の相続先は次男へといったことが可能です。
遺言ではこのようなことはできません。
こういったことからも、今後は家族信託が相続税対策、及び財産管理の主流になる可能性があります。

家族信託をうまく使えば税金の対策だけではなく、さまざまな相続に対応できる自分たちだけのルール作りができるともいえます。

ただし、信託とはれっきとした法律行為です。
きちんとした手続きをとって、効力のある家族信託を行わなければ、かえって遺されたご家族に混乱を与えてしまいます。
家族信託のご相談は、必ず相続の専門家と行いましょう。
これからの相続対策は家族信託が主役ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
相続税対策には様々なものがあります。
生前贈与などを活用した相続税対策は、聞いたことのある方も多いのではないでしょうか。
ところが大切なご両親やおじいさま、おばあさまが、もし認知症を患ってしまうと、その後にできる相続税対策はかなり限られてしまいます。
たとえご家族であっても、認知症になってしまった方の財産を本人の許可なく勝手にどうこうすることはできません。
ちなみに2025年には高齢者の5人に1人が認知症患者になると言われています。
長寿化が進み、今後は多くの方が相続と認知症という問題に向き合う時代がやってくるでしょう。
そして、今後は家族信託を利用した相続税対策が当たり前の時代になるかもしれません。
家族信託とは簡単に言うと、財産の管理を家族に委託する契約をあらかじめご家族の間で結ぶことです。
たとえば高齢のお父様がご長男との間で「もし自分が認知症になって財産の管理ができなくなったら、長男にその管理を任せる」というようなものです。
そうすることで、いざという時の相続税対策を進めやすくなる、ということになります。
さらに家族信託の内容は、ご家族の事情や考え方に合わせて、かなり柔軟に設計できます。
このことから、どのご家庭でも利用する価値があるものといえます。
ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、ご家族が認知症となった場合、私たちは成年後見制度という公的な制度を利用することもできます。
この制度は家庭裁判所の審判によって選ばれたご家族や専門家などが、認知症になられた方などの代わりに、その財産を管理するものです。
しかしながら、この制度は認知症の方の財産を守るという意味合いの強い制度です。
したがって財産を処分したり贈与したりする行為は、認知症の方の財産を減らす行為として様々な制約を受けます。
それがいかに有効な相続税対策であったとしても、この制度のもとで実行することは難しくなります。
さらに成年後見制度では、その活動内容を家庭裁判所に報告しなくてはなりません。
成年後見制度とは財産管理のための事務を法律上の役割として与えられるわけですから、この点からしても誰でも気軽に申し込めるものではありません。
これに対して家族信託は個人同士の契約です。
内容は家庭の事情に合わせて柔軟に決められます。
家族信託で認知症になった後の財産管理をご家族に任せれば、相続税対策をスムーズに進めることが可能です。
さらに家族信託を使えばご自身が亡くなった後に、その財産を別の人に管理してもらい、特定の人に渡してもらうよう決めることもできます。
たとえば浪費癖のあるお子さんに財産を遺したい場合、財産の管理を委託する相手を別に決めて、お子さんに毎月10万円ずつしか渡さないという内容にすることも可能です。
また、相続財産の行方を決めることもできます。
たとえば財産をお子さんが全て相続して、そのお子さんが亡くなると、その財産はお子さんの配偶者や場合によっては、その配偶者の家系に渡っていくケースがあります。
もし、長男が亡くなった後は長男の奥さんではなく、次男に渡してもらいたいという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
家族信託を使えば、相続した財産を次に誰が相続するかまで決めることも可能です。
つまり家族信託をうまく使えば税金の対策だけでなく、さまざまな相続に対応できる自分たちだけのルール作りができるともいえます。
ただし、信託はれっきとした法律行為です。
きちんとした手続きをとって、効力のある家族信託を行わなければ、かえって遺されたご家族に混乱を与えてしまいます。
家族信託のご相談は必ず専門家に行いましょう。