
名義預金対策には自己信託が有効
委託者と受託者が同一人物である自己信託を使えば、贈与者が孫などの預金を管理しても名義預金にはなりません。さらに信託契約で「受益者には通知しない」と規定しておけば、孫に知らせることなく贈与することも可能です。このように自己信託の契約内容をちょっと工夫すれば、お孫さんに内緒で預金を遺すことも可能です。もし、これが信託なしの贈与であれば、贈与契約となり双方の合意が必要になるため、内緒というわけにはいきません。自己信託は名義預金対策に有効な方法となります。
委託者と受託者が同一人物である自己信託を使えば、贈与者が孫などの預金を管理しても名義預金にはなりません。さらに信託契約で「受益者には通知しない」と規定しておけば、孫に知らせることなく贈与することも可能です。このように自己信託の契約内容をちょっと工夫すれば、お孫さんに内緒で預金を遺すことも可能です。もし、これが信託なしの贈与であれば、贈与契約となり双方の合意が必要になるため、内緒というわけにはいきません。自己信託は名義預金対策に有効な方法となります。
名義預金はよく税務調査で問題になります。
名義預金についての詳しい内容は名義預金の認定を回避するには贈与を受けた本人が口座を管理するに記載しています。
名義預金を簡単に言いますと、贈与された金額を自身(贈与を受けた人)の名義の口座に預金はしているが、その口座の実際の管理は贈与した人がしているでしょ?
これは贈与したと認めないので、この口座は遺産として相続税の対象にします、というのが名義預金と言われるものです。
この名義預金は孫への贈与などでよく問題になります。
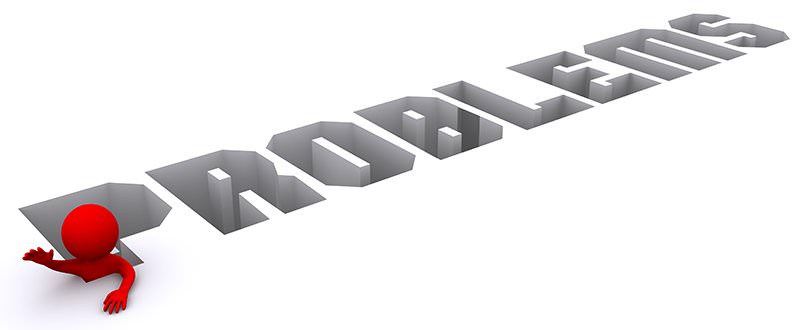
理由としては、おじいちゃんなどが孫の将来のために孫へ贈与はするが、孫自身にそのお金を(無駄使いなどを懸念して)管理させたくないので、お金の管理は自分(おじいちゃんなど)がしていたなどがよくあります。
贈与はしたいが、贈与したお金は自身で管理したい。
一見無理そうですが、実は【自己信託を使えばこれは可能】です。

では、具体的に見ていきましょう。
贈与者をおじいちゃん、受贈者を孫とします。
まず、以下のように委託者・受託者・受益者を設定します。
さらに・・、と言いたいところですが、基本的にはこれだけです。
ちなみに、委託者と受託者が同一人物であることを自己信託といいます。
委託するのもAさん、それを受託するのもAさん。
同じ人物が委託者であり、受託者でもある。
こういうことが出来ます。
委託者・受託者をおじいちゃんにし、受益者を孫にした場合、おじいちゃんが孫名義の管理をしていても名義預金になりません。
さらに言えば、信託契約で受益者には通知しないと規定しておけば、孫に知らせることなく、おじいちゃんが勝手に孫へ贈与し、その贈与金額を管理していても名義預金になりません。
(本来、贈与というのはあげる側・もらう側の双方が納得しないと成り立たないものなのですが、このように勝手に贈与できます。)
なぜこのようなことが可能なのかといいますと、信託を設定した場合、
が別々になります。
たとえ財産の名義が受託者になっていようとも、税務上の実質的な財産の所有者は「受益者」となります。
そして、財産の管理者は受託者になります。
受託者は財産管理のために、財産の名義が受託者になっているだけ、ということなります。
なのでこの場合、委託者(おじいちゃん)から受益者(孫)への贈与があったものとして「贈与税の対象」になります。
受託者(財産の管理者)がおじいちゃんであるので、孫のものになった金銭の管理をおじいちゃんがしても問題にならないのです。
孫への贈与は遺産を減らす相続税対策や二次相続の対策にもなります。
ただ心情として、若い孫への贈与は無駄使いをされるのではないか?
お金を贈与することは教育上いい影響を及ぼさないのではないか?
といったことから、贈与はしたいけれども・・。と思う方はたくさんいらっしゃいます。
自己信託を使えば、無駄遣いさせることもなく贈与でき、さらに相続税対策になります。

名義預金が心配な方は、自己信託での贈与を検討してみましょう。
自己信託に限らず、「信託契約は公正証書にして証拠を残す」のがベターです。
信託契約書も一般の契約書と同様、当事者が署名押印すればそれで成立します。
公正証書にすることは要件ではありません。
ただ、公正証書にすると公証役場で保管され、(税務調査の際などに)対外的な証拠としても使えます。
また、後で自己信託契約で問題や争いが発生しても、公正証書にしておけば証拠が残っているので、紛争などを防ぎやすいというメリットもあります。
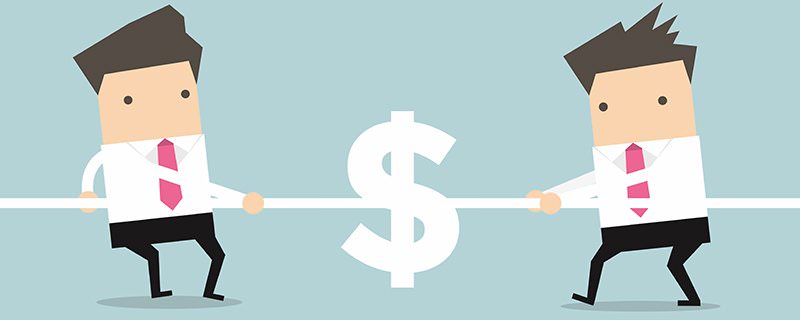
ただし、費用はかかります。
この費用は信託する財産の価格によって変動します。
たとえば1億円の財産であれば、10万円程度の費用がかかります。
ただ、対外的な証拠能力や後のトラブル防止を考えた場合のことも考えると、信託契約は公証役場で公正証書にするのが望ましいと言えます。
名義預金対策には自己信託が有効ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
今回は名義預金対策には自己信託が有効ということについてお話を致します。
生前贈与には一つ注意しておかなければならないことがあります。
それは名義預金です。
たとえば、小さなお孫さんに生前贈与をしたいとき、お孫さんに直接大金を渡すのは心配です。
そのため、おじいちゃん・おばあちゃんにあたられる方がお孫さん名義の預金口座を作って、そこにお金を振り込むという場合が多いと思います。
ところがこれには注意が必要です。
もし、お金を振り込んでいたおじいちゃん・おばあちゃんが亡くなると、税務調査では生前に振り込まれたお金を名義預金だと言って贈与とは認めてくれないことがあるのです。
なぜ贈与と認められないのか、そして、なぜ贈与と認められないと不都合があるのでしょうか。
まず、なぜ贈与と認められないかというと、その口座は確かに名義はお孫さんなのですが、そのお金を実際に管理しているのはお金を振り込んでいるおじいちゃん・おばあちゃんです。
おじいちゃん・おばあちゃんが管理しているお金なのだから、お孫さんに贈与したとはいえないでしょう、という理屈です。
では、なぜ贈与と認められないと不都合があるのかというと、贈与には年間110万円の基礎控除というものがあります。
これによって1年間に贈与を受けた金額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。
ところが贈与と認められなかった場合、この預金はすべて相続財産に足し戻されてしまい、その全額が相続税の対象になってしまいます。
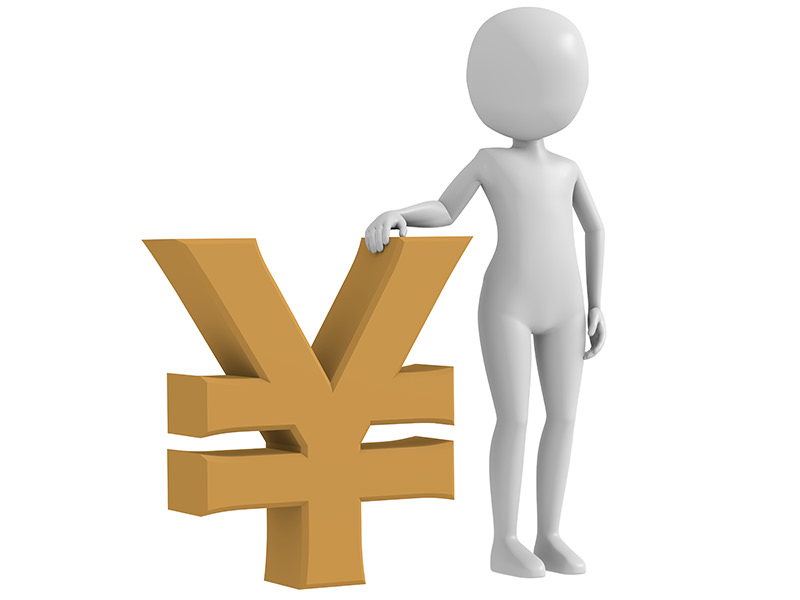
必ずしも税務署がこうした贈与を認めないというわけではありません。
しかし、名義預金は非常に問題になりやすいので始める時は注意が必要です。
では、どのようにすれば贈与が認められるでしょうか?
方法は色々ありますが今回は自己信託を使った方法をご紹介したいと思います。
まず、信託とは委託者・受託者・受益者の3者で行われる契約のことです。
たとえばAさんの財産をBさんに渡したいけれど、Bさんにその財産を管理する能力がない場合、Aさんから信頼できるCさんに財産の管理を委託して、Cさんが管理しながらBさんに使ってもらうというようなことができます。
それでは自己信託とは何かというと、Aさんが自分で自分に委託をしてBさんに財産を贈与する信託です。
委託者と受託者が同一人物ではダメという決まりはありません。
さきほどの贈与であればおじいちゃん、あるいは、おばあちゃんが自己信託を使ってお孫さんを受益者にすればよいということになります。
これなら口座の管理をおじいちゃん、あるいは、おばあちゃんが行いながら贈与を成立させることができます。
また、詳細は割愛しますが自己信託の契約内容をちょっと工夫すれば、お孫さんに内緒で預金を遺すことも可能です。
もし、これが信託なしの贈与であれば、贈与契約といって双方の合意が必要になるため内緒というわけにはいきません。
お話したとおり、自己信託は名義預金対策にとても有効な方法です。
ただし、自己信託を行う場合は契約書を書類でのこしておく必要があります。
あとになって相続で問題とならないよう、契約書の作成は相続の専門家に任せましょう。
そして、相続のことなら税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。
相続のワンストップサービスを提供しております。