
なぜ二次相続はもめるのか?原因を知り今すぐ対策しよう
二次相続は一次相続の時よりも、配偶者の税額軽減の特例が使えないなどの理由により、相続税が多額になる傾向があります。また、遺産分割のまとめ役になりやすい配偶者もいないため、遺産分割がまとまらないなど、相続トラブルにも発展しやすいです。相続対策は二次相続のことまで考えましょう。
二次相続は一次相続の時よりも、配偶者の税額軽減の特例が使えないなどの理由により、相続税が多額になる傾向があります。また、遺産分割のまとめ役になりやすい配偶者もいないため、遺産分割がまとまらないなど、相続トラブルにも発展しやすいです。相続対策は二次相続のことまで考えましょう。
二次相続とは、夫(もしくは妻)の相続により財産を取得した妻(もしくは夫)の相続のことをいいます。
もしも子供がいた場合、子供から見れば2回目の相続ということです。
この2回目の相続のことを二次相続といいます。
この二次相続は一次相続の時よりも
という傾向があります。
理由としては、二次相続では【配偶者の税額軽減の特例が使えない】ためです。
配偶者の税額軽減の特例とは、以下のいずれか多い金額までは相続税がかからない制度です。
配偶者の税額軽減の特例の詳しい内容は、相続税の配偶者控除で1億6千万円か法定相続分まで無税に記載しています。
また、そもそも一次相続で取得した財産の他に、妻(もしくは夫)の【固有の財産も二次相続では対象】となってきます。
そして、一次相続の時は故人の配偶者である妻(もしくは夫)が生存していたため、母親(もしくは父親)が遺産分割協議のまとめ役となり、遺産分割協議がまとまりやすい傾向があります。

しかし、二次相続の時には子供達だけで遺産分割をまとめる必要があり、遺産分割がまとまらないなどの【相続トラブルに発展しやすい】という傾向があります。
そういう点から遺言は一次相続の時よりも、二次相続の方がより重要さを増します。
もしも既に夫(もしくは妻)が死亡しており、次の相続は子供達だけなどの場合は、遺言はしっかり書くようにしましょう。

一次相続の時にはモメることもなく、無事円満に終わったから、うちの子供達は大丈夫。
そう思うかもしれませんが、それは「あなたがいたから」と言えるかもしれません。

もめる確率を低くするには、遺言の付言事項にエピソードを添えましょう。
詳しくは遺言書にはメッセージを残すことも可能!その効果は計り知れないに記載しています。
一次相続の時には、配偶者の税額軽減の特例に目が奪われがちですが、以下のような場合は、特に二次相続対策も考える必要があります。
一次相続では相続税が0円だったけれども、二次相続では多額に・・。

一次・二次の相続税のトータルをシミュレーションし、二次相続のことまで考えて、一次相続の遺産分割を考える必要があります。
シミュレーションの結果、必ずしも配偶者の税額軽減の特例をフル活用し、「一次相続での相続税を0円にすることが得策でない場合」もあります。
もっと極端な例では、一次相続の際に妻(もしくは夫)が「1円も財産を相続しない」ほうが、一次・二次の相続税のトータルでは安くなるということもあります。
二次相続税対策のコツは、「二次相続の時にも同じように特例が使えるかどうか」です。
例えば、配偶者の税額軽減の特例は一次相続の時しか使えません。
それに対して小規模宅地等の特例などは相続単位なので、条件さえ満たせば二次相続でも使えます。
二次相続でも使える特例の対象になる財産は配偶者へ。
シミュレーションをする際には、このことを頭の片隅に入れて計算するといいかもしれません。
ただし、「絶対○○した方がトータルで相続税が安くなる」というものはありません。
なぜなら状況が変わるからです。
二次相続までの間に、
など、シミュレーションした時と「完全に同じ状況ではない」ことがあるからです。
なので、二次相続の時にも同じように特例が使えるどうかは、あくまで目安として考える必要があります。
二次相続の時には、そもそも「特例自体がなくなっている可能性」もあり得ます。
また、相続税のみならず
など、事務的費用も勘案する必要があります。
二次相続対策は、まずシミュレーションしないと始まりません。
相続税対策を考える際には、一次相続はもちろん、二次相続のことまで考えて行いましょう。
二次相続の方が問題は多い、ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
相続対策は二次相続まで考えて行うことが大切です。
二次相続とは、2回目の相続のことです。
たとえば配偶者が亡くなり、その方の旦那さまや奥さまがその遺産を相続することを一次相続とすると、二次相続は、一次相続によって遺産を相続した旦那さまや奥様が亡くなるときの相続をいいます。
実は相続では、この二次相続の方が問題になりやすいといえます。
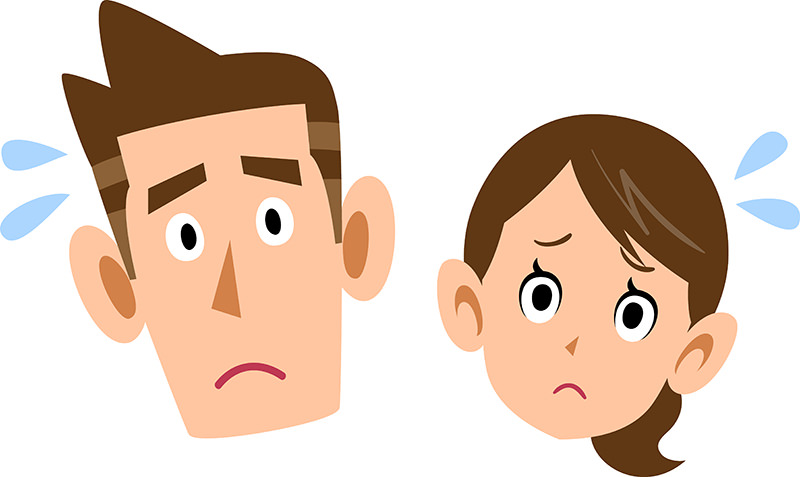
なぜ二次相続の方が問題になりやすいのかというと、1つは二次相続の方が相続税の金額が高くなりやすいからです。
二次相続で相続税の金額が高くなりやすい理由は、基礎控除額の減少です。
基礎控除額とは、相続税の計算をするときに、相続財産の総額から差し引くことができる金額のことですが、この金額は法定相続人が1人減ると600万円減少します。
それから一次相続で配偶者が亡くなった場合、二次相続では相続人の中に配偶者がいないため、配偶者の税額軽減が使えません。
配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続した財産については、最低でも1億6,000万円まで相続税がかからない特例のことです。
また、配偶者の法定相続分が1億6,000万円より高ければ、その金額まで相続税はかかりません。
この特例によって配偶者が多くの財産を相続した場合、ほとんど相続税がかからずにすみます。
ところが二次相続では相続人の中に配偶者はおりませんので、配偶者の税額軽減は使えません。
そのため、お子さんなどが負担する相続税は一次相続より高くなりやすいといえます。
さらに年齢の近いご夫婦の場合、一次相続によって相続した財産をほとんど使わないまま、二次相続が発生することもあります。
この場合、二次相続では後から亡くなった配偶者の個人の財産もプラスされて遺産となりますから、一次相続より相続税が高くなりやすくなります。
二次相続において問題になりやすいのは、税金だけではありません。
一次相続では亡くなった方の旦那さまや奥さまが、お子さんたちの話を聞いて、うまく遺産分割をまとめてくれることがよくあります。
しかし二次相続では、お子さんたちだけで遺産分割をしなければならず、話し合いがまとまらない、という事態に発展しやすいです。
このように二次相続では、一次相続には起こらなかった問題が起こりやすくなります。
それでは、どのような対策を行えばよいかというと、まず税金の対策としては、二次相続まで見越した相続税対策を一次相続のときから考えておくことです。
一次相続で配偶者の税額軽減に頼りすぎると、二次相続で発生する税額が膨らみ、かえって損をすることはよくあります。
また、二次相続でも使える相続税の特例の対象となる資産については、あえて配偶者に相続してもらい、一次・二次相続の2回とも特例を受けるという対策もあります。
まずは二次相続まで見越した、相続税のシミュレーションを専門家と行いましょう。
それから、お子さんたちが二次相続で揉めないようにするには、遺言書の作成が有効です。
遺言書には財産の分け方とは別に、付言事項といって、作成者の思いや感謝の気持ちなどを書き添えることもできます。
付言事項に法的な効力はないのですが、なぜそのような分け方をしたのか、その思いやエピソードを記載すると、お子さんたちが揉めにくい相続となるのではないでしょうか。
二次相続まで考えた相続対策は専門家に相談しましょう。
