
生前贈与とは何?相続との関係は?
生前贈与とは被相続人が亡くなる前(いわゆる相続が発生する前)に、資産を家族や他人に贈与することを指します。これには「相続税の節税対策」や「資産の円滑な移転」といった効果が見込めます。そして、贈与税の基礎控除額(110万円)以下の贈与であれば贈与税はかかりません。
生前贈与とは被相続人が亡くなる前(いわゆる相続が発生する前)に、資産を家族や他人に贈与することを指します。これには「相続税の節税対策」や「資産の円滑な移転」といった効果が見込めます。そして、贈与税の基礎控除額(110万円)以下の贈与であれば贈与税はかかりません。
相続税を節税する方法は大きく分けて二つあります。
一つは財産そのものを減らす方法。
もう一つは税法をうまく適用して、財産評価額を下げる方法です。
そして、生前贈与での節税方法は「財産そのものを減らす方法」となります。
被相続人がご存命中に、財産を贈与して相続財産を減らすという方法です。
ちなみに贈与とは民法549条において「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与えるという意思を表示し、相手方がこれを受諾することにより成立する片務契約をいう」と規定されています。
平たく言えば、贈与とは贈与者(財産をあげる人)が受贈者(財産をもらう人)にタダで財産を与えることをいいます。
贈与税についての詳しい内容は贈与税って誰が払うの?複数人から贈与されたら?契約書は必要?に記載しています。
相続税は贈与税より非課税となる基礎控除が大きく税率も低いです。
ちなみに贈与税は累進課税で最高税率が55%。
最高税率が課税される基礎控除後の課税価格は4,500万円。
相続税の最高税率が課税される6億円超よりも、かなりの低額で贈与税は最高税率が課税されます。
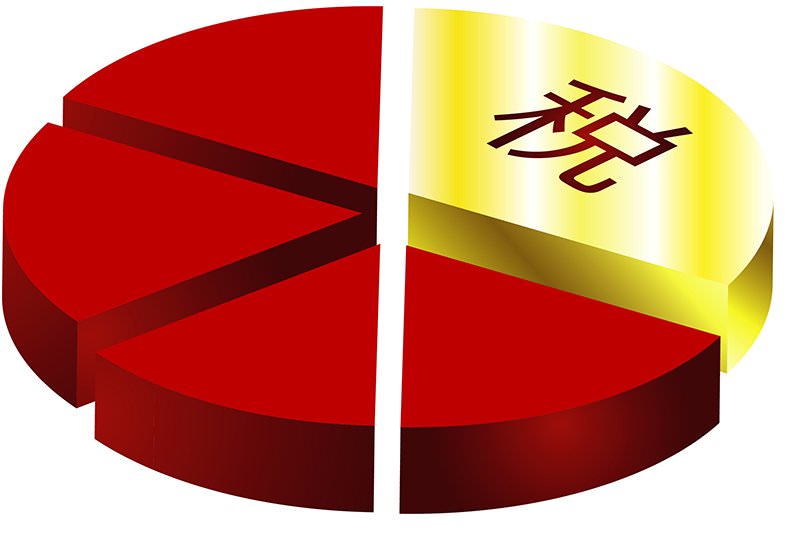
ただ、相続は被相続人ごとに1回しかありません。
いくら税率が低いと言えども、基礎控除も1度しか使えません。
一方、贈与税は相続税よりも税率が高く、基礎控除も110万円と大きいわけではありません。
ただ、110万円の基礎控除が「贈与を受け取る人ごと」に適用され、年があらたまるごとに、その基礎控除をくりかえし利用できます。
10年間贈与すれば1年ごとの基礎控除は110万円でも、10年で合算すれば1,100万円の基礎控除となります。
また、贈与は親族に限らず「誰にでも贈与」できます。
さらに贈与を受ける人が贈与する人の直系卑属(子ども・孫・ひ孫)で20歳以上ならば、一般の贈与税率(一般税率)ではなく、低い税率(特例税率)になります。
| 基礎控除後の金額(注.1) | 一般贈与 | 特例贈与(注.2) | ||
|---|---|---|---|---|
| 税率 | 控除額(万円) | 税率 | 控除額(万円) | |
| 200万円以下 | 10% | ー | 10% | ー |
| 200万円超 300万円以下 | 15% | 10 | 15% | 10 |
| 300万円超 400万円以下 | 20% | 25 | ||
| 400万円超 600万円以下 | 30% | 65 | 20% | 30 |
| 600万円超 1,000万円以下 | 40% | 125 | 30% | 90 |
| 1,000万円超 1,500万円以下 | 45% | 175 | 40% | 190 |
| 1,500万円超 3,000万円以下 | 50% | 250 | 45% | 265 |
| 3,000万円超 4,500万円以下 | 55% | 400 | 50% | 415 |
| 4,500万円超 | 55% | 640 | ||
(注.1)贈与された金額から110万円を控除した金額
(注.2) 20歳以上の者への直系尊属からの贈与
節税対策として生前贈与をおこなうなら、まずは110万円の基礎控除におさまる範囲で毎年贈与していくことが基本となります。
これを暦年贈与といいます。
例えば祖父が孫に年間で現金110万円を10年間贈与し、その後に祖父が亡くなり相続が発生したとします。
この場合、祖父が孫に生前贈与した1,100万円について相続税はかかりません。(厳密には相続開始前3~7年以内の贈与は相続税の対象となってきます。)
1暦年110万円までの贈与については、贈与税は非課税となるためです。
ちなみに以下は年間の贈与税額別の「贈与税の金額」と「その実効税率」となります。
| 贈与金額 (基礎控除前) | 一般 | 特例 | ||
|---|---|---|---|---|
| 税額(端数切捨) (万円) | 実行税率 (%) | 税額(端数切捨) (万円) | 実行税率 (%) | |
| 200万 | 9 | 4.5 | 9 | 4.5 |
| 300万 | 19 | 6.3 | 19 | 6.3 |
| 400万 | 33 | 8.3 | 33 | 8.3 |
| 500万 | 53 | 10.6 | 48 | 9.7 |
| 600万 | 82 | 13.6 | 68 | 11.3 |
| 700万 | 112 | 16.0 | 88 | 12.5 |
| 800万 | 151 | 18.8 | 117 | 14.6 |
| 900万 | 191 | 21.2 | 147 | 17.7 |
| 1,000万 | 231 | 23.1 | 177 | 17.7 |
| 1,500万 | 450 | 30.0 | 366 | 24.4 |
| 2,000万 | 695 | 34.7 | 585 | 29.2 |
| 3,000万 | 1,195 | 39.8 | 1,035 | 34.5 |
| 4,000万 | 1,739 | 43.4 | 1,530 | 38.2 |
| 5,000万 | 2,289 | 45.7 | 2,049 | 40.9 |
相続開始前3年以内の贈与は、相続税の計算上、相続財産に加算して計算します。(既に支払っている贈与税は相続税から控除されます。)
これが2024年以降の相続からは「3年以内 → 7年以内」と変更になりました。詳しい内容は「生前贈与加算とは相続前3~7年以内の贈与を遺産に加算すること」に記載しています。
相続開始前3~7年以内の贈与というのは、いつそうなるのか分かりません。
被相続人の方がいつ亡くなるのか分からないからです。
また、被相続人の方が認知症になったら、生前贈与したくてもできなくなります。
なので贈与は早い段階からコツコツと実行しましょう。
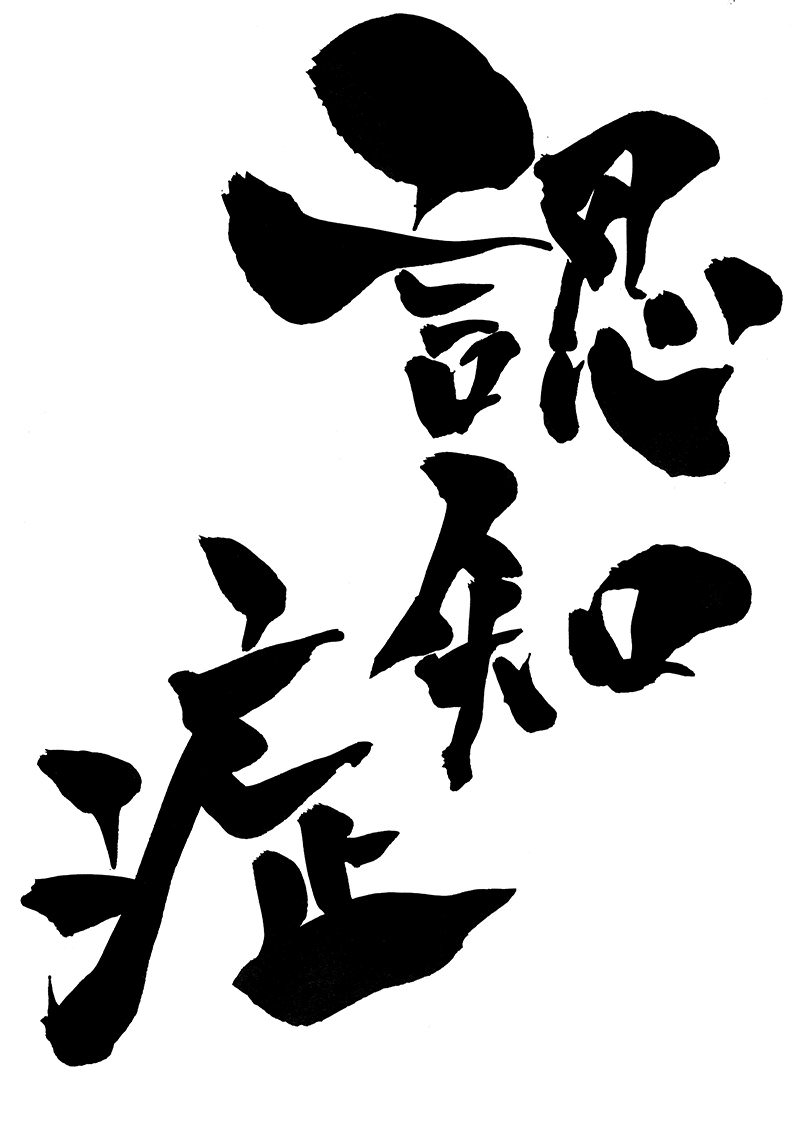
ただし、相続開始前3~7年以内に贈与を受けていても、相続発生時にその被相続人から財産を取得していない人については、贈与された時の贈与税の税金のみで完結します。
例えば同じ生前贈与でも「現金」と「金の延べ棒」では、効果が大きく変わる可能性があります。
現金110万円の贈与の場合、よほどのインフレやデフレにならない限り、その価値は数年・数十年後も110万円のままです。
ところが110万円分の「金の延べ棒」の贈与の場合、数年・数十年後も同じ110万円の価値である可能性は低いといえます。
ちなみに2001年に1kgあたり110万円だった【金】は、2024年7月では1,387万円になっています。
仮の話ですが、相続開始10年前に110万円分の金を生前贈与した。(贈与税の基礎控除額以下なので贈与税は0円)
その金が相続開始時点で約12倍の1,300万円になった。
もしも生前贈与せず金がそのまま相続財産として残ったら、1,300万として相続税の対象となります。
ただ、逆に価値が下がることも十分ありえます。
何を生前贈与するかで迷った場合は
といった視点で考えましょう。