
贈与税の配偶者控除のメリットや注意点
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦間の居住用不動産(もしくは取得するための金額)の贈与であれば、2,000万円まで無税というものです。贈与税の配偶者控除の適用を受けるには色々な要件があり、また、メリットもデメリットもあります。そして相続税対策の観点から見た場合には、贈与税の配偶者控除の適用は慎重に検討する必要があります。
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦間の居住用不動産(もしくは取得するための金額)の贈与であれば、2,000万円まで無税というものです。贈与税の配偶者控除の適用を受けるには色々な要件があり、また、メリットもデメリットもあります。そして相続税対策の観点から見た場合には、贈与税の配偶者控除の適用は慎重に検討する必要があります。
贈与税の配偶者控除とは、結婚生活20年以上の夫婦間(夫→妻または妻→夫)で居住用不動産(=住宅やその敷地)又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与をした場合に、最高2,000万円まで贈与税から控除できる特例です。

つまり、この特例を適用すると2,000万円まで贈与税はかかりません。
また、暦年贈与の基礎控除額110万円を合わせると「2,110万円まで贈与税は非課税」となります。
「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」の特例、いわゆる「おしどり贈与」とも言われています。
なお、贈与税の配偶者控除の特例(おしどり贈与)は、不動産の現物だけでなく、土地・建物の取得費用を贈与する場合にも適用されます。
同じ配偶者からの贈与について、控除が使えるのは「一生に1回のみ」です。
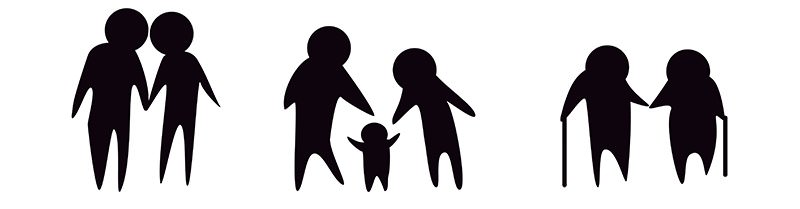
では毎年離婚を繰り返して、その都度配偶者から贈与させれば・・。
そんなに甘くはありません。
この贈与税の配偶者控除の特例(おしどり贈与)を受けるには、適用要件があります。
適用要件
(※居住用不動産は日本国内にあるものに限られ、敷地は借地権の場合も含まれます。居住用家屋の敷地のみの贈与も対象です。店舗兼用住宅は、その居住用部分のみが対象となりますが、居住用部分が概ね90%以上であれば全て居住用とみなされます。)
この適用要件は全て満たす必要があります。
一つでも欠けていたら、配偶者控除の特例(おしどり贈与)の適用は受けられません。
結婚してから20年というのは、贈与の時点で婚姻期間が20年以上(入籍後20年以上で未入籍期間は未カウント)という意味です。
20年目の結婚ではないので注意しましょう。
必ず戸籍で確認して贈与の日を決めましょう。
もしも1日でもズレていたら大変なことに・・。
結婚記念日は入籍日ですか?

また、前の夫で7年、今の夫で13年、通算で20年。
これは配偶者控除の特例(おしどり贈与)は受けられるか?
受けられません。
あくまでも同一の配偶者で婚姻期間が20年以上です。
ところでなぜ、このような制度があるのか?
それは居住用不動産や居住用不動産を購入するための資金は、贈与者一人(夫もしくは妻)だけの力ではなく「配偶者の協力があったからこそ、財産を生み出すことができた」という考え方が根底にあります。
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)は内助の功を評価して、設けられた制度とも言われています。
贈与税の申告の際に、次の書類を添付する必要があります。
※1 居住用不動産の贈与を受けた場合は、固定資産評価証明書などが必要となります。
※2 1の戸籍謄本とは、戸籍原本に記載されている全員分を謄写したものであり、戸籍抄本とは、戸籍原本から記載されている一部の人を謄写したものをいいます。さらに2の戸籍の附票の写しとは、住所の移転履歴を記録した書類のことです。
贈与税の配偶者控除のメリットは、主に以下のようなものです。
生前贈与加算とは「相続開始前3~7年以内の贈与財産」を相続財産に加算するというものです。

これが贈与税の配偶者控除の特例を適用した部分については、生前贈与加算の適用がありません。
なので「直前の相続税対策」としても有効に使えます。
居住用不動産を売却した場合には、譲渡所得{=譲渡収入-(取得費+譲渡費用)}に対して所得税がかかりますが、この譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。
また、仮に夫から妻へ居住用不動産を贈与し、その居住用不動産を夫婦共有の持ち分にした後に売却した場合には、夫と妻合わせて最高6,000万円まで控除可能となります。
こんな場合、配偶者に自宅を相続させたくても、もめたり、うまく相続できないことが発生するかもしれません。
贈与税の配偶者控除を使えば少ない贈与税、もしくは贈与税を無税で自身の生存中に「配偶者に確実」に自宅を贈与することができます。
贈与税の配偶者控除のデメリットは、主に以下のようなものです。
不動産取得税とは、土地や家屋の所有権が移転したときに課される税金です。

相続で不動産を取得した場合には、不動産取得税はかかりません。
ただ、贈与で不動産を取得した場合には、不動産取得税がかかります。
贈与税の配偶者控除は?
残念ながら通常の贈与と同じように不動産取得税がかかってきます。
不動産取得税の税率は4%です。
(ただし、令和9年3月31日までに取得した「土地」や「住宅(家屋)」に対する税率は3%に軽減されます。)
そして不動産取得税は「固定資産税評価額 X 税率」で計算します。
登録免許税とは、不動産などついての登記や登録、その他特許等について課される税金です。

これは相続での取得の場合にもかかってきます。
不動産取得税の時と同じで「固定資産税評価額 X 税率」で計算します。
そして贈与の時と相続の時で税率が変わってきます。
5倍も贈与のほうが高くなっています。
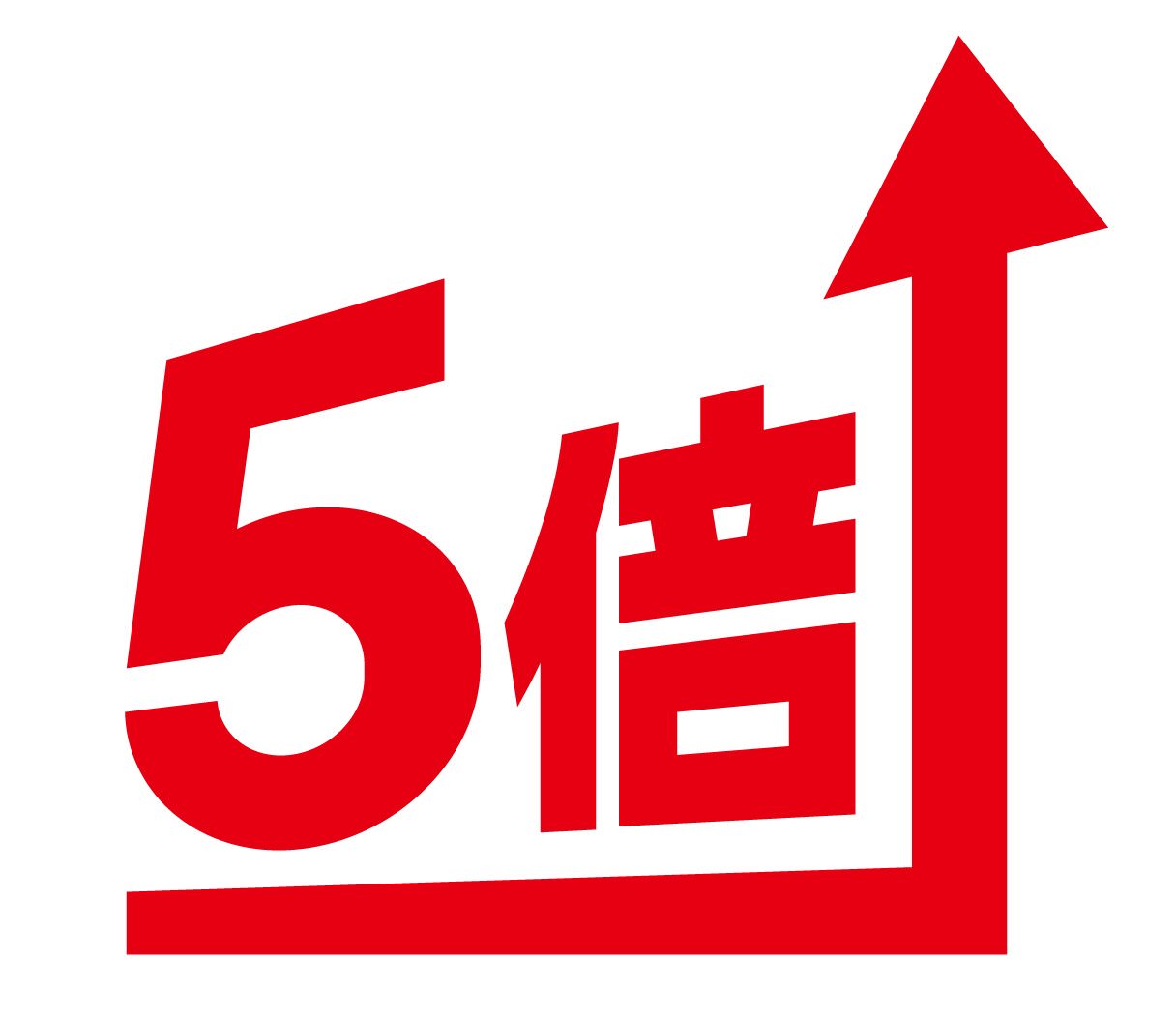
固定資産税評価額が2,000万円の場合、贈与により取得した場合の登録免許税は40万円(2,000万 X 2%)となります。
また、そもそも相続時に「配偶者に税金がかからない」場合も多いです。
詳しくは相続税の配偶者控除で1億6千万円か法定相続分まで無税に記載していますが、配偶者は
1、2のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。
なので、そもそも贈与税の配偶者控除を使わなくても、無税で配偶者に相続させることができる場合が多く「相続で取得した方が登録免許税などの費用も安く済む」ということがあります。
贈与税の配偶者控除は夫から妻へというパターンが一番多いです。
男性と女性の平均寿命からもいっても、夫から妻へ贈与して、夫が先に亡くなるのがある意味自然な流れとも言えます。
ただ、夫から妻へ贈与して、先に妻が亡くなった場合はどうなるでしょうか?
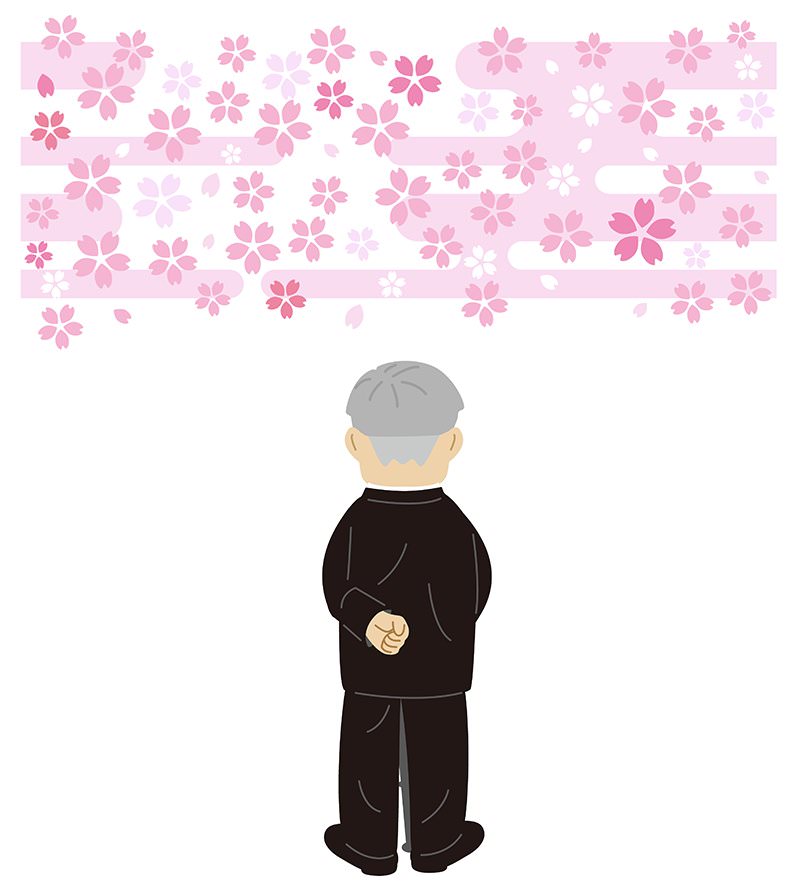
妻へ贈与しているということは、その贈与したものは妻のもの。
その妻のものを妻が亡くなって夫が相続する。
あり得ないことではありません。
そして相続税を支払うことになるかも・・?
配偶者が住宅を相続することが決まっているなら、贈与税の配偶者控除を検討する必要があります。
ただ前提として、贈与税の配偶者控除を「使うか・使わないか」を考える際に重要なことは「配偶者の住居と老後の生活を考える」ことです。
そもそも自宅の名義は配偶者にしたほうがいいのか?
嫁と姑の仲は自身が亡くなった後はどうなるのか?
また、小規模宅地等の特例なども考慮しなくてはいけません。
必ずしも配偶者が住宅を相続することが決まっていても、相続税対策の観点から見た場合、贈与税の配偶者控除を使わないほうがいい場合もあります。
2,000万の非課税枠があり、贈与しないと「もったいない」という考えだけで、贈与税の配偶者控除を使わないほうが賢明です。
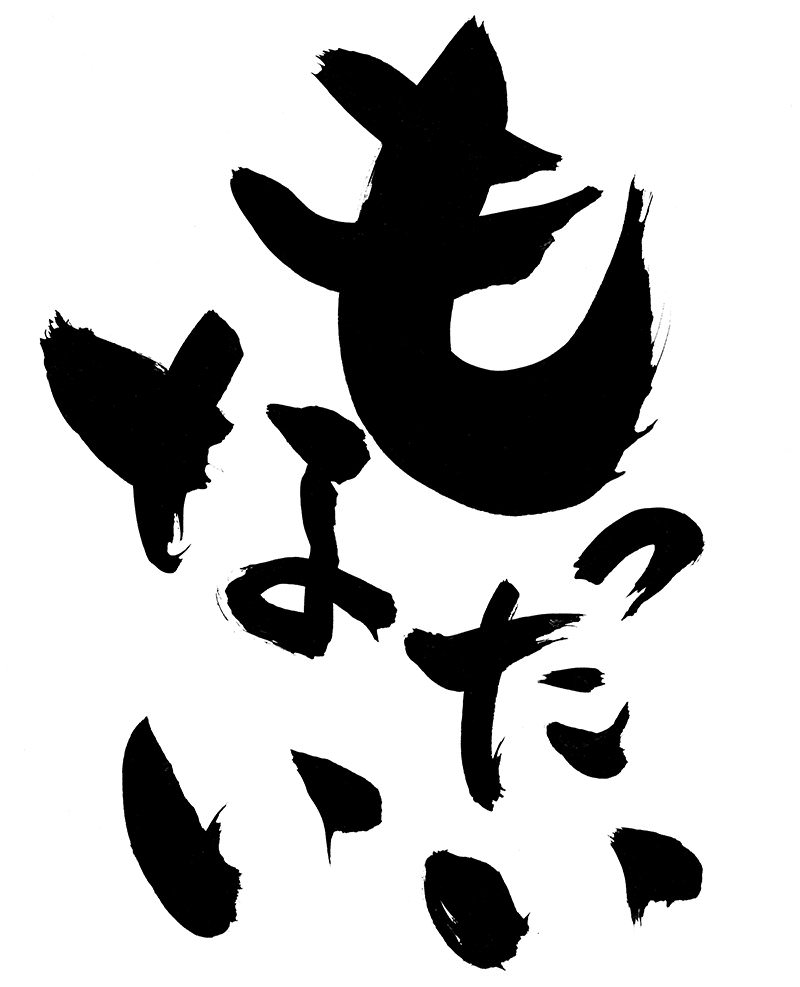
そもそも配偶者が居住用不動産を欲しいと思っていなかったら・・。
賃貸が気軽でいい、という人も少なからずいます。
贈与税の配偶者控除のメリット・デメリットを考える前に、そもそも配偶者が自宅を望んでいるのか?ということも確認しましょう。
贈与税の配偶者控除のメリットや注意点について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。