
相続人の中に認知症がいる場合の相続はどうなるの
被相続人が生前に認知症になったら、家族信託を利用することはできなくなり、成年後見人を付けるしか手はなくなります。そして相続人が認知症になった場合も、それは同様です。老老介護ともいわれる時代。他の相続人が認知症になるリスクは十分にあります。
被相続人が生前に認知症になったら、家族信託を利用することはできなくなり、成年後見人を付けるしか手はなくなります。そして相続人が認知症になった場合も、それは同様です。老老介護ともいわれる時代。他の相続人が認知症になるリスクは十分にあります。
相続人に認知症の方がいる場合、その方が遺産分割協議に合意しても、その遺産分割協議は無効になります。
認知症の方がいる場合は、その方を含めての遺産分割ができない(意味がない)ということです。
では、認知症の方を除いて遺産分割ができる(有効になる)のかというと、それもできません。
認知症の方の相続人を除いて、遺産分割をしても無効になります。

認知症の相続人がいる場合には法定相続人以外の方を代理人にして、遺産分割協議をしなくてはなりません。
例えば法定相続人である母親を介護している(法定相続人である)長女の方が母親の代理として、遺産分割協議をすることはできません。
母親・長女共に相続人であり利益相反の関係にあるからです。
遺産分割協議を成立させるには相続人全員の合意が必要です。
しかし相続人が認知症の場合、意思能力の欠如から合意をすることができません。
また、合意したとしても無効になります。
この場合には被相続人が認知症になったら成年後見制度を利用するのと同じで、相続人が認知症になった場合も成年後見人を付けることになります。
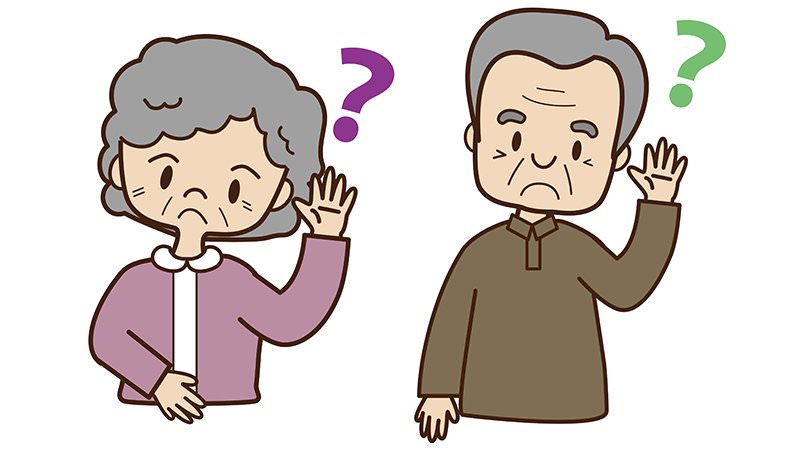
成年後見人となった方が、その相続人の代理人として遺産分割協議に参加します。
流れとしては、その成年後見人の方に、他の相続人が遺産分割を申し入れ遺産分割協議をします。
被相続人が生前に認知症になると、相続税対策ができなくなります。
また、ご自身で財産の処分や管理もできなくなります。
今後、相続税対策や財産管理の認知症対策として、家族信託が主流になってくる可能性があります。
そして、この家族信託は被相続人に限らず、相続人にも使えます。
相続人が認知症になった場合も、被相続人が認知症になった時と同様、以下のようなことができなくなります。
そして、相続税対策は二次相続も考えないといけません。
相続人が認知症になった場合も、一次相続のみならず二次相続対策に大きな支障がでたり、できなくなったりします。
老老介護ともいわれる時代。
他の相続人が認知症になることも想定しておく必要があります。
相続人の中に認知症の方がいる場合の相続について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
今回は相続人の中に認知症がいる場合の相続はどうなるのか?ということについて、お話を致します。
これからの相続税対策で大きな問題となるのは、認知症の対策をどうするかということです。
認知症になってしまうと、その方は自分の財産を処分したり、贈与したりすることができなくなります。
そのため認知症になってしまった後では、相続税対策をすることが非常に難しくなります。
そして認知症が問題となるのは、遺族も同じことです。
もし相続人の中に認知症になった方がいる場合、その方を交えて遺産分割協議をというわけにはいきません。
判断能力がない方が行った行為は、後から無効とされてしまうことがあるからです。
いくらその場で遺産分割協議書にサインをしてくれたとしても意味がありません。
中には「認知症になってしまった人を除いて遺産分割をすればいい」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、遺産分割は相続人全員の同意が必要です。
そのため、その人だけ外して話をすすめることはできないのです。
もし認知症になってしまった方が相続人の中にいらっしゃる場合は、すぐに成年後見人を付けることが必要となります。
成年後見人をつけるには、家庭裁判所への申し立てが必要になります。
成年後見人が無事に決定すれば、その人が遺産分割協議に代理で参加することができます。
また認知症になって困るのは、遺産分割だけではありません。
介護の手続きやその方自身の相続税対策など多方面に悪影響を及ぼします。
この認知症の問題を未然に防ぐには、家族信託が有効となります。
ただ、家族信託は認知症になる前にしかできません。
そして、家族信託は柔軟に設計ができるがゆえ、専門家の能力しだいで家族信託の内容が大きく違ってくることもございます。
よって家族信託を検討される際には、信頼できる相続の専門家に相談しましょう。