
認知症か微妙な時に作成した遺言書は有効?
被相続人が遺言書を書いていた時、認知症かどうか微妙であった。もしくは遺言書を書いてから、直ぐに認知症と診断された。このような場合、遺言書を書いていた時に被相続人に意思能力があったかどうかが論点になります。
被相続人が遺言書を書いていた時、認知症かどうか微妙であった。もしくは遺言書を書いてから、直ぐに認知症と診断された。このような場合、遺言書を書いていた時に被相続人に意思能力があったかどうかが論点になります。
被相続人が認知症の状態で亡くなった。
しばらくして、遺言書が発見された。
相続人の誰もが遺言書があるとは思っていなかった。
遺言書通りに遺産分割を進めようとしていた際、ある相続人Aが「待った」をかけてきた。
その遺言、法的に有効なの?相続人Aは言った。
法的に有効?
こうして実際に遺言書があるし、中身も正しく書かれていて遺言の形式に問題はない。
相続人Aは言った。
そいうことじゃない。
その遺言書は認知症になる前に書いたのか?
それとも認知症になってから書いたのか?
それが問題だ。
認知症だった人が亡くなった時、遺言書を
という問題があります。
また、「認知症になる前の遺言」と「認知症になった後の遺言」の内容が微妙に違う、というようなこともあります。
さらには、認知症か微妙な時に作成した遺言書があり、遺言書が作成された直後に、認知症として診断された場合はどうなるのか?という問題もあります。
遺言の形式に不備があり遺言書が無効になるのとは別に、遺言書そのものの効力が問われるケースも少なくありません。
遺言書の効力を発揮するためには、被相続人が遺言をする際に、意思能力(遺言能力)があったことが大前提として必要です。
逆に言えば、意思能力(遺言能力)が無い状態で、むりやり遺言書を作成させたとしても、その遺言書は無効となります。
そして、この意思能力(遺言能力)は以下の点で判定されます。
これらを検討して、遺言が有効か無効かを判断します。
そして遺言の内容に疑いを感じ、納得できずに無効を主張したい場合には、遺言無効確認訴訟で解決を図ることになります。
などを元に判断されます。
認知症になったら絶対にもう遺言書は書けないのか?
遺言書が効力を発揮するための大前提として、遺言書を書いた際の被相続人の意思能力(遺言能力)が必要と記載しました。
そうです。
認知症の方でも遺言書を書く際に、意思能力(遺言能力)があれば、法定に有効な遺言書を書くことが出来ます。
これは成年後見人等が選任されていても同じです。
ただし、条件があります。
それは医師2名以上の立ち会いが必要です。
認知症の方でも一時的に意思能力が回復し、医師2名以上の立ち会いのもと遺言を残せば、その遺言は有効となります。

ちなみに立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において、意思能力を欠いていない状態であった旨を遺言書に付記・署名・押印する必要があります。
なお、公証人が病院に行って公正証書を作成したとしても、遺言者に正常な判断能力がなければ、その遺言書は無効となります。
また、通常の行為能力より低い程度の意思能力(遺言能力)でも、満15歳以上の者は未成年者や被保佐人でも、法律的に有効な遺言書の作成は可能です。
認知症でも遺言書は書ける?ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
さて、みなさんの周りに認知症の方いらっしゃるでしょうか?
近い将来、日本のお年寄りの5人に1人が認知症になるだろうと言われています。
さて、遺言書を書いた時に認知症かな?それとも違うかな?と決められない場合、その遺言書は有効でしょうか?
また、遺言書を書いてからすぐに認知症ですとお医者さんから診断された場合、その遺言書は有効でしょうか?
今回は認知症と遺言書についてお伝えを致します。
こんな場合を考えてみてください。
お父さんが認知症になったまま亡くなりました。
しばらくして、お父さんの遺言書が見つかりました。
お父さんが遺言書を作っていたなんて、家族の誰も知りませんでした。
でも、確かにお父さんの遺言です。
そこで遺言書に書かれた通りに、遺産を分けようとしました。
すると長男が、この遺言は本当に法律的に大丈夫なのか?と言いました。
次男は、これは間違いなくお父さんが作った遺言だと言います。
でも、長男はさらに考えてしまいました。
この遺言書は、お父さんが認知症になる前に書いたのか?
それとも認知症になってから書いたのか?
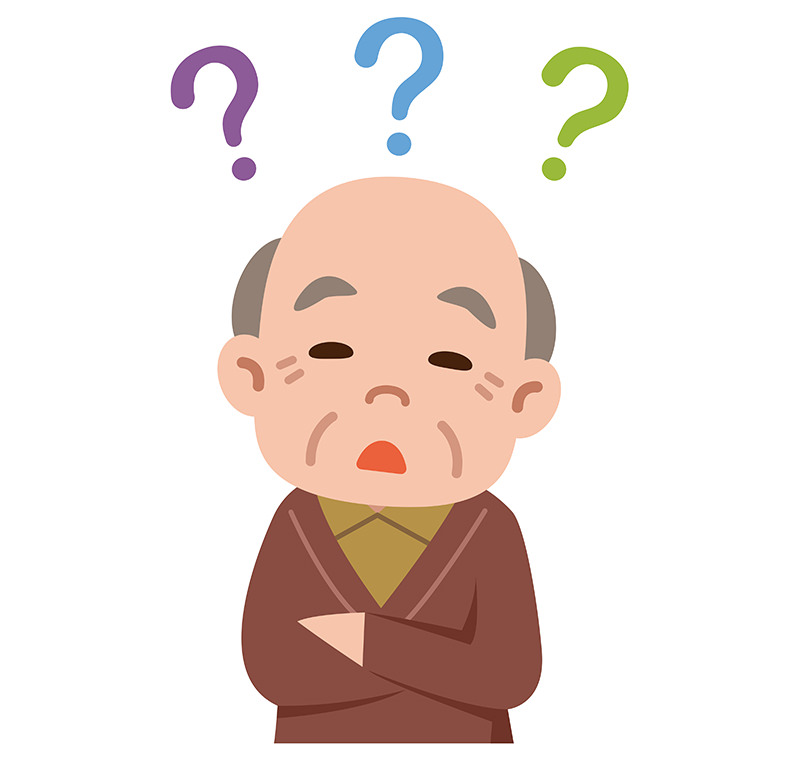
このように認知症だった人が亡くなって、遺言書が見つかった時には、その遺言書をいつ書いたのかが大きなポイントになります。
つまり遺言書を書いたのが認知症になる前だったのか、それとも認知症になってからだったのかによって遺言書が有効か無効かが決まるからです。
先ほどの例でいくと、遺言書の日付などから、お父さんが認知症になる前に書いたとはっきりわかれば、その遺言書は有効です。
ところで遺言書が有効かどうかは何で決まると思いますか?
もちろん、きちんとした手続きや形式も大切です。
けれども最も大切なことは、遺言をする人の意思です。
具体的には遺言を作る時に財産の分け方を指示するなど、自分で考えや思いを持っていたかどうかという点です。
このように遺言する内容について、自分の考えや思いがあることを「意思能力」または「遺言能力」があったといいます。
遺言を作る時に、はっきりとした「意思能力」を持っていたら、その遺言書は有効です。
逆に認知症が進んで「意思能力」がない状態で、無理やり書かされた遺言書は無効です。
意思能力は
この4つを検討して、意思能力があったかどうかを判定します。
そして、この判定に従って遺言書が有効か無効かを判断します。
もし遺言の内容が「おかしいな」とか、「これは納得できない」と思う場合には「遺言無効確認訴訟」を起こして、遺言書が無効かどうか解決します。
遺言無効確認訴訟では、
自分で作った自筆証書遺言の時には「筆跡が本物か」などを元に判断をします。
それでは認知症になってしまったら、もう絶対に遺言書は書けないのでしょうか?
さきほど遺言を作るときに、はっきりとした「意思能力」があれば、その遺言書は有効です、とお伝え致しました。
そうです。認知症の方でも遺言書を書く時に「意思能力」があれば、その遺言書は有効なのです。
ただし条件があります。
それはお医者さん2人以上の立ち合いが必要です。
それは認知症の人でも「遺言書を書く時には意思能力がありました」という確認をしてもらうためです。
ですから認知症の方でも、一時的に意思能力が回復した時にお医者さん2人以上に立ち会ってもらって遺言を残せば、その遺言は有効になります。
立ち会ったお医者さんは認知症の人が遺言をした時には、意思能力がありました、という内容を遺言書に書き加えて署名をして印鑑を押します。
身内の人が少しだけ認知症のようになった、どうやって遺言書を書いてもらおうか?と困った時は、ぜひ専門家に相談してください。
そして遺言書の作成や相続税対策、相続税の申告や相続手続きのことなら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。
相続のワンストップサービスを提供しております。