
遺書と遺言書は別物!法的に有効な遺言書の作成方法は?
遺書と遺言書は別物です。また、遺言書には押印が必要といったように、作成にルールがあります。そして、どんなに「立派な遺言書」でも、一つでもルールに反していたら、その遺言書は無効です。逆に、どんなに「みすぼらしい遺言書」でも、ルールを全て守っていたら、その遺言書は有効となります。
遺書と遺言書は別物です。また、遺言書には押印が必要といったように、作成にルールがあります。そして、どんなに「立派な遺言書」でも、一つでもルールに反していたら、その遺言書は無効です。逆に、どんなに「みすぼらしい遺言書」でも、ルールを全て守っていたら、その遺言書は有効となります。
勘違いされている方も多いのですが、遺書と遺言書は別物です。
遺言書は
など遺産分割に関して記載するものです。
そして、一定の要件を満たさなければ、遺言書は法的な効力を持ちません。
それに対して遺書は、そもそも遺産分割などに法的効力があるものではなく、故人の思いや考え、最後に伝えたいことなどを記載するものです。
ちなみに遺言書の付言事項という形で、法的に効力はありませんが、故人の思いや考え方、最後に伝えておきたいことなどを記載することもできます。
遺書や遺訓は法律上、遺言として効力が生じません。
遺言書がない場合、遺産分割は相続人同士で決めることになります。
遺言書がないと「相続人間で揉める原因」にもなります。
遺産の分割に関しては、遺言書に記載しましょう。
遺言書を書く際には、ただ書けばいいというものではありません。
注意しないと、せっかく書いた遺言書が無効になることもあります。
生前に被相続人が相続税対策などを考慮して、遺言書の内容を決めたとしても無効になってしまったら、遺産分割は相続人間で決めることになります。
なので相続税対策などを無意味にしないためにも、遺言書のルールに沿って正しく書きましょう。
遺言書を書くルールは主に以下のようになります。
まずは自筆(公正証書遺言・秘密証書遺言は除く)です。
遺言書の全文と日付、氏名はすべて自筆する必要があります。
なのでパソコンやワープロなどで入力し、印刷したものは遺言書として無効になります。
また
などで作成した遺言も無効となります。
現時点においては、「遺言書は文書(*注1)」でしか認められていません。
(*注1)
平成31年1月13日からは、財産目録はパソコンでの作成が可能になります。
(詳しくは、平成31年1月13日から自筆証書遺言の作成要件が緩和に記載)
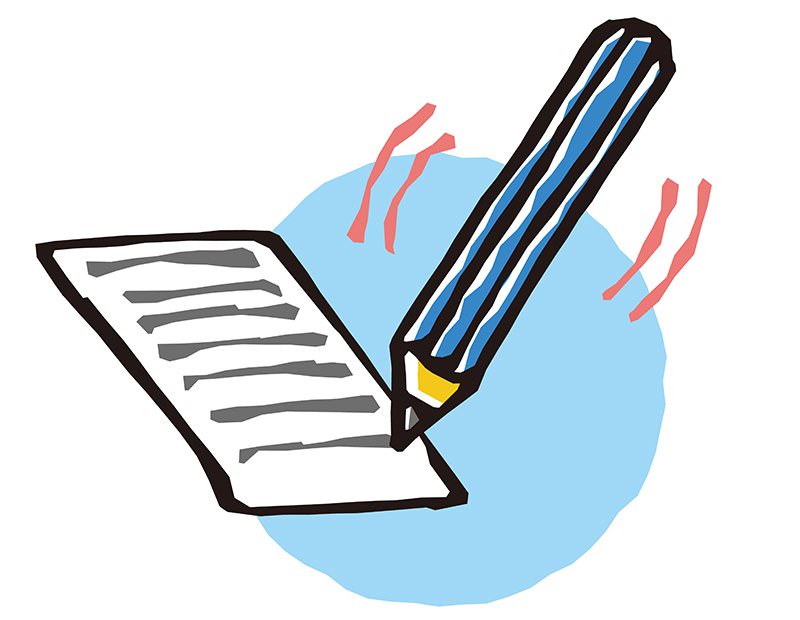
そして押印も必要です。
実印である必要はありませんが、実際は実印(印鑑証明と同じもの)を使用する場合が多いです。
最大の注意点は「日付の記載」です。
日付の記載がない遺言書(秘密証書遺言は除く)は、法的に効力がありません。
要は無効になるということです。
この日付は西暦・和暦どちらで記載しても有効ですが「●年●月●日と記載する必要」があります。
遺言書の原則は、自筆(公正証書遺言・秘密証書遺言は除く)・署名・押印・日付(秘密証書遺言は除く)の記載です。
ただ、この原則を守っていれば「どんな遺言書でも有効になるのか」というと、そういう訳ではありません。
以下のような遺言書は無効となります。
遺言書に記載している氏名が「ペンネームや屋号の場合は無効」となります。
(ただし、通称やペンネームを用いた遺言でも、遺言者の特定ができれば有効とする説もあります。)
また、夫婦などの「連名の遺言書も無効」となります。
遺言書は、被相続人1人につき1通が原則です。

氏名がペンネームだったり連名の場合、遺言書は無効になります。
このように遺言書はルールを守らないと無効になりますが、逆に言えばルールさえ守っていれば遺言書は有効となります。
以下のような遺言書は、一見無効とも思えますが有効です。
遺言書というと、何か格式ばった感じで記載しないといけないのかと思いますが、ルールさえ外していなければ問題ありません。
表紙はあってもなくても、その文書が「遺言書であると分かれば有効」となります。
また、書体も一切関係ありません。
普通は毛筆・ボールペン・万年筆などで遺言書は記載しますが、「鉛筆でも可能(有効)」です。
書くための媒体の決まり(ルール)がないからです。
そして、遺言書の紙にも決まりはありません。
なので
などに記載しても有効です。
さらに言いますと、紙でなく字を書くことができるものであれば全てOKです。
そして、英語などの外国語で記載したものでも有効です。
チリ紙に鉛筆でポルトガル語で書いてある遺言書も、ルール(日付を書くなどの)を外していなければ有効です。

ただ現実的に遺言書はある程度長持ちし、書き換えや消されたりできない必要があります。
また表紙がなかったり英語で記載されていたりしたら、遺言書を発見した人が遺言書でないと思って処分する可能性もあります。
遺言書はしっかりした形で残しましょう。
遺言書が乱筆で読みづらく、解読ができない場合はどうなるのか?
その場合は鑑定人が解読する場合があります。
というのも草書体で書かれていて、読めないだけの可能性もあります。
単なる乱筆ではなく、書体が違い読めない場合には読める人がいます。
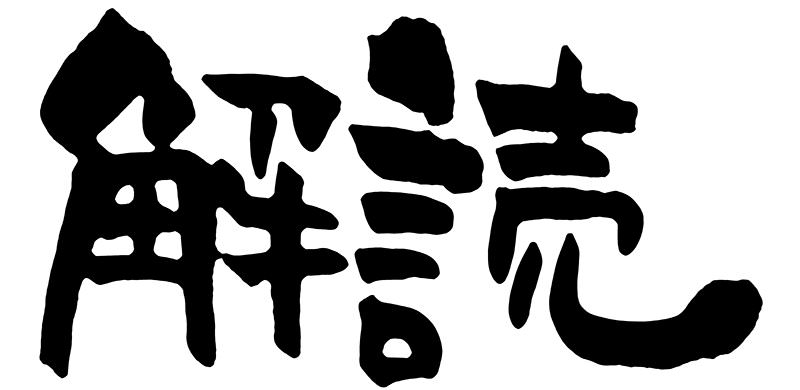
ただし、本当に単なる乱筆で誰にも読めない場合(解読不能な場合)は、その遺言書は無効となります。
遺言書と遺書は別物?遺言書の作成方法について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。