
遺言書が複数あったり、遺産分割協議成立後に発見された場合は?
前の日付の遺言書で撤回されるのは、内容が衝突する部分だけで、前の遺言書全体が撤回されるわけではありません。また、遺産分割協議成立後に遺言書が出てきた場合は、原則、その遺産分割は無効となります。
前の日付の遺言書で撤回されるのは、内容が衝突する部分だけで、前の遺言書全体が撤回されるわけではありません。また、遺産分割協議成立後に遺言書が出てきた場合は、原則、その遺産分割は無効となります。
遺言書は何度でも書き直しが可能です。
そして、遺言書が複数ある場合は「後の日付のものが有効」となります。
ただ、後の遺言書のみが有効となるわけではありません。
それぞれの遺言書はあくまでも有効ですが、その内容が衝突する場合には、その衝突している部分の内容は後の遺言書が有効となります。
前の遺言書で撤回されるのは内容が衝突する部分だけで、遺言書全体が撤回されるわけではありません。
そして
と遺言書には種類がありますが、遺言書に優越はありません。
自筆証書遺言より公正証書遺言のほうを優先する、というような決まりはありません。
また、公正証書遺言だから撤回できない、ということもありません。
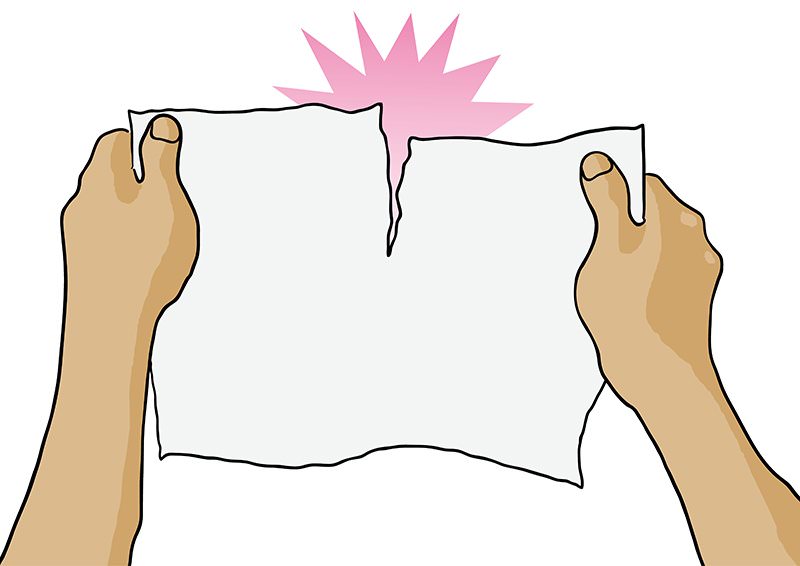
後の日付の遺言書が必ず優先されます。
ちなみにエンディングノートには、遺言書のような法的な効力はありませんので、このような有効や撤回などは関係ありません。
遺産分割協議成立後に遺言書が出てきた場合、原則、その「遺産分割は無効」となります。

なので、遺産分割をやり直す必要がでてきます。
また遺言書を隠匿していて、後からそれがバレた場合には、隠匿した者は相続欠格となり相続権がなくなります。
ただし、その欠格者に子供がいる場合、その子が代襲相続人になります。
相続人に変化が生じますので、結局遺産分割は無効となります。
また、相続回復請求権(相続権の侵害に対し財産請求や相続人たる地位の回復を要求する権利)によって、遺言の内容(相続権)の実行を求めることができます。
協議が成立しない場合は、遺言書の内容(実現)を訴訟で請求します。
ただ、相続権を侵害された事実を知ってから5年間、相続回復請求権を行使しない時には時効によって消滅します。
また、相続開始の時から20年を経過した場合には、無条件で(知らなくても)権利は消滅します。
相続税対策をしっかりする、後に相続トラブルを起こさないためにも、遺言書の存在の確認はしっかり行いましょう。
遺言書が複数あったり遺産分割協議成立後に発見された場合について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野敬佑が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。