
遺贈とは遺言で「財産を特定の人」に相続させること
遺贈により財産を与える者を遺贈者といい、財産を受ける者を受遺者といいます。そして、遺贈には特定遺贈と包括遺贈の2種類あります。
遺贈により財産を与える者を遺贈者といい、財産を受ける者を受遺者といいます。そして、遺贈には特定遺贈と包括遺贈の2種類あります。
遺贈とは「遺言による相続財産の移転」を言います。
簡単に言えば、遺言で相続する・相続させることを言います。
「遺贈は財産を譲る人が単独で決める行為」であり、死因贈与とはそこが大きく異なります。(死因贈与の場合は、両方の同意が必要)
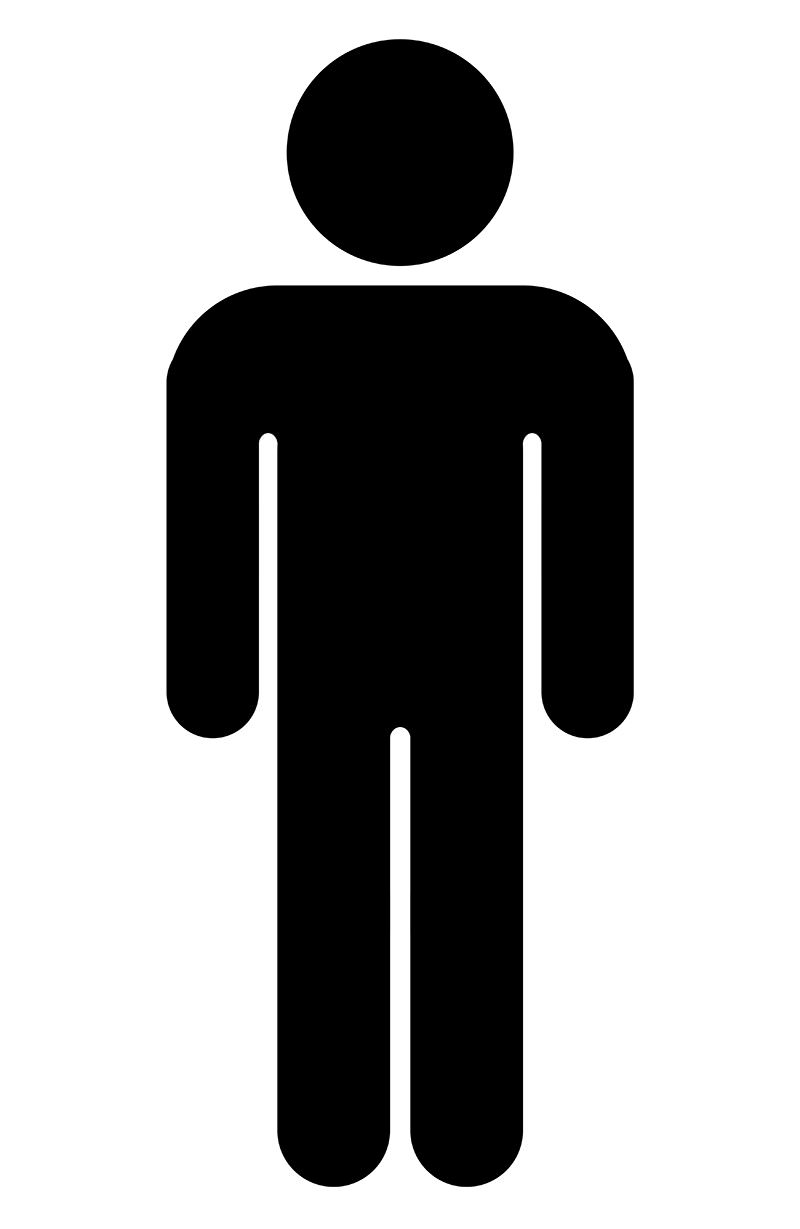
遺贈により、財産を与える者(いわゆる亡くなった方)を遺贈者といい、財産を受ける者を受遺者といいます。
こうした遺贈では、遺言書で財産を移転させることから「相続人以外の第三者」に財産を贈ることもできます。(ちなみに受遺者は、遺贈について承認も放棄もできます。)
遺贈は贈与税ではなく「相続税の対象」となります。
通常の相続と同様に、赤の他人や兄弟等が受遺者の場合、相続税額は2割加算となります。
遺贈をする場合はどういう場合か?
このような場合には遺贈が必要です。
もちろん法定相続人に遺贈することも可能です。
胎児や法人への遺贈も可能です。
この遺贈には以下の2つの種類があります。
特定遺贈とは「特定の具体的な財産」を遺贈することです。
例えば自宅の土地と○○銀行の預金はA、建物はBに与える、というような具合です。
債務についての指定がない限り「負担する義務がない」というメリットがあります。
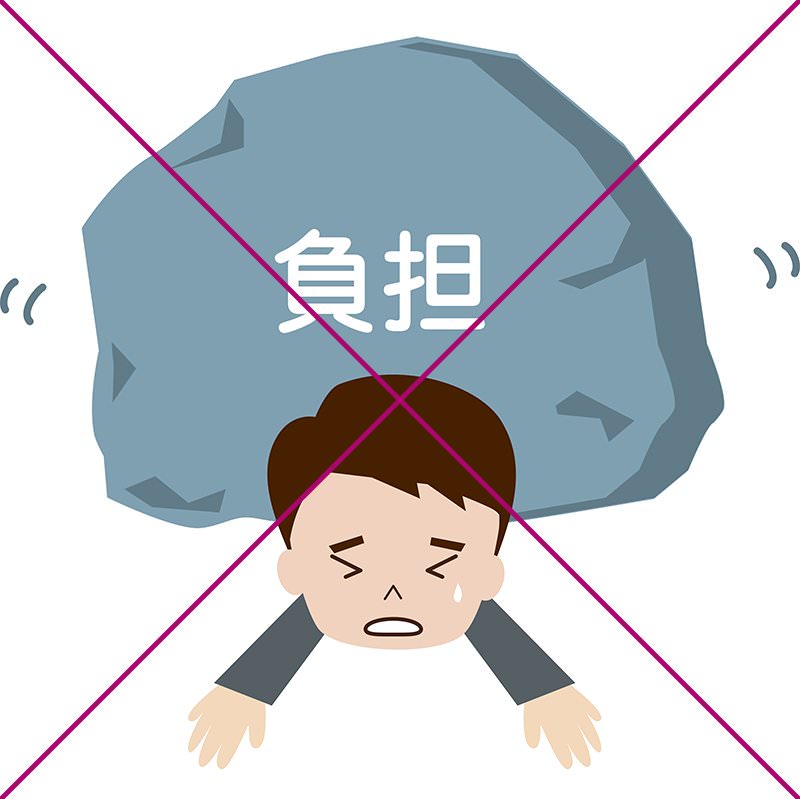
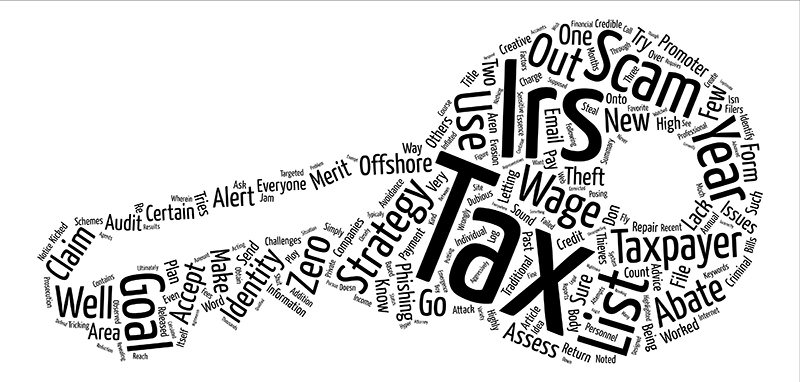
などのデメリットがあります。
包括遺贈とは「遺産の全部、又は一定の割合」を示して、遺贈することを言います。
遺産総額の5分の1をA、5分の2をBに与える、というような具合です。
そして、包括遺贈で財産を受ける者を包括受遺者といいます。
民法において、包括受遺者は相続人と「同一の権利義務を有する」とされています。
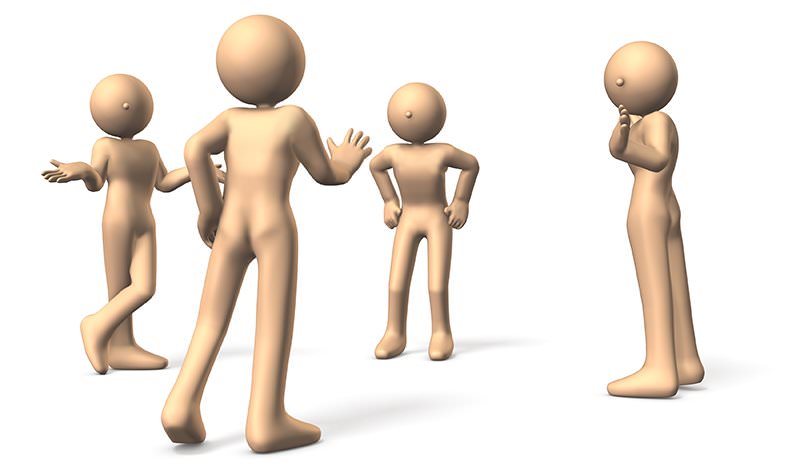

場合にもよりますが、特定遺贈の方をどちらかと言うとお勧めします。
包括遺贈の場合、指定の配分割合になるように相続人で分割協議をしないといけません。
そして、指定の配分割合で綺麗に分割するのは、実務上、煩雑で難しいということもあります。
遺贈の条件として、会社の事業を継ぐことなどと指定することが可能です。
負担付遺贈であれば、親の面倒や子供達の面倒をみることや、借金を引き継ぐこと、などと指定します。
ただし、債務の弁済のみを目的とする場合や、義務の負担のみの場合には無効となります。
例えば、Aに金1,000万円をあげるので、Bへの借金1,000万円を支払いしてください、というような遺贈は無効となります。
遺贈について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。
動画内容
遺贈とは、亡くなった人が生前に作成した遺言書によって、財産を特定の人に相続させることです。
特定の人に財産を遺したい、という思いを実現する際に有効な手段となります。
相続人でない人に財産を遺すことも可能ですし、まだ生まれていない胎児や法人を指定することもできます。
遺言書で指定できるのは、誰が相続するかだけではありません。
どの財産を相続させるか、これを指定することもできますし、具体的な財産を決めずに、全体の何割の財産を相続させるといった指定でも可能となります。

そしてどの財産を相続させるか、これを指定する遺言を「特定遺贈」といいます。
特定遺贈のメリットは、プラスの財産だけを相続することができる、ということです。
亡くなった人に借金がある場合、相続人はそのマイナスの財産も相続しなくてはなりません。
しかし特定遺贈では、指定された財産を相続するものなので、マイナスの財産について特に何も書かれてない場合は、プラスの財産だけを相続することができます。
一方で特定遺贈にはデメリットもあります。
まず不動産の特定遺贈を受けた場合、不動産取得税がかかってしまう、ということです。
不動産取得税とは、土地や建物を取得した人が都道府県に支払う税金です。
その税額は固定資産税評価額の3%になります。
不動産取得税は相続によって不動産を取得すると、かからない税金ですので注意が必要となります。
また、亡くなられた方の配偶者やお子さん、親には「遺留分」といって、一定の財産を相続する権利があります。
その権利を侵害する遺言書を作成すると、遺された人たちが揉めてしまいます。
遺言書を作成する時は遺留分を計算し、それを侵害しないよう作成しましょう。
続いて、財産を割合で指定する「包括遺贈」について説明をします。
包括遺贈とは、5分の1をAさんに与える、5分の2をBさんに与える、というような財産の分け方です。
包括遺贈で財産を受けた人は、相続人と同じ権利義務をもちます。
遺産分割協議に参加することもできますし、不動産を相続しても不動産取得税は、通常の相続と同じでかかりません。
ただし相続人の義務も負うため、亡くなった方の借金も相続しなければならなくなる点で注意が必要です。
遺言書は特定の人に財産を遺したい、という気持ちを実現することができます。
必要であれば遺贈に条件をつけることも可能です。
しかしながら、その書き方ひとつでマイナスの財産に対する義務が変わってきます。
遺言書の作成は必ず専門家に相談しましょう。