
遺留分侵害額請求とは?時効や手続き方法を解説
遺留分を侵害されている相続財産でも、自動的に相続することは出来ません。遺留分侵害額請求をする必要があります。そして、遺留分侵害額請求には時効があります。ただ、「遺留分を侵害されたときは裁判しか方法がない」というわけではありません。まずは話し合いで解決することが一般的です。
遺留分を侵害されている相続財産でも、自動的に相続することは出来ません。遺留分侵害額請求をする必要があります。そして、遺留分侵害額請求には時効があります。ただ、「遺留分を侵害されたときは裁判しか方法がない」というわけではありません。まずは話し合いで解決することが一般的です。
被相続人の遺言の内容が、愛人に全ての財産を相続させるなど、あきらかに他の相続人の遺留分を侵害している。(遺留分の詳しい内容は、遺留分とは?その計算方法や割合、兄弟との関係はにて記載)
遺留分を侵害している遺言だから、こんな遺言は無効?
だから大丈夫(相続できる)?
結論からいうと、大丈夫ではありません(遺留分を相続できません)。
また、遺言も無効ではありません。

何もしなければ、遺言通りに相続されます。
遺留分を侵害されている相続人が、何もしないで自動的に遺留分割合の財産を相続することは出来ません。

遺留分を侵害されている相続人は、遺留分割合の財産を相続するために、遺留分侵害額請求をする必要があります。
そして、この遺留分侵害額請求というのは、自分の遺留分を侵害する相続人に対し、遺留分の侵害を申し出ます。
遺言そのものが無効になるわけではないのです!(遺言を無効にすることは出来ません。)
遺留分侵害額請求とは、簡単に言ってしまえば
と、Aに通告することです。
Aだけでなく複数人が遺留分を侵害している場合は、その全員に通告します。
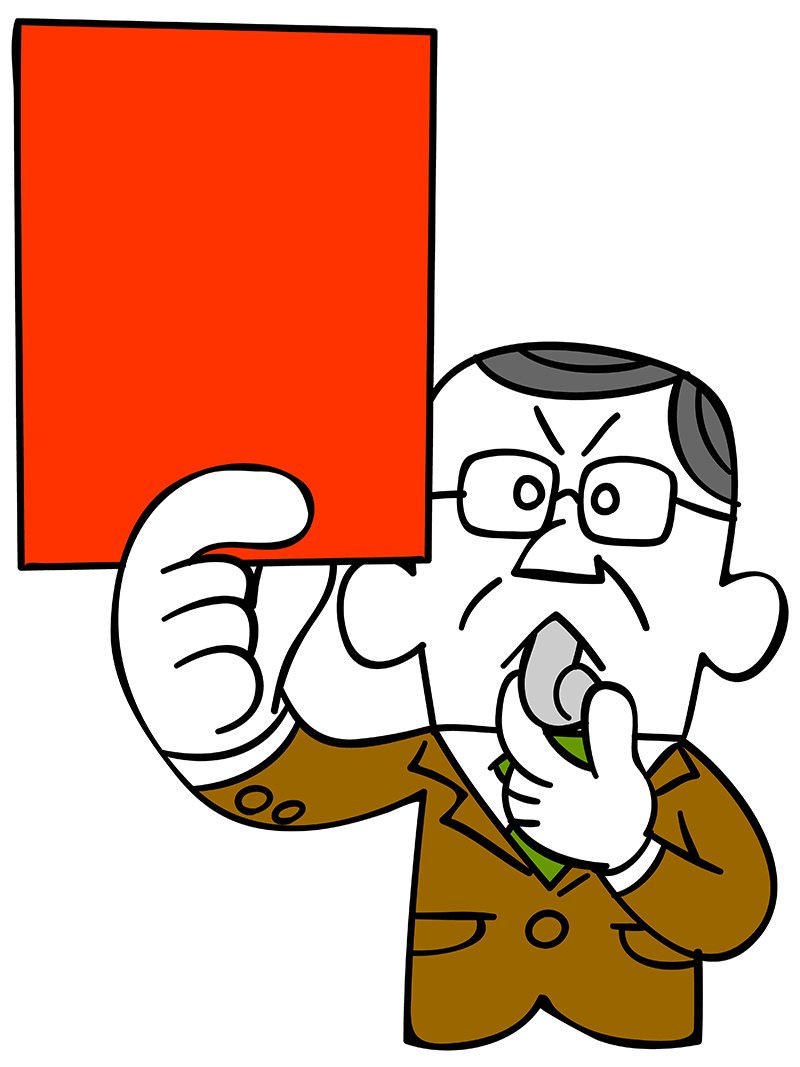
そして、この通告は口頭やメール、手紙などでも出来ますが、証拠の能力として内容証明郵便などを使うのが一般的です。
遺留分侵害額請求をすることができるのは
となります。
遺留分が侵害されていることを相続開始から11年目に知った。
もう時効です。
遺留分侵害額請求をする(財産を返してと通告する)ことは出来ません。
要注意です。
では、遺留分侵害額請求の手続きはどうしたらいいのか?
早い話、遺留分侵害額請求は相手との交渉です。
話し合いがつかない、そもそも話し合いができない時に、遺留分権利者は家庭裁判所の調停手続きを利用することができます。
なので、「遺留分侵害額請求の手続き=即裁判」というわけではありません。

相手(遺留分を侵害している相続人)に、私の最低限の相続分(遺留分)を戻してください!と通告し、話し合いで双方納得すれば裁判をする必要はありません。
そして、たとえ裁判になったとしても、基本的に遺留分を侵害されている相続人のほうが、法律的に認められていることを主張しているので有利となります。

遺留分侵害額請求の手続きは、まず相手(遺留分を侵害している相続人)に通告することです。
そして、通告はよほどのことがない限り、証拠能力の高い内容証明郵便を使って下さい。
遺留分?遺留分侵害額請求?と思ったら、まずは税理士法人 都心綜合会事務所までご相談下さい。
相続税対策・相続相談・相続手続き・相続税申告、お受けしております。
なお、お電話での相続相談は承っておりません。
遺留分侵害額請求について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
突然ですが「遺留分」という言葉を聞かれたことがございますか?
遺留分とは、遺産を最低限受け取ることができる権利のことです。
この遺留分をもつのは、相続人のうち、配偶者、お子さん、親や祖父母までとなり、兄弟姉妹にはありません。
遺留分として認められるのは、基本的に、その人の法定相続分の2分の1となりますが、もし相続人が親や祖父母のみの相続であれば3分の1になる等、例外もあります。
さて、遺留分についてよく「遺留分があるから、必ずその分の財産がもらえる」とお考えの方がいらっしゃるのですが、それは誤解です。
遺留分は単なる権利です。
もし財産がもらえそうにないことがわかったら、自分でその権利を行使しなければなりません。
たとえば亡くなった人が遺言書で、愛人に全財産を譲るというような内容を遺したとします。
この場合も遺族が何もしなければ、その遺言書の内容どおりになってしまいます。
自動的に遺留分がもらえるわけではありません。
では、このような遺言が行われた場合、自分の遺留分をどうやって守るかというと、相手に遺留分侵害額請求というものを行います。
相手というのは、さきほどの例でいうと愛人のことです。
遺留分侵害額請求とは、簡単にいうと「あなたが財産を沢山もらったことで、私の遺留分を侵害しています。ですので、もらったその財産から私の遺留分をください」という請求になります。
もし相手が応じてくれないなど、話し合いで解決できなければ、裁判所での調停を利用することとなります。
それでもダメなら裁判です。
よく「遺留分を侵害されたときは裁判しか方法がない」という誤解があるようですが、まずは話し合いで解決することが一般的となります。
遺留分侵害額請求を行うポイントは、相手への請求に内容証明郵便を使うことです。
口頭で遺留分侵害額請求を行うことについて、法律上ダメという決まりはないのですが、内容証明郵便を使うことによって、いつどのように相手に請求したか、明らかな証拠として残すことができます。
特に大切なのは、いつ請求したかということです。
遺留分侵害額請求には時効があります。
遺留分侵害額請求を行うことができるのは相続発生後、自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年の間か、相続開始から10年の間です。
ほとんどのケースでは1年になると覚えておきましょう。
時効を迎えるまでの間に遺留分侵害額請求を行わなければ、二度と請求できなくなってしまいます。
したがって、いつ請求したかを証拠として残しておくことは、とても重要です。