
法定相続情報証明制度を利用するための手続き方法
被相続人の死亡後から法定相続情報証明制度の利用申請は可能となります。利用申請するには、申出書や様々な書類が必要となってきます。また、相続人によって提出する書類が変わってきます。
被相続人の死亡後から法定相続情報証明制度の利用申請は可能となります。利用申請するには、申出書や様々な書類が必要となってきます。また、相続人によって提出する書類が変わってきます。
法定相続情報証明制度を利用するには、まずは管轄の法務局に申出書の提出が必要です。
申出書の詳しい書き方等については、法務局のホームページの申出書の記入例
に記載されています。
注意点としては申出書に記入する事項で、公文書から内容を読み取れる場合には公文書のとおりに記入します。
申出入の氏名や住所は公文書である住民票の通りに記載します。
なお、申出書の詳しい作成方法については、法定相続情報証明制度の申出書の作成方法に記載しています。
提出先の法務局はどこの法務局でもいいわけではなく、管轄の法務局に提出する必要があります。
管轄の法務局は以下のようになります。
これらの法務局のどれかで手続きをします。
なお、この制度はあくまでも相続登記などの手続のための制度なので、被相続人の生前にあからじめ利用申請することはできません。
被相続人の生前に相続税対策をしているので、ついでに法定相続情報証明制度の利用申請も事前にしておく、というようなことはできません。
あくまでも相続開始後(被相続人の死亡後)からの利用となります。
法定相続情報証明制度の利用の申し出や、一覧図の写しの交付の請求は郵送でも可能です。
法務局に提出する書類は、申出書以外に以下のようなものも必要となります。
1については、被相続人(代襲相続がある場合には被代襲者を含む)の出生時からの⼾籍謄本及び除籍謄本となります。
これは以下の事由等を確認するためです。
また、被相続⼈の兄弟姉妹が法定相続⼈になる場合などは、法定相続⼈の確認のために1の資料に加えて、被相続⼈の親等に係る除籍謄本の添付が必要な場合もあります。
2については、法定相続情報一覧図の記載内容の裏付けと、被相続人を特定するために必要です。
3については、相続⼈全員の現在の⼾籍謄本(全部事項証明書)、⼜は抄本(一部事項証明書)が必要です。
これも法定相続情報一覧図の記載内容の裏付けるために必要となってきます。
4につていは、申出書の記載内容の裏付けと、申出人の本人確認のために必要です。
具体的には
などが必要です。
ただ、住民票などでも問題はありませんが、相続⼈全員の現在の⼾籍謄本⼜は抄本が必要なので、その戸籍謄本を取得するのと同時に、戸籍の附票を取得したほが効率的といえます。
また、運転免許証の写しやマインバーカードの写しの場合には、その写しに原本と相違ない旨を記載し、申出人が署名又は記名押印する必要があります。
それぞれの書類の取得先などの詳しい内容は、法務局のホームページの必ず用意する書類/必要となる場合がある書類
に掲載されています。
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載したい場合には、相続人の住所を証する書面、いわゆる住民票もしくは戸籍の附票が必要となります。
ちなみに法定相続情報一覧図へは
などは必須の記載事項ですが、住所の記載は任意です。
また第2順位及び第3順位の相続人が申出人になる場合には、先順位の相続人が既に死亡していることを証する戸籍なども必要です。
これは申出人が相続人の地位があることを証明するためです。
例えば申出人が第3順位の相続人である兄弟姉妹である場合には、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍も必要です。
兄弟姉妹として相続人になった者が誰で、第3順位の相続人が何人いるのかを証明するためです。
また、同順位の相続人の中に死亡者がいる場合には、その死亡している者の死亡の記載がある戸籍も必要です。
相続人が第2順位や第3順位、同順位に死亡者がいる場合には、申請をする法務局に事前に何が必要かを確認しておきましょう。
申出人が代理人である場合には、委任状や申出の代理権限があるかどうか(いわゆる弁護士や税理士の資格があるかどうか)を証明する書類が必要です。
なお、法定相続情報証明制度の利用の申出や、一覧図の写しの交付を請求できるのは、相続人だけでなく、以下のような専門家に任せることも可能です。
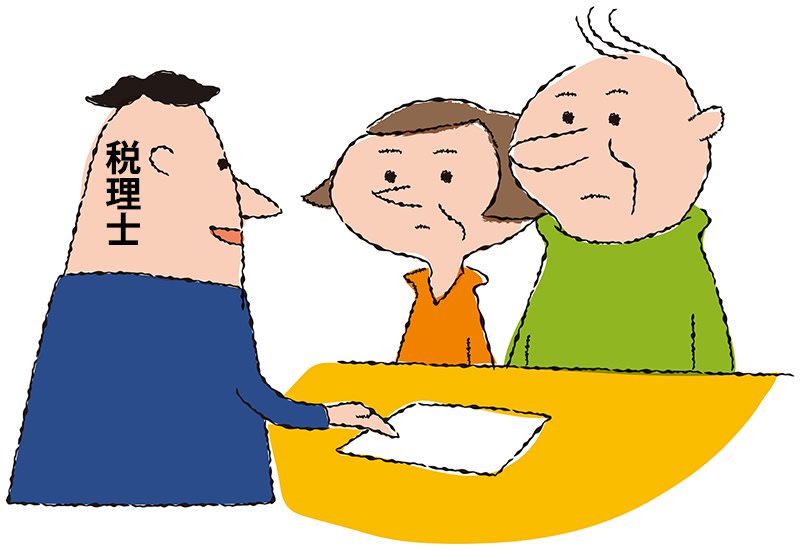
また、法定代理人が本人に代わって申出をする場合には、以下のようになります。
法定代理人とは、法律によって代理権を与えられた者のことをいいます。
また、相続人の親族の方も代理申請できます。
このように秘匿性のある戸籍を扱いますので、本人に代わって手続できる者は、上記のように限定されています。
制度の利用は被相続人単位です。
これはどういうことか?
例えば、被相続人Aとその子供BとBの子供である子供Cがいたとします。
Aが亡くなり、その後すぐにBが亡くなり、子供CがBの相続人の地位を引き継いだとします。
このような場合、Cから見れば、AとBの2つの相続があることになります。
この際CがAとBの相続をまとめて、法定相続情報証明制度を利用することはできません。
両方の相続でこの制度を利用したい場合は、Aの相続で申出・一覧図を作成をし、Bの相続でも申出・一覧図を作成する必要があります。