
家族が死亡してからするべき手続き一覧
死亡後の手続きは相続税の申告だけではありません。本当に様々なものがあります。死亡後の手続きと並行し、相続税対策をして後悔のない相続税の申告をすることは大変な作業となります。相続税対策は早くから始めましょう。
死亡後の手続きは相続税の申告だけではありません。本当に様々なものがあります。死亡後の手続きと並行し、相続税対策をして後悔のない相続税の申告をすることは大変な作業となります。相続税対策は早くから始めましょう。
死亡後の手続きの大まかな流れとしては
となります。
病院で亡くなった場合、亡くなってから2~3時間後には遺体の搬送をしなくてはなりません。
たとえ夜中に亡くなった場合でも同様です。
現在、葬儀社はほとんど24時間対応しています。
葬儀社に連絡をして遺体の搬送をします。
葬儀社が決まっていない場合、病院が葬儀社を紹介してくれることがありますが注意が必要です。
搬送のみの依頼であることを明確にしないと、葬儀もその葬儀社に依頼したことになっている場合があります。
料金等を考えた上で、しっかりと葬儀社を決めたい場合には、亡くなりそうになっている時から葬儀社を検討しておきましょう。
亡くなった際、医師から死亡診断書、もしくは死体検案書(事故や事件による死亡の場合)を渡されます。
この死亡診断書がないと
ができません。
死亡診断書は大切に保管しましょう。
最近では遺体の搬送先に遺体ホテル(遺体安置施設)が増えています。
特に都市部では火葬場の不足で安置期間が長くなっているため、遺体ホテルの利用が多いそうです。
自宅への搬送の場合は
必要があります。
どこに搬送するかなどは葬儀社が指南してくれます。
葬儀スケジュールなどが決まっていなくても、遺体の安置前後には親族・知人・友人・会社関係者等へ逝去のお知らせをしましょう。
逝去報告の例
〇〇日、父Aが✖✖により亡くなりました。
遺体は△△斎場に安置しております。
面会ご希望の方は、息子B(携帯番号は090-CCCC-CCCC)までご連絡ください。
葬儀日程は改めてご連絡致します。
喪主は早い段階で決めましょう。
葬儀社とのやりとりや通夜や葬儀のスケジュールを決める際に、喪主がいたほうが何かとスムーズになります。
一般的に喪主は配偶者が務める場合がほとんどです。
ただ、配偶者が高齢や病気である場合には、子供が務めることもあります。
子供がいない場合は、兄弟姉妹や甥などが喪主を務めることもあります。
死亡した日から7日以内に死亡届を提出にも記載していますが、通夜・葬儀・告別式の前に死亡届を提出します。
一般的には
に提出するのが多いようです。
なお、国外で亡くなった場合には、死亡を知った日から3カ月以内に死亡届を提出します。
死亡届の提出先は、以下のどれかに提出します。
提出できる人は以下のようになります。
注意点として、死亡届に押印した同じ印鑑が必要です。
また、死亡届の提出際に死亡診断書の提出も必要です。
死亡診断書は生命保険金の支払いなどに必要な場合もありますので、提出の前にコピーをとっておきましょう。
そして、死亡届が受理されると火葬許可証を受取れます。
ただ、注意点としては、死亡届は夜間や土日祝日でも受け付けてくれます。
しかし、火葬許可証の交付は役所が開いている平日でしか受け取れません。
ご臨終の翌日から大体1週間以内にお通夜・お葬式等をします。
ご臨終から2週間以内にする手続きは以下のものがあります。
死亡に伴い世帯主に変更が生じた場合、死亡日から14日以内に世帯主の変更手続きをする必要があります。
(なお、夫婦だけの世帯や残った家族が配偶者と15歳未満の子どもだけの場合、次の世帯主が明白なため変更手続きをする必要はありません。)
手続きは新しい世帯主か同一世帯の人、代理人ができます。
提出先は故人が住んでいた市区町村の役所です。
提出の際に必要なものは、以下のとおりとなります。
通常は世帯主変更届(住民異動届)は、死亡届の提出と一緒にします。
様式も転居などの際に提出する住民異動届と同一である場合が多いです。(届け出用紙は提出先の市区町村ごとに異なります。)
世帯主を変更したら世帯主名義になっていたものを
などをしましょう。
また、運転免許証は警察への返納が義務づけられています。
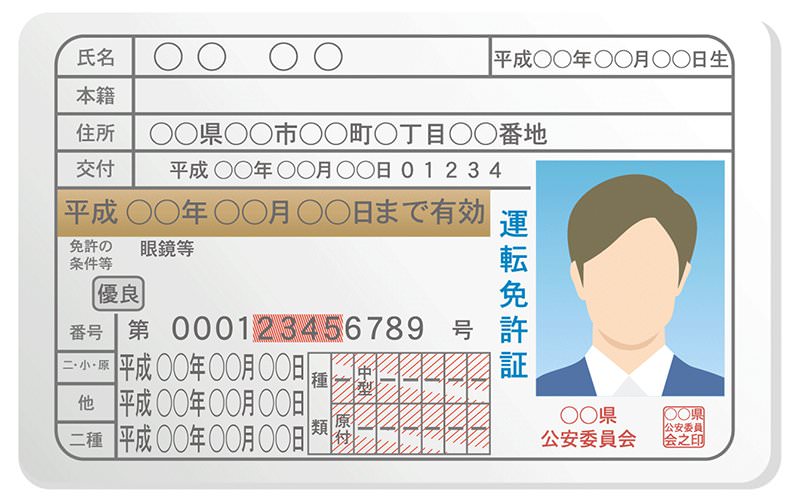
そして以下のような公共料金等の支払いは、世帯主名義になっている場合が多いです。
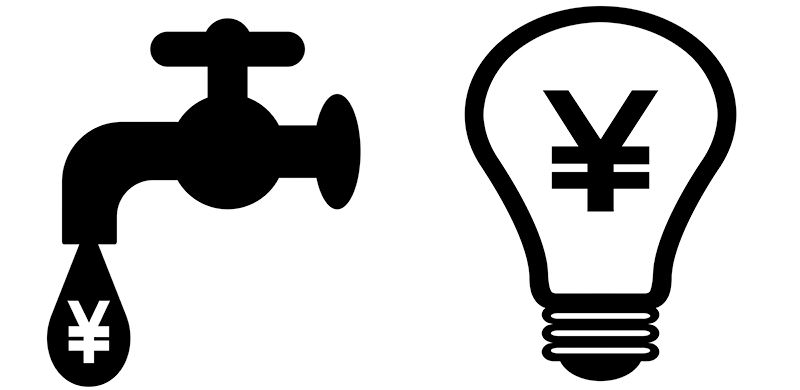
公共料金等の名義変更に期限はありませんが、できるだけすみやかに手続きを行いましょう。
また、クレジットカードの解約手続き等もすみやかに行いましょう。
退会処理をいつまでもしないと、会費などが引き落としされてしまいます。
故人が年金受給者だった場合には、年金受給の停止手続きをする必要があります。
(また、一定の要件を満たせば遺族年金の給付を受取ることができます。詳しくは遺族年金の種類や給付の手続き方法に記載しています。)
厚生年金の場合は10日以内、国民年金の場合は14日以内に手続きをします。
提出先は年金事務所で必要な書類は
また、未支給年金が発生している可能性が高いので、未支給年金の受給手続きもしましょう。
未支給年金についての詳しい内容は、未支給の年金や遺族年金は相続財産ではないに記載しています。
手続きは受給資格のある遺族の方が申請できます。
受給権が発生してから5年以内であれば請求できますが、できるだけすみやかに手続きをしましょう。(5年を超えた場合、時効により権利が消滅します。)
提出先は故人の住所地の市区町村の役所、もしくは年金事務所や年金相談センターとなります。
提出の際に必要なものは、以下のとおりとなります。
手続きは14日以内です。
ただ、社会保険に加入している家族の扶養になる場合は5日以内です。
提出先は
提出に必要なものは、以下のようなものです。
亡くなった方が世帯主の場合は注意が必要です。
扶養されていた家族も資格を失うことになるので、他の家族の扶養、もしくは自身で国民健康保険に加入する必要があります。
また、資格もなくなるので保険証を返却します。
健康保険証がなくなりますので、返納手続きと同時に新しい保険証を作成しましょう。
ちなみに手続きをしたから資格を失うのではなく、返納手続きをしていなくても、死亡した翌日から保険証は使えなくなります。
この期間に以下のようなことをします。
相続税の申告以外にも家族が死亡してからするべき手続きは、上述のように様々なものがあります。
亡くなってから相続税対策を考え、相続税の申告をし、その他様々な手続きを並行してする。
かなりタフな作業となります。
相続税対策は故人の生前中に行うのがベストです。
相続税対策・相続手続き・相続税申告なら税理士法人 都心綜合会計事務所にお任せください。
死亡後の手続きについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
本日のテーマは死亡後の手続きについてです。
ご家族が亡くなられたあと、遺族にはやらなくてはならない手続きが沢山ございます。
手続きの大まかな流れは
・死亡確認をしてもらう
・ご遺体を搬送する
・喪主や世話役を決める
・関係者への連絡をする
・役所に死亡届を提出する
というものになります。
まずは死亡確認です。
病院で亡くなった場合もご自宅で亡くなられた場合も、その方が本当に死亡しているという事実を専門家が確認しなければなりません。
医師が確認することが一般的ですが、近年は看護師にもその確認権限の拡大が進められています。
確認後に受け取る死亡診断書・死体検案書は、その後の役所での手続きに必要になりますので必ず保管しておきましょう。
死亡確認を終えたらご遺体の搬送です。
搬送は葬儀社に連絡をして行ってもらいます。
ご自宅に搬送する場合のほか、専用の遺体安置施設に搬送できる場合もあるので、葬儀社にアドバイスを求めるとよいでしょう。
搬送を終えたら喪主や世話役は早いうちに決めておきましょう。
色々な人が葬儀関係の窓口をやると混乱しますので、1人に決めたほうがいいと思います。
関係者への連絡も早めに行う必要があります。
葬儀の詳細が決まっていない場合は、とりあえず関係者の窓口となる親族を決めて、その電話番号を伝えておけば大丈夫です。
家族葬などの希望がある場合には、その旨をお世話になった人に伝えましょう。
最後は役所への手続きです。
葬儀前に行わなければならないのは、死亡届と火葬の申請になります。
医師等から受け取った死亡診断書・死体検案書をもって行いますが、葬儀社が代行してくれる場合があるため相談してもよいでしょう。
それ以外にも亡くなってから14日以内に、世帯主の変更・年金・医療保険の変更手続き等を行わなければなりません。
さてここまで終わっても、あとは個人の状況に応じて行う個別の手続きが待っています。
口座やクレジットカードなどの停止、会社や自営業を行っていた人はそちらの手続きも必要となります。
ご家族が亡くなられた後には、こんなに沢山の手続きがあります。
これらと併行して行うのが遺産分割の話し合いです。
この部分は生前に対策をしておくことで、死亡後の負担をかなり軽減できますし節税対策も可能です。
相続対策なら税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。