
準確定申告の手続きや期限
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日(亡くなったことを知った日)の翌日から4カ月以内です。準確定申告の計算は、その年1月1日から亡くなる日までの日割りや月割り計算となります。また、準確定申告を行うのは、亡くなった方の相続人となります。
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日(亡くなったことを知った日)の翌日から4カ月以内です。準確定申告の計算は、その年1月1日から亡くなる日までの日割りや月割り計算となります。また、準確定申告を行うのは、亡くなった方の相続人となります。
確定申告をする必要のある人が、その年の中途において死亡した場合には、相続人は相続の開始があったことを知った日(亡くなったことを知った日)の翌日から4カ月以内に、被相続人(亡くなった方)の1月1日から死亡した日までの所得を計算して、準確定申告書を税務署に提出する必要があります。
ただ、確定申告を本来すべき人が、1月1日から3月15日(いわゆる確定申告期限)までの間に、前年分の確定申告書を提出しないで死亡した場合には、前年分の確定申告、本年分の準確定申告とも、提出期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内となります。
納税金額が発生した場合には、納付をする必要があります。ちなみに、還付申告の場合(申告すると税金が戻ってくる場合)には、4カ月以内の提出は必須ではありません。
相続人が2人以上いる時には、各相続人が準確定申告書に連署して提出します。
ただし、他の相続人に申告した内容を通知すれば、他の相続人の氏名を付記して、各相続人が個別に提出することも可能です。
準確定申告の提出先は、提出する相続人の住所地ではなく、被相続人の納税地を所轄する税務署に提出します。
納税地は通常、死亡した人の住所地ですが、事業をしていた場合、事業所の所在地となっていることもあるため、過去の確定申告書などで納税地を確認しましょう。
通常の確定申告は暦年ベースで、1年単位での計算です。ただ、準確定申告はその年1月1日から亡くなる日までの日割り、または月割り計算となります。

各所得控除も亡くなった日までの状態で計算します。例えば、以下は死亡の日までに支払った金額が控除対象となります。(年額で支払っている場合には月割りです。)
配偶者控除や扶養控除の判定は、死亡日現在の状況での判断となります。
被相続人が事業をし青色申告をしていた場合で、相続人も事業を承継して引き続き青色申告をしたい場合には、次のそれぞれの提出期限までに青色申告承認申請書を税務署長に提出しなければなりません。
相続開始日(被相続人の亡くなった日)が、
例えば、12月31日に亡くなった場合には、青色申告承認申請書の提出期限のほうが、準確定申告書の提出期限よりも早くきます。

この青色申告承認申請書の提出は、かなり忘れやすいので注意しましょう。提出先は、その提出をする人の住所地を所轄する税務署となります。
なお、青色申告のメリットには以下のようなものがあります。
概ね以下のような場合には、準確定申告書を提出する必要があります。基本的に被相続人(故人)が確定申告の必要な人であれば、準確定申告をする必要があります。
会社の従業員などであり、死亡時点での年末調整がされている場合には、準確定申告をする必要はありません。
準確定申告をする必要があるのかどうか迷われたら、東京新宿神楽坂の都心綜合会計事務所までご相談ください。

準確定申告の手続きや期限について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
準確定申告とは、亡くなった方の所得について、相続人が代わりに行う、確定申告のことです。
準確定申告の対象になるのは、亡くなった人の1月1日から、死亡日までの所得になります。
ただし、前年の確定申告の申告期限よりも前に亡くなり、前年の確定申告をしないまま、亡くなってしまった方の場合は、前年分の申告も、相続人が行わなければなりません。
確定申告の期限は、通常3月15日ですから、それよりも前に亡くなった方の場合、前年と死亡した年の、2つの準確定申告を行うパターンもある、ということです。
ただし、亡くなった方の全てに、準確定申告が必要になるわけではありません。
亡くなった方に、準確定申告が必要となるケースは、通常の確定申告が必要となるケースと同じです。
たとえば、亡くなった人が、個人事業を営んでいた場合や、不動産賃貸業を営んでいた場合、また、亡くなった方が、会社から給与をもらっている方であれば、給与収入が2,000万円を超えている場合、給与所得や退職所得以外に、20万円を超える所得があった場合、亡くなったときの年末調整が行われていない場合などが、準確定申告が必要になる、主なケースとなります。
続いて、準確定申告を行う人について、お話をします。
準確定申告を行うのは、亡くなった方の相続人です。
相続人が2人以上いる場合は、全員で1通の準確定申告書を提出するか、それぞれが個別に提出するか、選択することができます。
ただし、個別に提出する場合、内容がバラバラにならないよう、他の相続人に申告した内容を通知し、準確定申告書には、他の相続人の氏名などを書いて、提出する必要があります。
続いて、申告期限についてお話します。
準確定申告の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。
前年の準確定申告を行う場合も、その期限となります。
準確定申告書の提出先は、亡くなった方の住所地を管轄する税務署となることが、ほとんどですが、提出先を事業所の所在地にしている場合もあるので、個人事業を営んでいた方の場合は、過去の確定申告書などから、提出先を確認しましょう。
最後に、相続人の青色申告の手続きについて、お話をします。
亡くなった人の個人事業を、相続人が引き継ぐ場合、その相続人は、自分で税務署に青色申告の承認申請書を提出する必要があります。
理由は、青色申告者の地位が、相続では引き継がれないからです。
ただし、その提出期限が、亡くなった方の死亡日によって、変則的となることに、注意をしてください。
亡くなった日が、1月1日から8月31日の場合、青色申告の手続きの期限は、相続開始日から4カ月以内となります。
注意が必要なのは9月以降で、亡くなった日が9月1日から10月31日の場合、手続きは、その年12月31日が期限となり、亡くなった日が、11月1日から12月31日の場合は、翌年2月15日が期限となります。
9月以降に亡くなった場合は、期限が特定の日付に固定されているため、亡くなった日によっては、準確定申告の提出期限よりも、青色申告の承認申請の期限の方が、短くなることがございます。
提出し損ねてしまうと、翌年まで、青色申告の特典を受けられないため、提出期限には十分注意が必要です。
準確定申告は、自分以外の人の確定申告ですから、ご自身の確定申告を毎年している人であっても、なかなか難しいと思います。
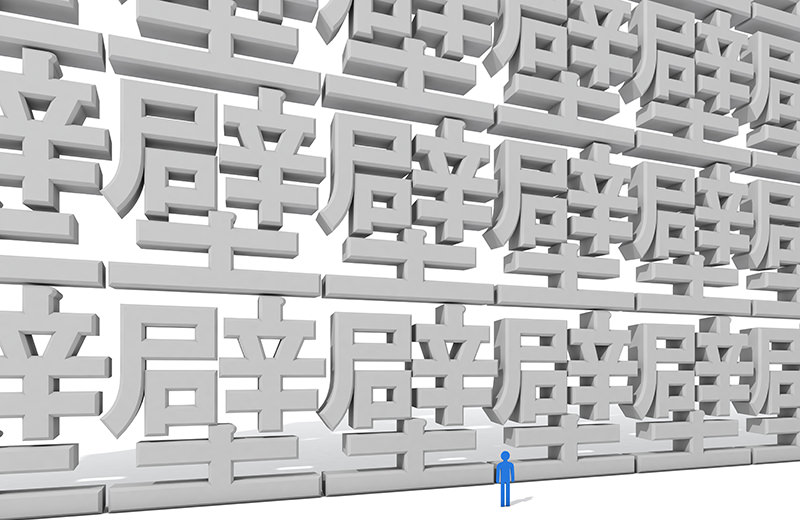
準確定申告が必要かどうか、また、どのように行ったらよいのかなど、迷われたときは、専門家に相談しましょう。