
相続放棄申述書の書き方と家庭裁判所への提出方法
相続放棄申述書は申述人が未成年かどうかで書き方が変わります。また、相続放棄申述書の提出は持参もしくは郵送で行います。手続きミスなどにより相続放棄ができなかった場合、その後の人生設計が大きく狂いかねません。そして相続放棄申述書の書き方や、家庭裁判所への提出には注意点が沢山あります。少しでも不安がある場合や、既に死亡日から3か月を過/ぎている場合には、税理士事務所などの専門家と相談しましょう。
相続放棄申述書は申述人が未成年かどうかで書き方が変わります。また、相続放棄申述書の提出は持参もしくは郵送で行います。手続きミスなどにより相続放棄ができなかった場合、その後の人生設計が大きく狂いかねません。そして相続放棄申述書の書き方や、家庭裁判所への提出には注意点が沢山あります。少しでも不安がある場合や、既に死亡日から3か月を過/ぎている場合には、税理士事務所などの専門家と相談しましょう。
相続放棄申述書は家庭裁判所のホームページからダウンロード可能です。
ちなみにダウンロード先は以下のようになります。
ちなみに相続放棄申述書そのものは、18歳以上などに関係なく同一です。
ただ、未成年(18歳未満)かどうかで書き方が変わってきます。
申述人が18歳以上の場合の記載例
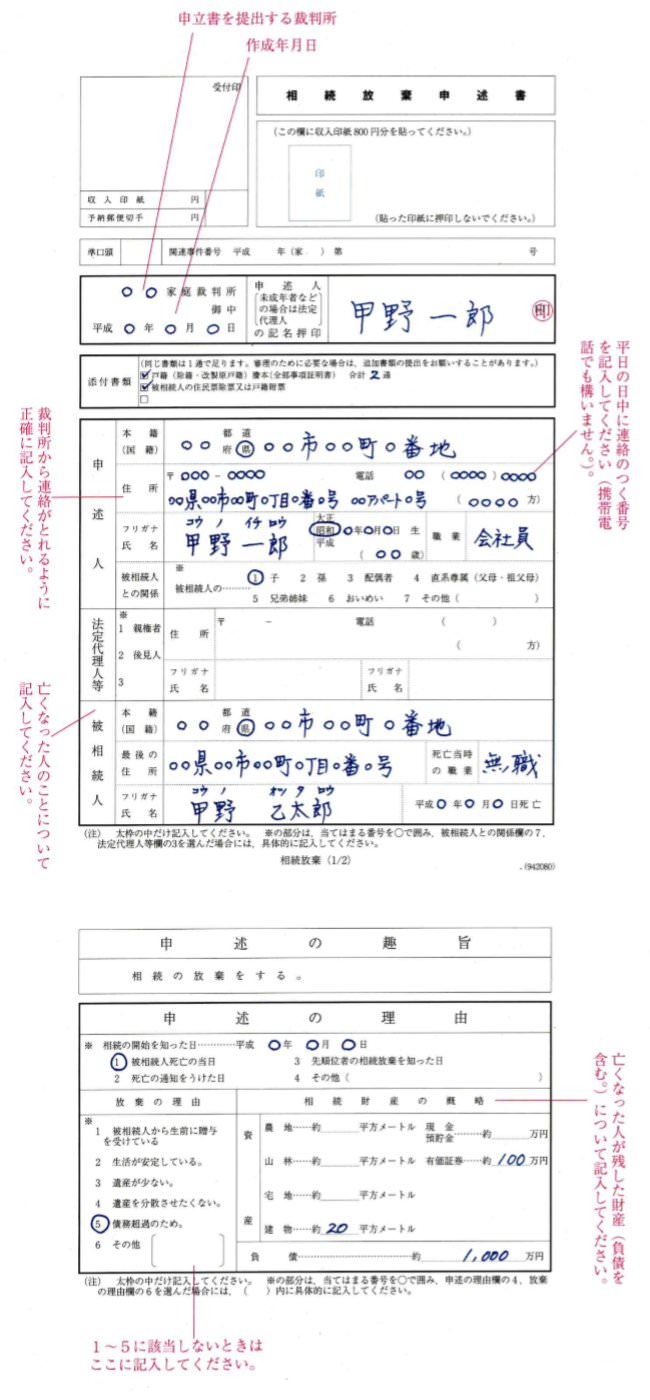
住所や本籍は、住民票や戸籍に記載されているものと同じように記載します。
相続の開始を知った日の欄
相続放棄申述書の2枚目に「相続の開始を知った日」という記載欄があります。
死亡日から3か月以内の提出であれば、ここは死亡日で問題ありません。
ただ、死亡日から3か月を過ぎている場合には注意が必要です。
相続放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にする必要があります。
死亡日=相続の開始があったことを知った時、である場合がほとんどですが、中には死亡日よりも後である場合もあります。
そんな場合には死亡日から3か月を過ぎて、相続放棄申述書を提出する場合があります。
そのような場合に
にマルを付けます。
そして死亡日から3か月を経過している場合には、上申書(事情説明書)も提出するのが賢明です。
(上申書には決められたフォーマットなどはありません。)
死亡日から3か月を経過していると、相続放棄が認められない可能性が高くなります。
なので上申書で死亡日からは3か月を経過しているが、自己のために相続の開始があったことを知った時からは3か月経過していない旨を、しっかりと家庭裁判所へ伝えましょう。
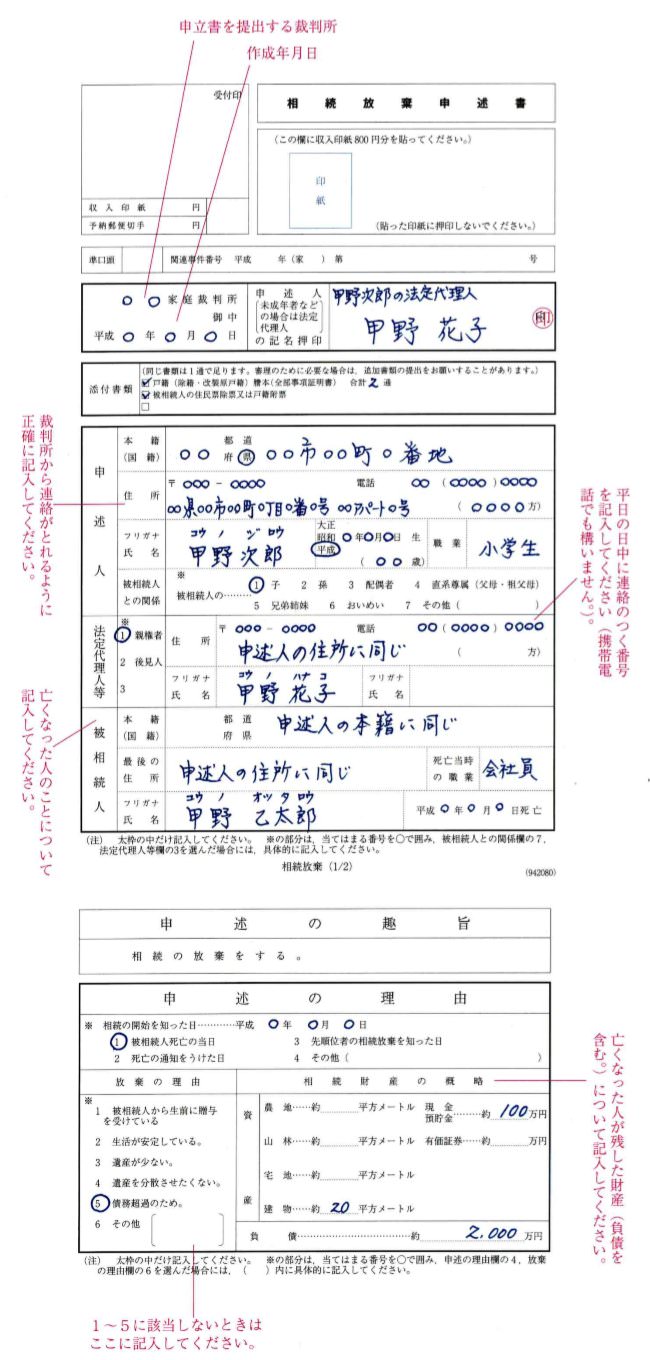
申述人が未成年者や認知症等で成年被後見人である場合は、法定代理人等の欄を記入します。
親権者や成年後見人が本人に代わって記載します。
相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出する必要があります。
また、提出する書類は相続放棄申述書だけではありません。
その他、戸籍謄本なども必要です。
(詳しくは相続放棄に必要な書類は申述人ごとで異なるに記載)
相続放棄申述書などの提出は、家庭裁判所へ持参、もしくは郵送で行います。
郵送の場合は、書留など追跡のできる郵送方法で行いましょう。
また、本当に届いたかどうか必ず確認しましょう。
手違いで届いていない可能性や、間違えて管轄でない家庭裁判所へ提出してしまうこともあり得ます。
郵送で申述書を提出した場合、「照会書」という書面で相続放棄の意思等を確認されることがあります。
これは家庭裁判所が
を確認するためです。
また、一定の事由に該当すると相続放棄はできません。
(詳しくは相続放棄が認められない場合は3か月の経過のみではないに記載)
照会書が届いたら必要事項を記入の上、裁判所に提出しましょう。
決して無視してはいけません。
しっかりと対応しましょう。
また、相続放棄の申述書を持参して提出した場合場合、家庭裁判所によっては、以下のような内容を口頭で確認されるかもしれません。
このような場合にもしっかりと回答しましょう。
提出先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。
申述人の近くの家庭裁判所ではありませんし、また家庭裁判所であれば、どこでもいいわけではありませんので注意しましょう。
なお、最後の住所地とは被相続人の死亡当時の住所のことであり、被相続人の住民票の除票、又は戸籍の附票で確認できます。
また、管轄の家庭裁判所は裁判所の管轄区域で調べることが可能です。
例えば第1順位の相続人である子が相続放棄をしたため、第2順位の父母が相続人になった。
そして、第2順位の父母も相続放棄するために放棄の手続きを開始した。
この場合、第1順位の相続人である子が相続放棄をするために、既に被相続人の死亡時の戸籍を提出しています。
なので第2順位の父母が相続放棄の手続きをする際には、被相続人の死亡時の戸籍を提出は不要です。
ただし、管轄の家庭裁判所に本当に不要かどうかは、念のため確認しておきましょう。
また、戸籍や戸籍の附票、住民票の除票などは取得にお金がかかります。
管轄の家庭裁判所によっては、原本の返却を希望すれば、原本を返却してくれる場合もあります。
戸籍や戸籍の附票、住民票の除票を使い回したい場合には、原本返却を希望してみましょう。
相続放棄申述書の書き方と家庭裁判所への提出方法について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
相続を放棄するには、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなくてはなりません。
もし、定められた期間内に相続放棄の手続きや、その期間を延長する手続きを行わなければ相続を放棄することはできません。
今回は相続放棄を行うために必要な相続放棄申述書について、作成のポイントや提出時の注意点などについてお話を致します。
まず、相続放棄申述書には申述人の記名押印が必要となります。
申述人とは相続放棄を行う人を指します。
ただし、申述人が未成年者や成年被後見人の場合、この記名押印は親権者や成年後見人が行います。
さらに「法定代理人等」の欄にも申述人の親権者や成年後見人の住所、氏名、連絡先を記載する必要があります。
成年後見人とは認知症や知的障害などによって、法律判断が難しい方の代わりに、法律行為を行う人として選ばれた人のことです。
続いて申述の理由の欄にある「相続の開始を知った日」ですが、ここには次の4つの選択肢があります。まず
の4つです。
相続放棄ができる期間は、原則として相続があったことを知った日から3ヶ月以内です。
この4つの選択肢は相続放棄ができる期間を過ぎていないかどうか、確認するためのものになります。
もし申述書を提出する日が亡くなった日から3か月以内であれば、1の被相続人死亡の当日を選んで問題ありません。
これに対して3ヶ月以上経過している場合は、2から4の選択肢を使用します。
3の先順位者の相続放棄を知った日とは、申述人の前の相続順位にあった相続人が相続放棄を行ったことを知った日です。
相続人には相続順位があって、子や親などが相続放棄をすると、その相続権は次の順位の相続人に移ります。
前の順位の相続人が相続放棄をしたことで、新たに相続人となった人については先順位者の相続放棄を知った日が基準となります。
もし3ヶ月以上経過して、相続放棄申述書を提出する場合は、できるだけ上申書など任意の様式を作成し、3ヶ月を経過した理由を添えるようにしましょう。
続いて家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する時の注意点です。
まず、相続放棄申述書の添付しなければならない書類について、ご説明いたします。
相続放棄申述書には、戸籍謄本など決められた書類の添付が必要です。
添付する書類については、相続放棄申述書の「添付書類」の欄にチェックを入れ、合計何通提出するか数字を書き込まなければなりません。
必要な添付書類は申述人と亡くなった人の関係によって変わります。
ただし、他の相続人が既に相続放棄を行っている場合、添付書類が他の相続人と重複することがあります。
このとき既に提出されている添付書類については、提出を省略することができます。
ムダな書類を提出しないために、提出先の家庭裁判所にあらかじめ連絡をして、添付が必要な書類を確認するとよいでしょう。
また家庭裁判所によっては、戸籍謄本や住民票の除票などの原本を返還する手続きも可能ですので、必要に応じて裁判所に確認をしてみて下さい。
次に提出先の家庭裁判所や提出方法についてご説明します。
相続放棄申述書の提出先は、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
どの裁判所が管轄になるかは、裁判所のHPで確認できます。
提出方法は裁判所に直接持ち込むか、郵送で行います。
郵送の場合は書留など、追跡できる郵送方法で行いましょう。
最後は家庭裁判所に提出した後の注意点です。
家庭裁判所に相続放棄申述書を提出した後は、裁判所から質問や確認などの連絡が行われることもあります。
特に郵送で申述書を提出した場合、「照会書」という書面で確認が行われることがあるので必ず対応しましょう。
ただし、郵送で提出した場合は、できれば自分から電話などで無事に受理されたことを一度確認しておくことが望ましいです。
相続放棄はミスの許されない手続きです。
専門家に相談して行うことをおすすめします。
そして相続のことなら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。
相続のワンストップサービスを提供しております。