
相続時精算課税制度のメリットやデメリットは?安易な適用は危険
相続時精算課税制度にはさまざまなメリットがあります。うまくこの制度を有効活用すれば、大幅な節税効果も見込めます。ただし、メリットにはデメリットもつきもの。相続時精算課税制度のメリット・デメリットのご紹介です。
相続時精算課税制度にはさまざまなメリットがあります。うまくこの制度を有効活用すれば、大幅な節税効果も見込めます。ただし、メリットにはデメリットもつきもの。相続時精算課税制度のメリット・デメリットのご紹介です。
相続時精算課税制度を利用すれば、贈与税なしで生前に贈与できる。
こう思われている方は、少なからずいらっしゃいます。
では「完全に間違っているのか?」というと、そういう訳でもありません。
ただ、相続時精算課税制度というのは、読んで字のごとく「相続の時に精算して課税しますよ」という制度です。
そして相続時精算課税制度のメリットはもちろんあるのですが、本来なら相続税がかかるものが、かからなくなるといった魔法の制度ではありません。
また、下手をすると相続税を多く払うことになる可能性もあります。
相続時精算課税制度は複雑な制度です。
そして、一度この制度を利用したら生涯にわたり撤回することができません。
相続時精算課税制度を利用する際には、必ず専門家と相談してください。
また、相続時精算課税制度とは、そもそもどういった仕組みなのか?については、相続時精算課税制度とは?適用要件・手続・計算の仕組みを解説に詳しく記載しています。
相続時精算課税制度のメリットとデメリットを完全に把握した上で、この制度を利用するかどうか検討しましょう。
相続時精算課税制度のメリットは主に以下の4つです。
とくに累計で2,500万円まで贈与税がかからない点は大きなメリットです。
贈与には、暦年課税と相続時精算課税の2種類あります。
暦年課税の場合には非課税枠が年110万円ですが、相続時精算課税を選択すれば累計で2,500万円まで贈与税はかかりません。
(ちなみに令和6年1月1日以降からは、相続時精算課税制度を適用している方でも年間110万円の基礎控除が受けられます。ただ、今回の説明ではわかりやすくするため、その部分は計算から外しています。)
累計というところがポイントでもあります。
例えば
をしても、ともに贈与税がかかりません。
3年目に100万円を贈与した。
これには贈与税がかかってきます。
(相続時精算課税を選択適用した場合、贈与税率は一律20%となります。)
また、1年目で3,000万円贈与したら、2,500万円を差し引いた500万円に贈与税がかかってきます。
このような制度のため、暦年課税に比べて多額の財産を通常の贈与より少ない贈与税額にて、早期に贈与することができるというメリットがあります。
ちなみに暦年贈与のメリットについては生前贈与とは何?相続との関係は?に記載しています。
相続税の財産評価は、原則として相続時の価額で評価することとなります。
ただし、相続時精算課税を選択している場合においては「相続時精算課税適用財産」として「贈与時の価額」を相続税の課税価格に算入することになります。
つまり、相続時の価額ではなく贈与時の価額で評価することとなります。
したがって時の経過によりその価値が増加する財産については、その増加分の相続税を抑えることができます。
具体例としては、ある土地Aを相続時精算課税制度を利用して贈与した。
その時の価格が3,000万円。
数十年後、相続が発生(贈与者が死亡)。その時の土地Aの価格が5,000万円。
でも、相続税の計算としては「贈与時の価格の3,000万円で計算する」ということになります。
暦年課税と共通することですが、あらかじめ贈与された財産については、相続時において財産の取り合いになることはありません。
したがって生前に贈与した財産について、遺産分割をめぐるトラブルに発展する可能性は低くなると言えます。
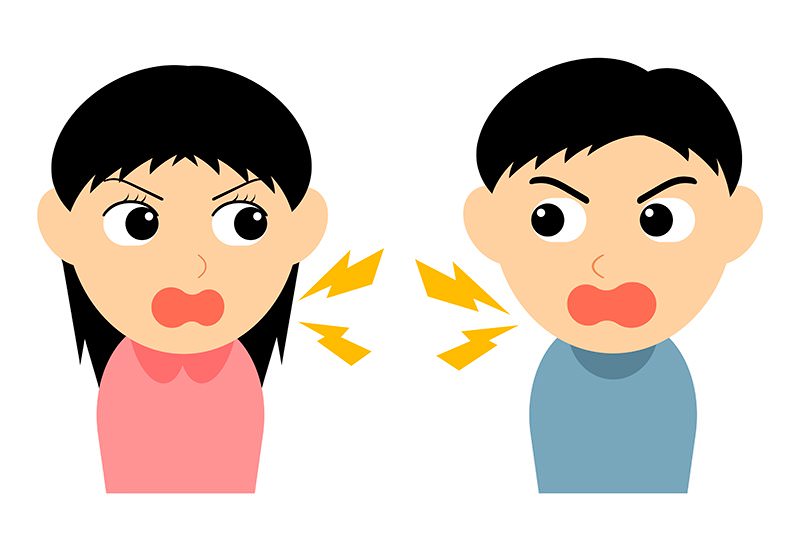
ただし、相続発生時の遺産分割において、相続時精算課税制度で既に贈与された分を特別受益として遺産に加えて計算される可能性はあります。
特別受益についての詳しい内容は特別受益に該当するものや計算方法!そしてバレる原因は?に記載しています。
また、相続争いを防ぐ方法として、以下の関連記事をご紹介致します。
収益物件などがある場合、ほうっておくと、ひたすら相続財産が増えることになります。
この収益物件を相続時精算課税制度を利用して贈与した場合には、その贈与後にその収益物件からもたらされる収益(賃貸料など)は、受贈者(財産をもらった人)に帰属することになります。
したがって贈与者の財産の増加を抑えることができ、受贈者(次世代)の財産を増やすことができます。
つまり、次世代への所得分散と財産承継が可能になります。

所得分散の方法としては、不動産管理会社を設立するといった方法もあります。
詳しくは不動産管理会社で所得分散や不動産名義を法人にし財産圧縮を図るに記載しています。
相続時精算課税制度のメリットを見てきました。
メリットだけみると、今すぐにでも相続時精算課税制度を適用したいと思う方もいるかもしれません。
でも、ちょっとお待ちください。
相続時精算課税制度にはデメリットもあります。
相続時精算課税制度のデメリットは主に以下の5つです。
小規模宅地等の特例を適用できる場合には、最大限の注意が必要です。
よくよく調べたら、小規模宅地等の特例を適用できることがわかった。
相続時精算課税制度を撤回して小規模宅地等の特例を適用したい。
このようなことはできません。
一度、相続時精算課税制度を選択したら生涯に渡り取り消しできません。
ただし、相続時精算課税は贈与者(財産をあげる人)ごとに選択することが可能です。
例えば父からの贈与については相続時精算課税を選択し、母からの贈与については暦年課税を選択するということが可能です。
相続時精算課税制度を選択して土地等を贈与した場合には、その土地等については小規模宅地等の特例を適用できません。
小規模宅地等の特例とは一定の要件等がありますが、事業用・居住用であれば80%、貸付用であれば50%を土地の価額から減額できる制度のことです。
小規模宅地等の特例についての詳しい内容は小規模宅地等の特例は8割も評価減が可能な相続税対策の王様に記載しています。

収益物件だからと言って、本当に相続時精算課税制度を適用していいのか?
その収益物件が土地等である場合は、充分に検討する必要があります。
相続税は金銭一括納付が原則ですが、金銭で納付することが困難である場合には、納税者の申請により物納が認められています。
(物納についての詳しい内容は相続税の物納制度の利用は簡単ではない!その仕組みや手続方法に記載しています。)
しかし、相続時精算課税制度を選択して贈与された財産については、物納は認められません。

メリットの所で「相続税の財産評価額が安くできる可能性がある」と記述しました。
でも逆に、贈与した時の財産評価額が高額で、相続した時にはほとんど価値がないといった場合でも、相続財産は贈与した時の財産評価額で計算します。
なので、相続税が多くなる可能性もあります。

相続と比べると、贈与(相続時精算課税)の登録免許税の税率は高くなります。
~以下、国税庁HP(登録免許税の税額表)より引用~
(1)土地の所有権の移転登記 内容 課税標準 税率 軽減税率 売買 不動産の価額 1,000分の20 令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15 相続、法人の合併又は共有物の分割 不動産の価額 1,000分の4 - その他(贈与・交換・収用・競売等) 不動産の価額 1,000分の20 - 相続による土地の所有権の移転登記について、次の免税措置があります。
※「相続による土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置について」をご覧ください。
➀相続により土地の所有権を取得した個人が、その相続によるその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、令和7年3月31日までに、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税は課されません。
➁個人が、令和7年3月31日までに、土地について所有権の保存登記、又は相続による所有権の移転登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額(注)が100万円以下であるときは、その土地の所有権の保存登記又はその土地の相続による所有権の移転登記については、登録免許税は課されません。
(2)建物の登記 内容 課税標準 税率 軽減税率 所有権の保存 不動産の価額 1,000分の4 個人が、住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合については「住宅用家屋の軽減税率」を適用 売買又は競売による所有権の移転 不動産の価額 1,000分の20 同上 相続又は法人の合併による所有権の移転 不動産の価額 1,000分の4 ー その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) 不動産の価額 1,000分の20 - (注) 課税標準となる「不動産の価額」は、市町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は、その価格です。固定資産課税台帳に登録された価格がない場合は、登記官が認定した価額になりますので、その不動産を管轄する登記所にお問い合わせをする必要があります。
相続だと「1,000分の4」である登録免許税が、贈与(相続時精算課税)だと「1,000分の20」になります。
また、相続で不動産を取得したのであれば、不動産取得税は課税されませんが、贈与(相続時精算課税)では課税対象となります。
なお、不動産取得税の計算方法は、以下のようになります。
~以下、東京都主税局HP(2 不動産取得税の計算方法)より引用~
【取得した不動産の価格(課税標準額)➀】 × 【税率➁】
➀令和9年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合、当該土地の課税標準額は価格の1/2となります。
➁税率は以下のとおりです。
取得日 土地 家屋
(住宅)家屋
(非住宅)平成20年4月1日から令和9年3月31日まで 3/100 4/100
現時点で相続時精算課税制度を利用して宅地の贈与を受けた場合、「固定資産税評価額の1.5%の不動産取得税」がかかることになります。
相続時精算課税と暦年課税の違いをまとめると、以下のようになります。
| 項目 | 相続時精算課税 | 暦年課税 |
|---|---|---|
| 税率 | 一律20%(2,500万円を超えた金額に対して) | 累進課税 詳しくはこちらに記載 |
| 贈与財産 | 限定なし | 限定なし |
| 控除金額 | 1年間で110万円 その他、生涯で2,500万円 | 1年間で110万円 |
| 計算期間 | 届出から相続開始時まで | 1年 |
| 申告の義務 | 年110万円を超える場合 | 年110万円を超える場合 |
| 物納の利用 | 不可 | 可能 |
| 贈与する人 | 60歳以上の父母及び祖父母 | 年齢制限なし |
| 贈与される人 | 18歳以上の推定相続人たる子供及び孫 | 年齢制限なし |
| 相続時の加算 | 毎年110万円超の金額 | 相続開始前3~7年以内の贈与 |
| 贈与税の還付の有無 | 還付される | 還付されない 詳しくはこちらに記載 |
相続時精算課税制度のメリットとデメリットについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。