
非上場株式(取引相場のない株式)の相続税評価方法
自社株式などの非上場株式(取引相場のない株式)といっても、家族経営などの零細企業から上場企業と変わらない位の企業規模と様々です。よって、会社の規模や株主の支配力に応じた評価方法が定められています。
自社株式などの非上場株式(取引相場のない株式)といっても、家族経営などの零細企業から上場企業と変わらない位の企業規模と様々です。よって、会社の規模や株主の支配力に応じた評価方法が定められています。
相続財産として、株式と言えば上場株式が真っ先に思い浮かぶかと思います。
ただ、もしも被相続人が株式会社を経営していた場合には、たとえどんなに零細企業であろうと、経営していた会社の株式というものがあります。
中小零細企業の場合は、全ての株式をオーナーやその配偶者だけで持っていることがほとんどです。
ちなみに、このような株式を取引相場のない株式といい「上場株式及び気配相場等のある株式以外の株式」のことを指します。
簡単に言えば、他人と売買できない株式です。
この取引相場のない株式も相続財産の対象となります。
そして、やっかいなのがこの取引相場のない株式評価方法。
金額に換算すると一株いくらになるのか?という計算方法が、上場株式と違い大変複雑です。
ちなみに株式会社以外の持分会社、医療法人、企業組合に対する出資も取引相場のない株式の評価方法に準じて財産評価します。
一口に中小零細企業といっても、家族経営などの零細企業から上場企業と変わらない位の企業まで様々です。
また、株主の会社に対する支配力にも大きな差があります。

ゆえに、実態に即した会社の規模や株主の支配力に応じて評価方法が定められています。
まずは株式を取得した株主が
の2つに大きく分けます。
1の支配力を有する同族株主である場合は、原則的評価方式により評価します。
2の支配力を有しない株主である場合は、特例的評価方式により評価します。
具体的には次の1から4に該当する場合は、特例的評価方式により評価し、それ以外は原則的評価方式により評価します。
(※)一定の要件とは、以下の3つの要件すべてをいいます。なお、4については1の「同族株主」を「株主」に読み替えて準用して下さい。
原則的評価方式か特例的評価方式に分けて上で、原則的評価方式の場合には、さらに評価方法を以下の3つの区分に分けて行います。
大会社
大会社は、原則として類似業種比準方式により評価します。
類似業種比準方式は類似業種の株価を基に、評価する会社の一株当たりの
の三つで比準して評価する方法です。
中会社
次の3つの区分に応じて、類似業種比準価額方式と純資産価額方式の併用により評価します。
純資産価額方式とは、会社の有する資産の評価額から負債の評価額を控除した純資産価額を基に算出します。
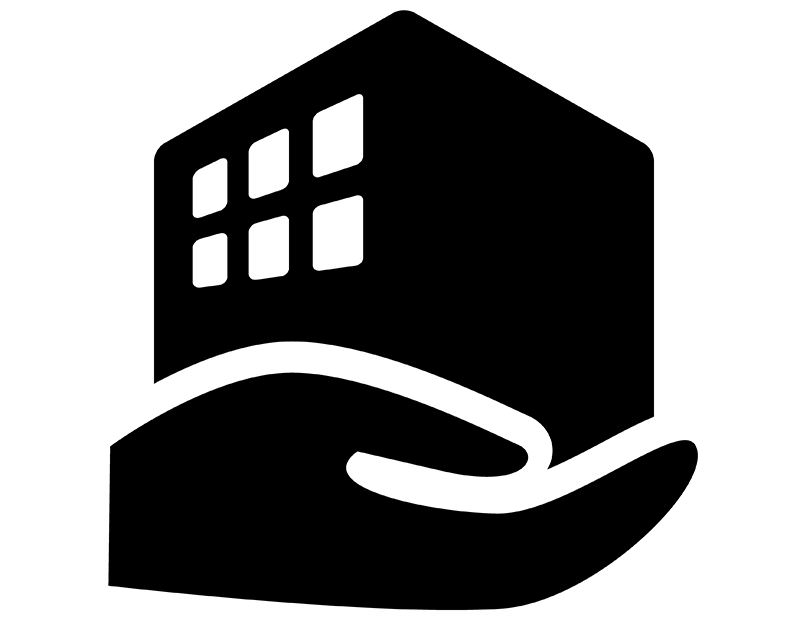
小会社
原則として純資産価額方式によって評価します。
ただし、納税義務者の選択により、類似業種比準価額×0.5+純資産価額×0.5での評価も可能です。
同族株主以外の人が株式を取得した場合には、会社の経営ということよりも「配当を期待している」と考えられます。
そのため、特例的評価方式は受取配当金をもとにした配当還元方式により評価します。
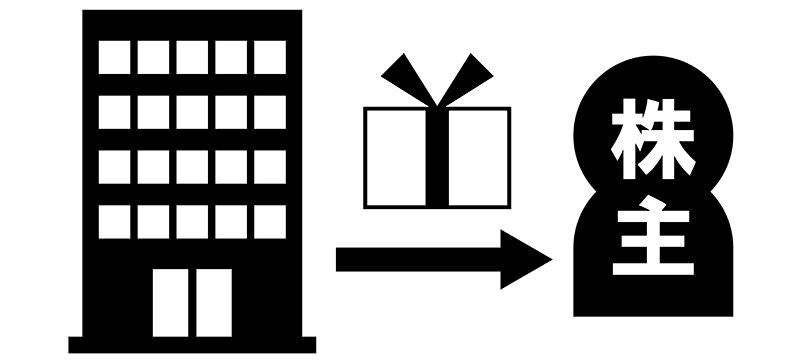
配当還元方式は、その株式を所有することによって受け取る一年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。
取引相場のない株式でも、以下のような会社は、それぞれの状況に応じた評価方法が必要となってきます。
取引相場のない株式の相続税評価額を算出するには「法人税の決算書や申告書」が必要です。
その際、決算書の貸借対照表が重要となってきます。
決算書の貸借対照表で、主に以下のようなことを確認します。
注1:法人税の別表2で、とりあえず誰が株主になっているのかも確認します。
ただし、実際の株主の判定に法人税申告書別表2は証拠にならないに詳しく記載していますが、証拠にはなりません。
また、事業概況書などでは、以下のようなことを確認します。
取引相場のない株式評価は専門家でも大変な作業となります。必ず専門家に依頼しましょう。
ただ、相続税対策の一環として、評価方法の概要だけでも知っておいて損はありません。
原則として、類似業種比準価額方式での評価はできません。
純資産価額方式で評価します。
純資産価額方式で「1株当たりの純資産価額」を計算した後、「対顧客直物電信買相場」により邦貨換算します。
資産や負債が2カ国以上に所在している場合には、資産は「対顧客直物電信買相場(TTB)」により、負債は「対顧客直物電信売相場(TTS)」により、それぞれ邦貨換算した上で「1株当たり純資産価額」を計算することも認められています。