
養子は実親と養親の両方からの相続は可能?
普通養子縁組の場合、養子は実親と養親の両方から相続できます。特別養子縁組の場合は、実親から相続することはできません。また、二重の相続権と似た言葉に「二重資格の相続人」というものがありますが意味は全く異なります。
普通養子縁組の場合、養子は実親と養親の両方から相続できます。特別養子縁組の場合は、実親から相続することはできません。また、二重の相続権と似た言葉に「二重資格の相続人」というものがありますが意味は全く異なります。
普通養子縁組の場合、養子は実親と養親の両方から相続できます。
民法で「養子と養親およびその血族との間においては、養子縁組の日から血族間におけると同一の親族関係を生ずる」という規定があります。
なので、養子は法的に実子と同じ扱いを受けます。
だからといって、実親との親子の関係がなくなるわけではありません。
なので普通養子縁組の場合、養子は養親の子供でもあり、実親の子供でもあります。
よって、二重の相続権をもつことになります。
これは養親の親が亡くなっても養親の財産を相続でき、元親が亡くなっても元親の財産を相続できるということです。
なんだかおかしいな?と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、現状はこのようになっています。
特別養子縁組の場合、普通養子縁組と違い、実親から相続することはできません。
これは特別養子縁組の場合、法律上、元の親(実親)との親子関係が消滅するからです。
もちろん、養親から相続することは出来ます。
養子縁組には、もう一つ二重資格の相続人という論点が発生する場合があります。
相続税対策のために孫を養子にするということがあります。
(詳しくは相続を飛ばせるに記載)
このこと自体は何の問題もありません。
問題は孫を養子にした状態で孫の親(養親から見た場合は子供)が養親より早く亡くなった場合です。
この状態で養親(祖父母)が亡くなると孫は
と2つの相続権を持つことになります。
祖父母の養子になったからといって、孫の資格(代襲相続権)を失うということはありません。
これがいわゆる、二重資格の相続人というものです。
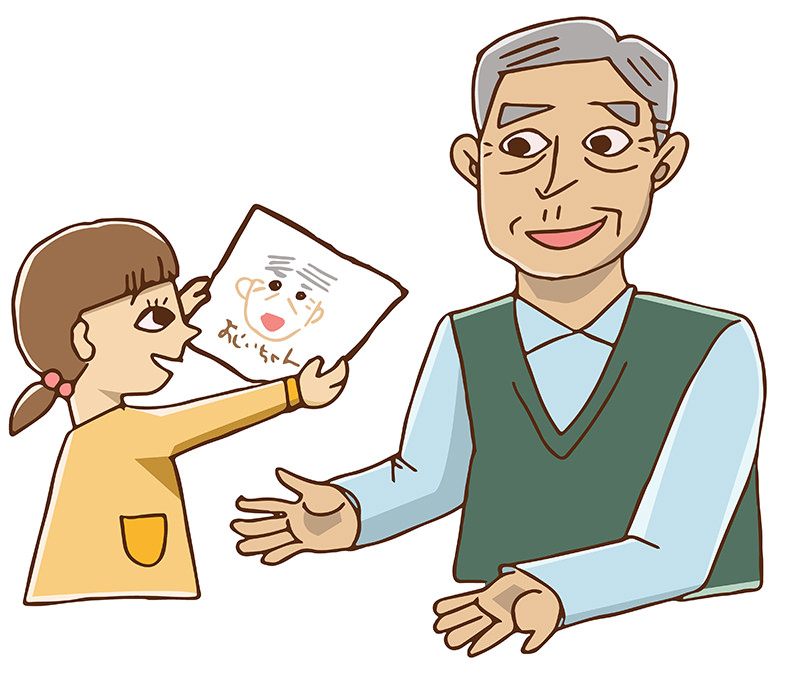
このように2つの相続権が発生している人を二重資格の相続人といいます。
二重の相続権と二重資格の相続人。
言葉は似ていますが意味は全く異なりますので注意しましょう。
被相続人が亡くなる直前にAと養親縁組をした。
しかし、被相続人の子供であるBは、この養子縁組は遺産が目的であるとして無効を訴えた。
このような場合、相続税の計算はどのようにしたらいいのか?
Aを法定相続人に含めて計算するのか?
結論をいいますとAを法定相続人として相続税を計算します。
なので、この場合の基礎控除額は4,200万円(3,000万円 + 600万 × 2人)となります。
争いがないものとして計算するということです。
しかし、AとBが係争中であるため「遺産分割がまとまる」ということはありえません。
ただ、このような状況でも相続税の申告期限は相続開始日(被相続人が亡くなった日)から10カ月以内と変わりません。
よって、AとBの相続分を1/2(法定相続分)として未分割申告します。
(未分割申告についての詳しい内容は、未分割での相続税申告は最終手段と考えるべきに記載しています。)
そして訴訟の判決により、Aを養子として認めるかどうか確定した時に「修正申告」又は「更正の請求」をするという流れになります。
養子縁組と相続の関係について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
養子縁組とは、具体的な血縁関係とは無関係に人為的に法律上の親子とするための手続きです。
養子縁組によって親子になると、法律上の扶養義務が生じたり、養親が死亡したときの相続人となります。
養子縁組の基本としてまず知っておきたいのは、普通養子縁組と特別養子縁組の違いです。
どちらも法律上の親子関係を生じさせるものですが、この二つには実親との関係に違いがあります。
普通養子縁組の場合、実親との関係は法律上そのままになります。
そのため養子になっても養親と実親の両方から遺産を相続することができる、二重(の)相続権をもつことができます。
なんだかおかしな話だと感じるかもしれませんが現状はこのようになっています。
これに対し特別養子縁組の場合は、実親との親子関係はなくなります。
養親の相続人にはなれますが実の親の相続人にはなれません。
なぜこのような違いがあるかというと、特別養子縁組は子供の福祉のための制度だからです。
特別養子縁組ができるのは実の両親の同意がある15歳未満の子どもと、その子どもを実の子として育てたい夫婦に限られています。
そのため本当の親と育ての親のような区別はなく「養親=実親」とするのが特別養子縁組という制度となります。
続いて、相続と養子縁組の話でよく出てくるのが孫養子という言葉です。
その名のとおり、おじいちゃんやおばあちゃんと孫が普通養子縁組をすることをいいます。
孫養子はもちろん祖父や祖母の相続人の資格を得ることになります。
孫と養子縁組をするメリットは相続税の節税になることです。
法定相続人が1人増えると相続税の基礎控除額といって、相続税がかからない財産の枠が600万円も増えます。
ただし養子縁組によって、無制限に基礎控除額を増やすことはできません。
基礎控除の計算に入れることができる養子は最大2人までで、祖父母に実の子がいれば1人までと決まっています。
そして少しややこしい話となりますが、孫と養子縁組をすると孫に二重資格が生じることがあります。
これは孫を養子にしたあと、祖父や祖母より先に孫の親が亡くなると、孫には養子としての資格と先に亡くなった親の代襲相続人としての資格が発生します。
さきほど養子縁組の話で出てきた実親と養親との二重の相続権と似ていますが、こちらは同じ相続人から二重に相続権を得ることを言いますので、意味はまったく異なります。
最後に養子縁組をしたものの、その縁組が無効ではないかと裁判になってしまい、その途中で相続税の申告をするときの話を致します。
養子縁組をする人の中には、親子関係を築くことが目的ではなく、遺産のために形だけの養子縁組を利用しようとする人がいます。
しかし、こうした養子縁組は無効です。
そのため遺族から養子に対して「その養子縁組が無効ではないのか」と訴えられることがあります。
この争いが決着しなければ、遺産を分けることは当然できません。
しかし、相続税の申告期限までは10ヶ月しかありません。
この場合どうすればいいのかというと、相続税の申告は、とりあえず争いがないものとして養子縁組をした状態のまま行います。
遺産分割もできていないのに、どうやって相続税を計算するのかというと、それぞれの法定相続分で遺産を分けたと仮定して計算を行います。
そして問題が解決して遺産分割が確定してから、必要に応じて修正申告や更正の請求をすることになります。