
法定相続人になれるルールは第1位~第3位まである
配偶者は必ず法定相続人になりますが、血族であれば誰でも法定相続人なれるわけではありません。法定相続人になれるルールについて解説しています。
配偶者は必ず法定相続人になりますが、血族であれば誰でも法定相続人なれるわけではありません。法定相続人になれるルールについて解説しています。
そもそも法定相続人とは、相続できる権利がある人のことを言います。
これは民法で定められています。
(厳密にいえば民法で定めているのは相続人です。相続税法で相続の放棄があった場合に、その放棄がなかったものとした場合における相続人を法定相続人と定義しています。詳しくは相続放棄しても基礎控除額は変わらないし税金も安くならないに記載しています。説明の便宜上、ここでは法定相続人という表現で説明しています。)
突然ですが兄弟がいたとして、そのうちのAさんがお亡くなりになられました。
さて、あなたはAさんの財産を相続できる権利はありますでしょうか?
いわゆる法定相続人に該当するでしょうか?
答えは・・分かりません。
となります。
決してふざけているわけではありません。
Aさんの家族状況によって、あなたが法定相続人に該当するかどうか変わってきます。
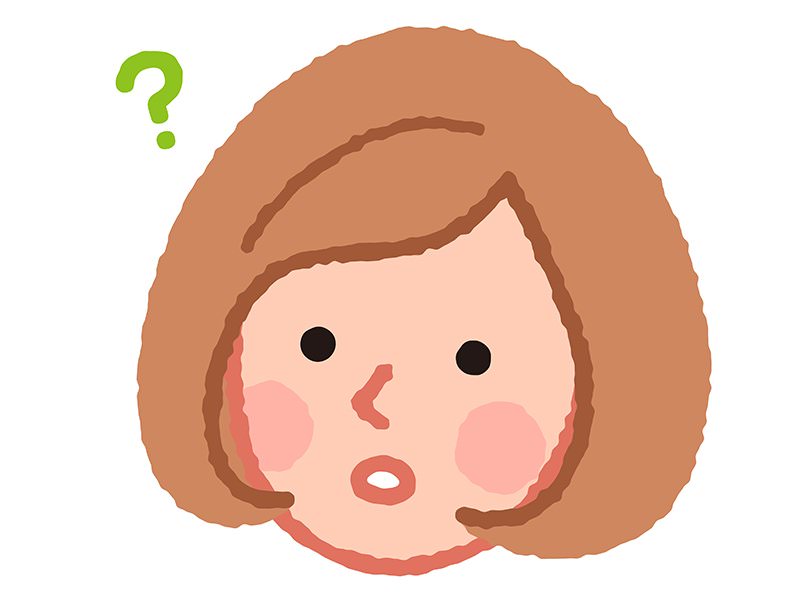
法定相続人に該当するかどうかはルールで決められています。
ルールよりも、どのような場合に法定相続人になるか知りたい方は、相続できる人は誰?パターンを多数ご紹介に個別的な事例を掲載しております。
また、相続税の基礎控除の額は法定相続人の数で決まります。
なので誰が法定相続人の該当するか、何人法定相続人になるかを把握することはとても重要です。
法定相続人は「相続人となると民法で定めている間柄の人」という意味なので、実際に財産を相続する人とは別になったりします。
例えば、あなたが遺言で法定相続人でない人たちにも財産を遺す予定であっても、その人達は法定相続人の数に含めないで計算します。
まず、「配偶者は法定相続人」となります。
ただし、民法上の正式な婚姻関係に基づく者をいい、内縁の関係にある者は含まれません。
もちろん愛人も含まれません。
次に被相続人(亡くなった方)と「一定の血族関係にある方も法定相続人」となります。
まとめますと、大前提として
が相続人となります。
なので、以下のようになります。
が法定相続人となります。
でも、一定の血族関係って?
そうです。
この一定の血族関係が少し厄介です。
配偶者は必ず法定相続人になりますが、血族であれば誰でも法定相続人なれるわけではありません。
法定相続人になれる順位があります。
正式な用語で書くと、以下のようになります。
直系卑属って?
代襲相続人って?
ちょっと難しいですよね。
正式な用語を簡単な事例で紹介しますと、以下のようになります。
また、上の順位に該当する方(例えば第1位に該当する方)がいる場合は、下の順位の方(例えば第2位,第3位に該当する方)は誰も相続人にはなりません。
この親族の関係は「戸籍ベース」で判断していきます。
もっと詳細に複雑なケースも知りたいという方は、法定相続人について完全解説している「法定相続人とは遺産相続の権利がある人で順位や範囲も決まってる」をご参照ください。
相続人になるのは誰?について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。