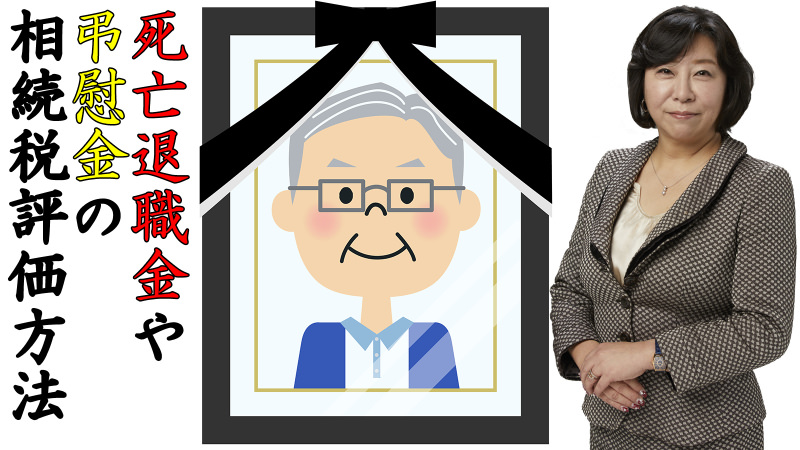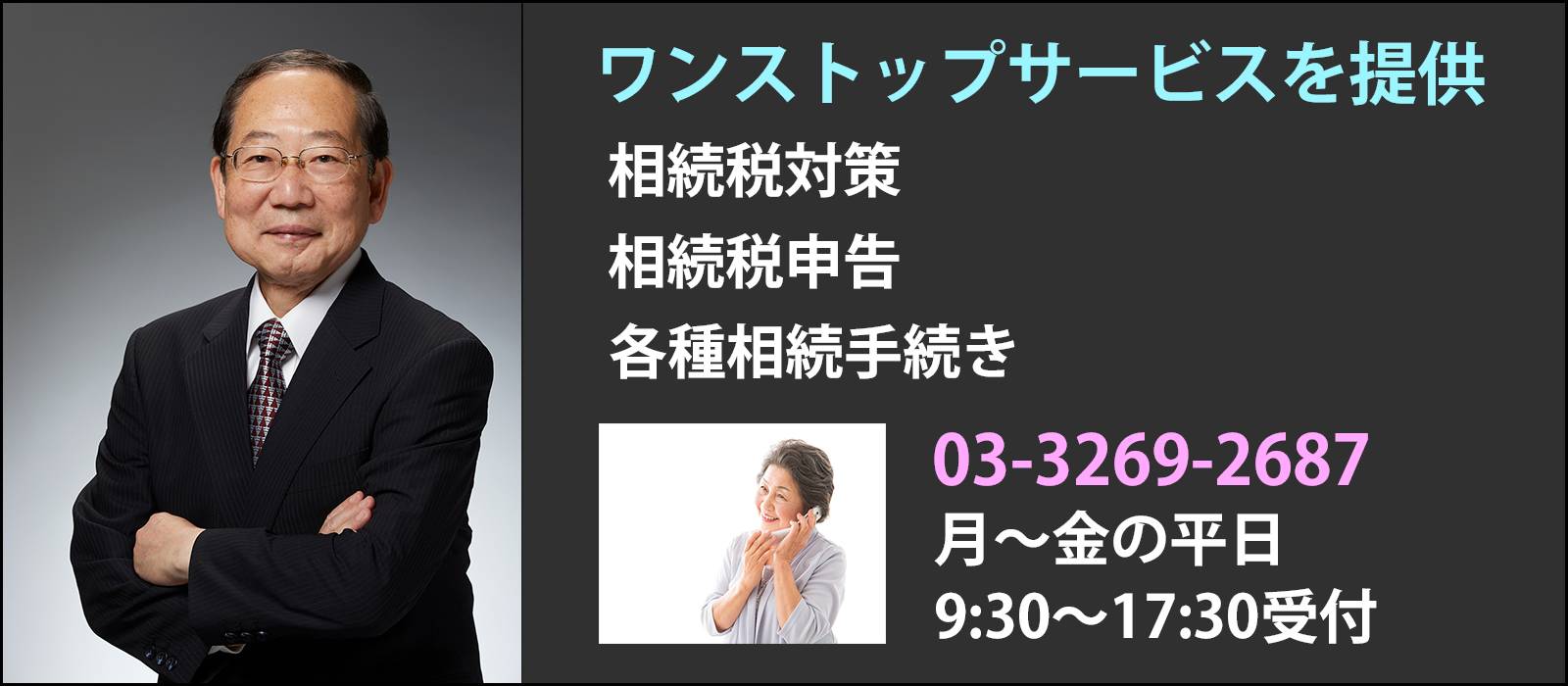死亡退職金は500万円まで非課税
死亡退職金の相続税評価額としては、額面の金額通りとなります。
ただ、死亡退職金には、生命保険金と同じ非課税枠というものがあります。
この非課税枠の金額は、「500万円×法定相続人数」となります。
そしてこの非課税枠は、
- 生命保険金
- 死亡退職金
それぞれ別枠です。
例えば、死亡保険金5,000万円、死亡退職金3,000万円、法定相続人4人の場合、それぞれの受取人がどの相続人であっても、相続税の対象になる金額は、死亡保険金3,000万円、死亡退職金1,000万円となります。
非課税枠の金額が2,000万円(500万円×4人)だからです。
ちなみに、この非課税は相続人でない人が死亡保険金や死亡退職金をもらった場合には、適用されません。
死亡退職金は被相続人の勤務先が加入していた企業年金などからの死亡退職金として支給されるものや、小規模企業共済などがあります。
そして、死亡退職金や生命保険金は、正しくは相続財産ではありません。
ただし、相続をきっかけに相続人が財産を受取れることからみなし相続財産として相続税の課税の対象としています。
相続税の課税の対象となることから、死亡退職金や生命保険金も考慮して、相続税対策を講じる必要があります。
弔慰金は原則非課税
死亡退職金の他に、会社から弔慰金を支給されることがあります。

死亡退職金の他に、会社から弔慰金を支給される場合があります。
この弔慰金は原則は非課税です。
ただ、以下の金額を超える部分については、退職金扱いとなります。
- 業務外死亡の場合で、月額報酬の6カ月の弔慰金
- 業務上死亡の場合で、月額報酬の3年分の弔慰金
例えば月給50万円の人が、業務には関係のない病気で死亡した場合で、会社から弔慰金として400万円を支給された場合には、100万円(400万-50万×6カ月)が退職金扱いとなります。
弔慰金以外に退職金があれば、その金額に100万を加算した金額が退職金となります。
相続放棄しても死亡退職金はもらえる?
被相続人本人に支払われるべき退職金であれば、相続放棄によって放棄者は退職金を相続出来ません。
ただ、退職金は会社の規約・規定によって作られます。
なので、会社ごとに退職金の制度が異なってきます。

退職金制度は、会社ごとによって異なってきます。
会社によっては、退職金の扱いが被相続人への支払いではなく、遺族に対する弔慰金への支払いとして、扱っているところもあります。
このような場合には、相続財産ではなく【遺族固有の権利】として、相続放棄者でも相続することが出来ます。
その退職金が遺産に相当するものなのか?
遺族の固有の財産に相当するものなのか?
で変わってくるということです。
ちなみに退職金が遺産であるなら、遺言で相続人や分け方を指定することも可能です。
また、相続人は会社に対し請求をすることも出来ます。
退職金が遺産でない場合には、死亡退職金について遺言で処分することは出来ません。
ちなみに、生命保険金受取人の変更は「遺言ですることが可能」になっています。
今までは、保険金を受け取る権利は、受取人の固有の権利であり、遺産を相続したものではないという考えでしたが、その考え見直され、遺言による受取人変更が可能となっています。

生命保険金受取人の変更は遺言ですることが可能
退職金が遺産に相当するものなのか?
遺族の固有の財産に相当するものなのか?
は一律で判断できるものではなく、会社の退職金の規約・規定で変わってきます。
退職金は普通の給料と異なり、必ずもらえるものでもありません。
退職金制度がない会社もあり、また、退職金制度がなくても違法ではありません。
そして、退職金制度はあっても、懲戒解雇の場合には、退職金が支払われないこともあります。
死亡退職金や弔慰金の相続税評価方法を動画で解説
死亡退職金や弔慰金の相続税評価方法について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
本日のテーマは、死亡退職金と弔慰金にかかる相続税についてです。
まずは死亡退職金からお話しを致します。
従業員が亡くなった場合、会社の規定によっては、その遺族に、退職金が支払われることがあります。
もしこの退職金が、亡くなってから3年以内に金額が確定したものである場合、これは遺族の相続税の対象となります。
本来、このような形で受け取る退職金は、会社の規定で遺族に直接支払われますから、その遺族の固有の財産にあたります。
相続財産ではありません。
しかし、これは実質的には、亡くなった人の退職金です。
そこで相続税のルールでは、これを相続財産とみなして、相続税を課すこととしています。
これを、みなし相続財産といいます。
しかし、死亡退職金の全額に対して、相続税を課すことはしません。
なぜなら、通常、退職金とは家族にとって、その後の生活保障のために不可欠なお金だからです。
こうした事情を考慮して、死亡退職金は、一定の金額まで非課税になります。
非課税となる額は、法定相続人の数×500万円、これが上限です。
たとえば、法定相続人が4人いる場合、500万円×4人で2,000万円まで非課税で受け取ることができます。
もし死亡退職金が3,000万円であれば、相続税の対象になるのは、残りの1,000万円だけです。
ただし、相続人ではない人が受け取った死亡退職金については、非課税の適用はありません。
続いて弔慰金についてお話しします。
死亡退職金とは別に、会社から遺族に支払われるお金として、弔慰金というものがあります。
弔慰金は、死者を弔う気持ちで支払われるものなので、死亡退職金とは異なります。
弔慰金は、香典などと同じように、通常は誰にも税金はかかりません。
しかし、弔慰金の金額が大きいと、相続税のルールでは、それって実質的には退職金じゃないのか?という考え方をします。
このことから、基準額を超える高額な弔慰金については、死亡退職金として、相続税の対象にすることとしています。
基準額は、亡くなった人の死が業務上のものである場合と、業務外のものである場合で変わってきます。
もし死亡した理由が業務上のものであれば、死亡当時の月額報酬の3年分、これが基準額となります。
死亡した理由が業務外のものであれば、基準額は月額報酬の6か月分です。
基準額を超える部分が、死亡退職金の扱いとなります。
相続に関するお悩み等がございましたら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。