
特別受益の持ち戻しを無視させる方法
被相続人(故人)が遺言や生前に「特別受益の持ち戻しをしない」という意思表示をすれば、相続の際に特別受益を無視して遺産分割することができます。
被相続人(故人)が遺言や生前に「特別受益の持ち戻しをしない」という意思表示をすれば、相続の際に特別受益を無視して遺産分割することができます。
特別受益とは法定相続人の間で公平を図るため、生前贈与や遺贈などで特別にある特定の法定相続人だけ財産を優遇されていた場合、その優遇されていた財産を相続財産に戻し、相続人間で平等に相続させようとするものです。
しかし、この特別受益にあたると考えられる場合でも、持ち戻しをしなくてもよい方法があります。
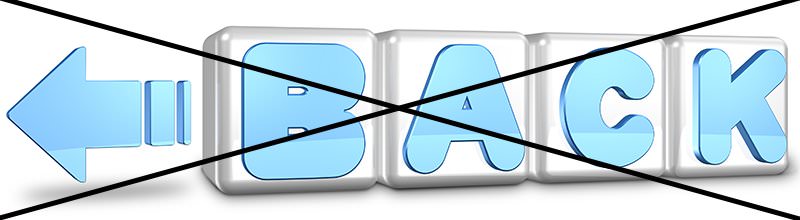
それは特別受益の持ち戻し免除の意思表示というものです。
特別受益の持ち戻し免除の意思表示とは、被相続人(故人)が遺言や生前に「特別受益の持ち戻しをしない」という意思表示をしれば、持ち戻しをしなくてよいとするものです。
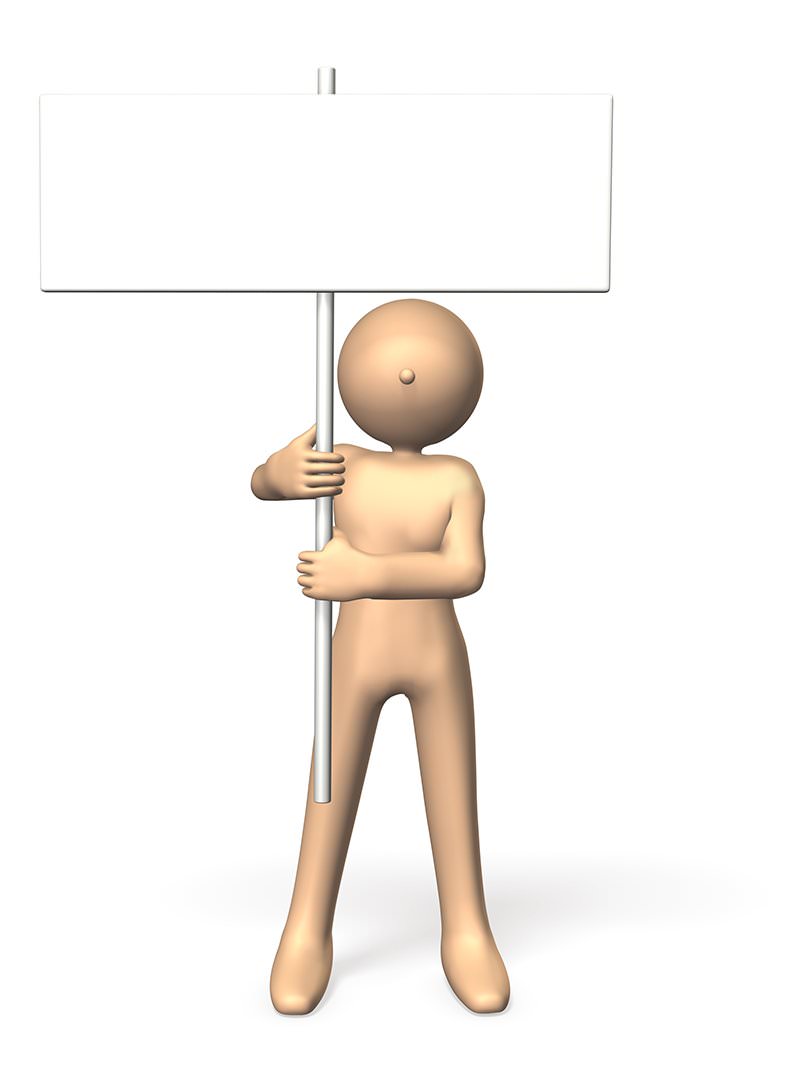
特別受益の持ち戻し免除の意思表示は財産をあげる側がするものです。
もらう側ではありません。
この特別受益の持ち戻し免除の意思表示はどういう時に使うのか?
例えば被相続人のある特定の人に対する贈与が、遺産の前渡しとしてではなく、特別にその人にあげたものという場合があります。
そのような場合に特別受益の持ち戻し免除の意思表示をすれば「持ち戻しをしなくてもよい」ことになります。
持ち戻しの免除の意思表示の方法は決まった方式はありません。
口頭だけでも形式上は問題ありません。
贈与の場合であれば、贈与と同時ではなく後から意思表示することでも可能です。
ただ、言った・言わないとの争いになりやすいので、書面などで形に残るようにしておきましょう。
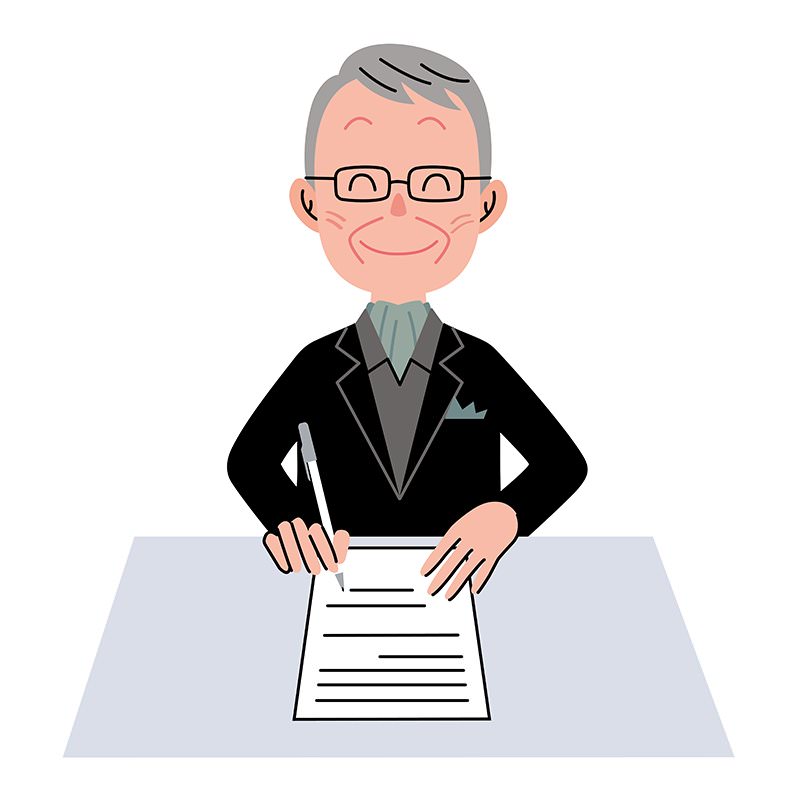
一般的には遺言に特別受益の持ち戻しの免除について記載する方法がとられています。
遺言に「持ち戻しは必要ない」と記載するということです。
例えば遺言書に「Aにした生前贈与による特別受益の持ち戻しについては、全て免除する。よって遺産分割で問題にしないこと」と記載されていたとします。
この場合、他の相続人はそれに従う必要が出てきます。
他の相続人が「Aには特別受益があるから遺産相続財産を減らすべきだ」と主張できなくなるということです。

ただ、この特別受益の持ち戻し免除は相続争いに発展しやすくなりますので、後の相続人間のことも考えて慎重に検討しましょう。
特別受益の持戻し免除の意思表示について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
「特別受益の持ち戻し」、まずこれが何なのかといいますと、相続人同士の公平を図るための制度です。
たとえば相続人のうち1人だけが特別に生前贈与を受けていたり、遺言書で特別な贈与を受けたりすると他の相続人は不公平を感じるかと思います。
そして、このような特別な形で贈与された利益のことを「特別受益」といいますが、民法では特別受益によって不公平な相続が起こらないように、特別受益は「相続財産に持ち戻す」というルールがあります。
たとえば相続人が長女・次女・三女の3人で、相続財産が5,000万円あったとします。
普通なら1人あたりの相続分は5,000万円を3等分した金額となります。
しかしここで長女だけに生前に1,000万円の特別受益があったことがわかったとしましょう。
すると、この1,000万円は相続財産に戻されるので、5,000万円に1,000万円を加えた6,000万円を3人で分けることとなります。
そうすると1人2,000万円ずつですので、次女と三女は2,000万円ずつ相続する権利があります。
しかし長女は特別受益を差し引いた残り1,000万円となります。
このように特別受益が認められると、贈与を受けていない他の相続人は相続のときの取り分が多くなります。
そのため「あの時、お姉ちゃんだけお金を出してもらっていた」のような特別受益の探し合いになり、争いの火種になることがあります。
それでは前置きが長くなってしまいましたが、特別受益の持ち戻し免除の意思表示の説明に入ります。
「特別受益の持ち戻し」には一つ例外があります。
それは被相続人、つまり亡くなる人が生前に「持ち戻しをしないで欲しい」という意思表示をしておけば、その意思が優先されるというものです。
ということは、この意思表示をしておけば少なくとも意思表示をした贈与に対しては、特別受益を主張されずにすみます。
意思表示の方法に特に決まりはありませんが書面で行うことが望ましいです。
ですので遺言書に記載するケースが多いと言えます。
たとえば「長女にした生前贈与による特別受益の持ち戻しについては、全て免除する。よって遺産分割で問題にしないこと」のような内容を遺言書に記載しておきます。
ただし免除することによって、かえって他の相続人の感情を逆撫でする可能性もあります。
あまりに不公平感のある特別受益であれば、何もかも免除してあげるというのも考えものです。
相続人同士の関係性も考えて慎重に検討しましょう。