
保証債務や連帯債務は相続財産から控除できる?
借金を相続した場合、その借金は相続財産から控除できます。ただ、保証債務や連帯債務は原則、控除できません。保証債務や連帯債務を債務控除するためには、一定の条件を満たす必要があります。
借金を相続した場合、その借金は相続財産から控除できます。ただ、保証債務や連帯債務は原則、控除できません。保証債務や連帯債務を債務控除するためには、一定の条件を満たす必要があります。
借金を相続した場合、その借金は相続財産から控除できます。
たとえば現金1,000万円を相続し、また被相続人の借金1,000万円も相続した場合には、プラスマイナス0円となり相続税は発生しません。
このように被相続人の負の財産を相続する場合には、プラスの財産から控除できます。
ちなみに借金は相続開始時点では、各相続人の相続分に応じ、それぞれ等しい割合で義務を負います。
その後の遺産分割などで、特定の相続人が被相続人の借金を相続すると決めた場合、その相続人間の間では有効となります。
ただ、遺産分割協議では借金の相続をする相続人が決まっているのに、銀行などがその相続人の支払能力などを勘案し認めない場合もあります。
その場合、債務者の名義変更ができませんので注意が必要です。
債権者である銀行などが認めた場合に、債務者の名義が変更できます。
保証債務が債務控除できる条件や金額は以下のようになります。
この3つの条件全てを満たし上で、主たる債務者が弁済不能の金額のみ、保証債務者の債務として控除できます。

連帯債務が債務控除できる条件や金額は以下のようになります。
この2~4の条件を満たした場合、1の本来負担すべき金額に、4の当該弁済不能者の負担部分の金額も債務控除することができます。
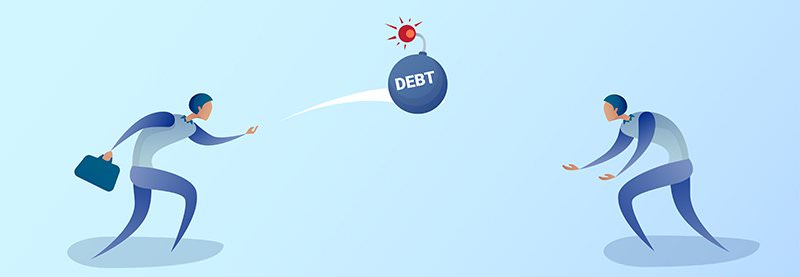
被相続人(Aさん)に借金がなく、問題なく相続できると思っていた矢先、被相続人の銀行口座のみならず、自身(相続人Bさん)の銀行口座も凍結されている。
どういうことか?
なぜ自分の銀行口座まで凍結されているのか?
この場合、被相続人の保証債務などを相続している可能性が高いです。

たとえば被相続人(Aさん)の父親(Cさん)が、被相続人の弟(Dさん)の借金の保証人になっていたとします。
Cさんの相続の際に、Aさんは相続放棄をしていませんでした。
そして、Cさんの連帯保証債務をAさんが相続。
そしてAさんが亡くなるとすぐに、その弟のDさんも亡くなり・・。
そうなるとAさんはDさんの保証をしていることになっていますので、Aさんの相続でBさんにそれが相続され、Bさんの銀行口座が凍結される・・
保証債務や連帯債務が被相続人にあることが分かっていれば
などの対策を考えられますが、被相続人に保証債務があるどうか不明の場合には、ある日突然、相続人の銀行口座が凍結されているような事態も考えられます。
相続が発生した場合には被相続人の借金はもちろん、保証債務や連帯債務がないかどうかの確認もしましょう。
保証債務や連帯債務が「相続財産から控除できるかどうか」について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
相続では現金などプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続人に承継されます。
ただし、マイナスの財産を相続した人は、相続税の計算において債務控除を受けることができます。
債務控除とはマイナスの財産をプラスの財産から控除して、相続税を計算できる制度です。
もし父親Aさんが亡くなって、その長男がAさんの現金1,000万円と借金300万円を相続した場合、1,000万円から300万円の債務控除を受けることができるので、差額700万円が長男の課税対象となります。
ところが亡くなった人の借金が保証債務や連帯債務の場合、債務控除は原則として適用できません。
保証債務というのは借金の主たる債務者が別にいて、その人が返せなかった場合の保証人となっていることです。
たとえば父親Aさんがその弟Bさんが作った借金300万円の保証債務を負っている場合、もしBさんが借金を返せなくなったときに、Aさんが代わりに300万円を返さなくてはならないという債務になります。
また連帯債務とは、債務者がそれぞれ借金を返済する義務を負います。
たとえば父親Aさんが弟Bさんの借金300万円の連帯債務を負っている場合、Bさんが返せなくなるかどうかに関係なく、Aさんの元に返済の請求がやってくることもあるということです。
保証債務と連帯債務とでは返済義務の重さはだいぶ違いますが、相続税の計算においては、どちらも債務控除の対象には原則なりません。
なぜなら債務控除の対象になるのは、負担する債務の金額が確定しているものに限られるからです。
保証債務の場合、Bさんが借金をきちんと返せばAさんは返済しないで済みますし、仮にBさんの代わりに返済してあげたとしても、AさんはBさんに返すよう請求できますので、Aさんの負担がいくらになるのかまだわかりません。
連帯債務もAさんとBさんで300万円を返済する約束ですから、Aさんがいくら負担してもよいため負担額は確定していません。
このように負担額がはっきりと決まっていないという点から、保証債務や連帯債務は債務控除の対象とすることが原則できないのです。
ただし特別な事情があって、負担額がはっきりとしているときは、債務控除を適用できるということがあります。
保証債務の場合、弟Bさんが返済できない状態で、父親Aさんが返済しないといけない状態にあり、かつ、弟Bさんから返還を受けられる見込みがない状態であれば、債務控除を適用できる余地もあります。
連帯債務の場合、父親Aさんの負担する金額がもともと100万円と決められているときは、その100万円について債務控除を適用できる余地があります。
またこのとき弟Bさんが50万円について返済不能となり、その50万円も父親Aさんが負担しなければならず、後にBさんから返還を受けられる見込みがないときは、父親Aさんがもともと負担すべき100万円に、Bさんから請け負った50万円をプラスして債務控除を適用することもできます。
ただし借金のある相続では、債務控除が適用できるかどうかというよりも、まず、その借金を本当に自分が負担できるかどうかを考えて、相続をすることが重要となります。
自分ではどうしようもできない借金があるときは、相続放棄や限定承認の手続きを行いましょう。
そして、その判断を正しく行うためには、日頃から借金がいくらあるのかをご家族できちんと共有していくことが重要です。