
遺産分割が申告期限までにまとまらない場合は未分割申告
遺産分割が申告期限までにまとまらない。そのような場合、未分割申告をすることになります。ただ、未分割申告には様々なデメリットがあります。
遺産分割が申告期限までにまとまらない。そのような場合、未分割申告をすることになります。ただ、未分割申告には様々なデメリットがあります。
遺産分割が申告期限までにまとまらない場合には、未分割の状態で相続税の申告を申告期限内にします。
(通常、未分割申告と言われます。)
ちなみに民法では遺産分割の期限はありません。
なので、一般的には遺産分割の期限と言えば「相続税の申告期限」のことを指します。

ただ、相続税の申告期限内(相続開始から10か月以内)に遺産分割できないと、分割していない財産は相続人の共有状態のままとなり、様々な特例などが使えない(相続税対策が出来ない)、財産の管理が面倒などのデメリットが発生します。
では、デメリットがあるにも関わらず、なぜ未分割申告になってしまうのか?
大きく分けると、以下の3つのパターンがあります。
3は相続人の中に「20歳に近い未成年者がいる場合」に、あえて未分割で申告し、その未成年者が成人になるのを待って遺産分割をする場合などです。
本来、未分割申告は極力避けるべきですが、上記の1~3のような理由により、未分割申告をせざるを得ない場合もあります。
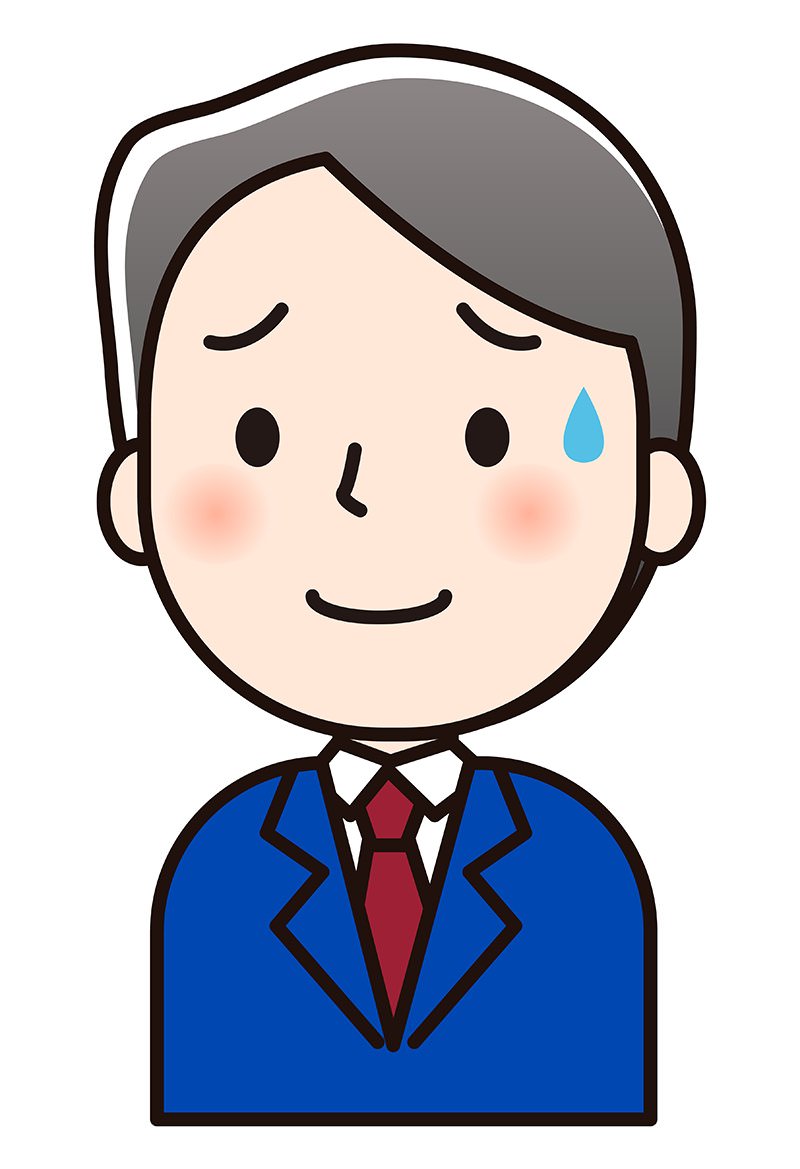
ちなみに未分割の遺産については、法定相続分や代襲相続分の割合に従って、その遺産を取得したものとみなして相続税額を計算することになります。
未分割申告にはデメリットがあります。
簡単に言えば、未分割申告は相続税対策ができないうえ、財産の管理が面倒になるなど、損をする可能性が高くなります。

具体的なデメリットは以下のようになります。
未分割申告のデメリット
2の物納に関しては、共有者全員が持分全てを物納する場合には物納の申請をすることはできます。
1~4については、申告期限までに遺産分割が確定してなくても、申告期限後3年以内の分割見込書を相続の申告期限内に提出すれば、未分割であった遺産が相続税の申告期限から3年以内に分割された場合、その分割された日から4カ月以内に更正の請求を行えば適用されます。

適用を受けることにより、納税済みの相続税額が多かった場合は、その多額であった部分の金額は【還付】されます。
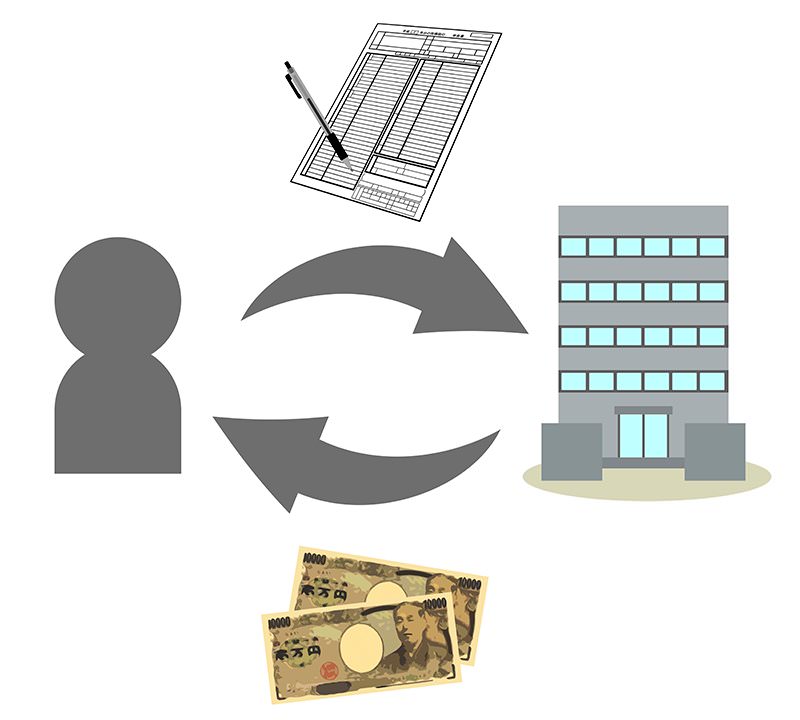
5~9については、申告期限までに遺産分割が確定している必要があります。
申告期限を過ぎてから適用されるということはありません。
相続税対策などを考えると、未分割申告は極力避けるべきです。
また、長期にわたる遺産分割協議は相続人の精神的負担も高くなります。
遺産分割協議がまとまらない場合には、有効な相続税対策が打てなくなる可能性があることを意識しましょう。
また、遺産分割が難航している場合には、未分割申告のデメリットを相続人間で共有しましょう。

未分割申告について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
突然ですが遺産分割に期限はあるのでしょうか?
実は民法で遺産分割の期限は定められていません。
ただ、相続税の申告期限というものがあります。
それはある方が亡くなった日、これを相続開始と言いますがその日から10ヶ月以内、正確には死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告をしなければなりません。
そのためにも遺産分割を相続税の申告期限までにする必要があります。
けれども、どうしても申告期限までに遺産分割がまとまらない場合もあります。
その場合には未分割の状態で相続税の申告をします。
このことを「未分割申告」と言います。
さて、分割していない財産は相続人全員が権利を持っている状態、つまり共有状態になります。
こうなると税金の特例が使えないので、相続税対策ができないうえ財産の管理が面倒になるなど、損をする可能性が高くなります。
しかし損をするとわかっていても、未分割申告になってしまう場合があります。
それは大きく分けて3つのケースがあります。
1つ目は相続人の間で分割の話し合いがまとまらないケースです。
「兄弟は全員平等なはず」
「俺はお父さんと同居して最後まで面倒をみたのにそれを無視するのか」など揉めるケースです。
2つ目は申告期限までに財産の把握ができていないケースです。
「お父さんがそんな遠くに土地を持っていたなんて知らなかった」
「お母さんが銀行じゃなくて、郵便貯金してたなんて全然知らなかった」などです。
3つ目はあえて未分割で申告を行うケースです。
「一番下の妹はまだ18歳で未成年だから、成人してから相続しよう」このような理由で未分割申告をあえて選択する場合もあります。
ちなみに未分割申告の相続税の計算方法は、法律で決められた相続分である法定相続分で遺産を相続したとみなして計算をします。
ところで未分割申告をすると、なぜ損をすることになるのでしょうか?
その損について相続人が理解したら、もしかすると遺産分割が進むかもしれません。
そこで、どんな損をするのかをお伝え致します。
【1つ目】相続税を軽くするための様々な特例が使えません。
【2つ目】基本的に物納が出来ません。
【3つ目】納税猶予が適用されません。
このうち1つ目が一番大きな損になります。
配偶者に対する税額軽減や小規模宅地等の特例など、相続税を軽くするための特例はたくさんあります。
しかし未分割申告をすると、これらの特例が使えなくなります。
ただ未分割申告をする時に申告期限後3年以内の分割見込書を提出し、申告期限から3年以内に遺産分割をすれば、配偶者に対する税額軽減や小規模宅地等の特例などは使えます。
特例を使って計算した相続税が、未分割申告の際に納税した相続税額より少なかった場合は差額が戻ってきます。
ただ、非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除など、分割見込書を提出しても使えない特例はあります。
このように未分割申告は相続税で大きな損をする可能性があります。
そして長い間、兄弟や親族で揉めているとお互いに心が疲れてしまう、ということも見過ごせません。
本来、身近で助け合わなければならない親族がいつまでも遺産分割の話し合いをまとめられないのは、亡くなった方から見たらどうなのでしょうか?
遺産分割協議を相続税の申告期限までにまとめるのが一番の孝行です。
せっかく残してくれた財産にみすみすたくさんの相続税を掛けられ減らされないように、相続人みんなが「未分割申告をした時にはすごく損をする可能性がある」という認識を持って円満に遺産分割の話し合いを行えるようにしましょう。