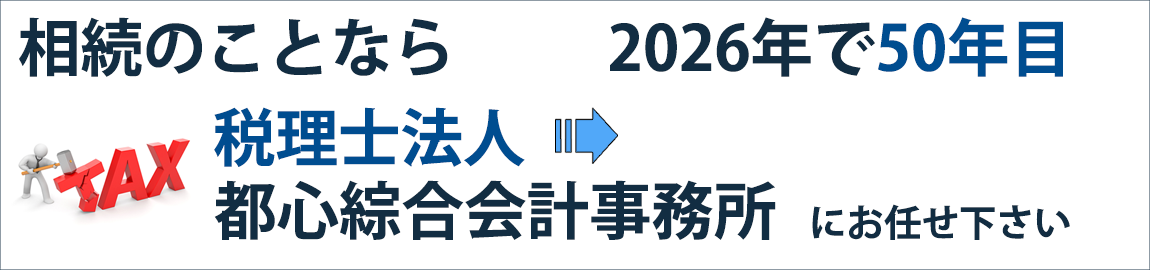
遺産の現物分割は簡単だが不公平感が生まれやすい
遺産の現物分割は、代償分割や換価分割のような手間がかからないというメリットがあります。ただ、法定相続分通りに遺産分割することが困難ということもあり、不公平感が生まれやすいデメリットもあります。
遺産の現物分割は、代償分割や換価分割のような手間がかからないというメリットがあります。ただ、法定相続分通りに遺産分割することが困難ということもあり、不公平感が生まれやすいデメリットもあります。
遺産分割の大前提として、遺言書があろうとも、相続人の遺産分割協議により自由に遺産分割することができます。

ある人に全てを相続させることも、他の相続人の全員が合意していれば問題なくできます。
そして遺産分割の方法には、多く分けて以下の3つの方法があります。
共有とする分割を現物分割に含めず、別の分割方法(共有分割)としてご紹介している方もいますが、当サイトは共有分割は現物分割に含まれるものとして記載致します。
現物分割とは、遺産をそのままの状態で分け合う方法です。
いわゆる「財産目録の項目」で分配する方法とも言えます。
例えば
などといった具合です。
そして遺産として土地が一つしかない場合などには、長男・次男・三男で1/3ずつ共有するということも現物分割となります。
遺産をそのままの姿で相続するのが現物分割です。
そのままの姿で相続するので、現物分割は代償分割や換価分割のような手間がかからないというメリットがある反面、相続人間で不公平感が生じやすいというデメリットがあります。
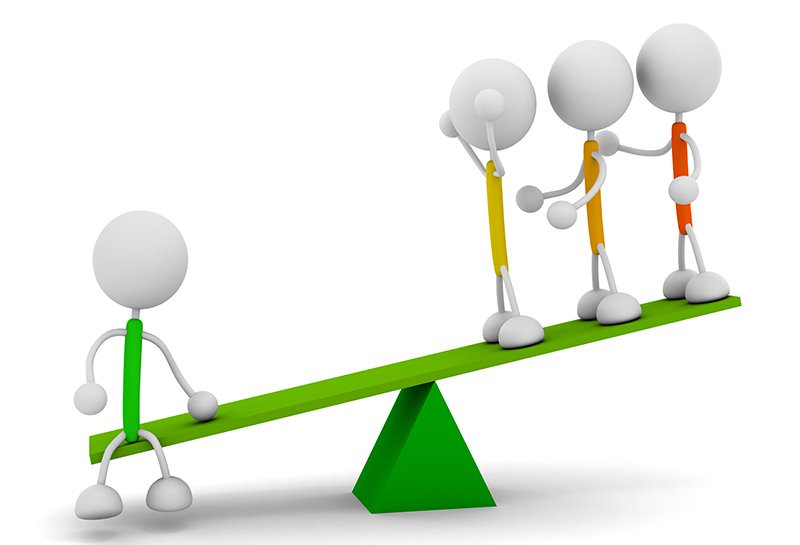
特に遺産が現金ではなく不動産が多い場合には、不動産ごとに評価額が異なってきますので、財産評価額を基準に分割するというのは、現実的に厳しいものがあります。
そこで共有分割という方法も考えられるのですが、共有分割は極力避けるべきです。
詳しくは共有での遺産相続は避けるべき!次世代にトラブルの元を残さないにて記載しています。
現物分割で相続する場合には
ということを相続人間で共有しましょう。
また、場合にもよりますが現物分割の場合、各種の特例(小規模宅地等の特例など)が適用しやすくなるといったことも挙げられます。
相続相談・相続税対策・相続手続・相続税申告なら東京新宿神楽坂の税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。
遺産の現物分割について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
現物分割という表現は聞き慣れない方も多いかと思いますが、これは遺産をそのままの形で分けることをいいます。
たとえば遺産に自宅、別荘、車があったとき、長男は自宅、次男は別荘、三男は車というような分け方を現物分割といいます。
1人1つずつのような方法で分ける以外にも、複数の人で共有名義として相続することもできます。
たとえば自宅を3人で3分の1ずつ共有することも可能です。
ただし1つのものを複数の人が共有することによって、発生するトラブルもあるためにおすすめはしていません。
さて現物分割のメリットとしては、手間がかからないということがあげられます。
財産をそのままの形で受け継ぐわけですから、わかりやすい上に換金などの手続きも必要ありません。
また小規模宅地等の減額特例といって、土地の相続に活用できる、相続税の特例も活用しやすくなることがあります。
その一方で現物分割には相続人のあいだで不公平感が生まれやすい、というデメリットもあります。
たとえば、さきほど長男が自宅を次男は別荘を三男は車を相続する例をあげましたが、自宅の評価額が5,000万円、別荘も5,000万円、車だけ100万円というような差があったら、よほどの理由がなければ円満に分けることはできないでしょう。
現物分割には、こうしたメリットとデメリットがあります。
このことを踏まえて、うまく活用致しましょう。